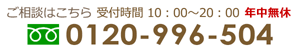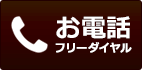4月。
新年度がはじまった。学校でも職場でもフレッシュな気分で、新しいものごとに挑戦していく時節だ。わたしも職場や労働環境が微妙に変化した。しかし半世紀以上、甲羅を経た生きものなのでさすがに「フレッシュ」な気分とは、ほど遠い。
自分にとってフレッシュだったのは、札幌での大学進学や上京しての企業就職である。大学では日本中からやってきた、さまざまな学生と知り合う機会があった。視野が一気にひろまった。
香川県出身の級友はカップ麺を食べた後、割り箸を捨てた。「え! 1回しか使ってないのに?」とびっくりして声をあげ、笑われた。経年劣化で素材が自然に磨滅する(ある日突然、ポキッと折れる)まで、割り箸は使い回すものだと思っていたのだ。「視野がひろまった」って、割り箸かよ、と思われるだろう。まったくその通り。そのレベルですらカルチャーショックだった。いわんや、それ以外の出来事においてをや!
たとえば7・8月の夏休み明け、9月1日からはじまる前期末試験にむけ、クラスで「訳本」を作ることになった。英語は第1外国語で全員必修の授業が多い(文学・法学・経済学・教育学部共通のクラスだった。教養学部と呼ばれた。英語演習などは戯曲を読んだり、会話を練習したり、選択科目だったかな)。優良可不可で成績がつくが、「クラス上位10パーセントが優」などという縛りはない。全員の成績がよければ、全員で「優」が取れる。
そこで協力体制がしかれた。試験範囲をクラス10人ほどで分担し(40人ほどのクラス)、全文日本語訳の「訳本」を作ることになったのだ。ところが、「訳の文体」を統一しなかった。その結果、次のような訳文ができ上がった(以下、誇張あり)。
「時間は貨幣だということを忘れてはだめだよ。1日の労働で10シリング儲けられるのに、外に遊びに行ったり、室内でだらだらして半日を過ごしちゃうと、娯楽やグータラのためにはたとえ6ペンスしか支払っていなくてもさ、それを勘定に入れるだけではダメダメ。ほんとは、そのほかに5シリングの貨幣を支払っている。いや、むしろ捨てているってわけだよーん」(ちびっこ訳)
「信用は貨幣だということを、忘れてはいけませんわ。誰かが、支払い期日が過ぎてからも、その貨幣をわたくしの手元に残したとすれば、よろしいかしら、わたくしはその貨幣の利息を、あるいはその期間中にその利息で出来た何かを、相手から与えられたことになりますのよ。もし大きい信用を十分に利用できたら、それは少なくない金額に達するでしょうね。おほほほほ」(貴婦人訳)
「貨幣は繁殖し、子どもを生むことを忘れてはいかんのじゃ。貨幣は貨幣を生むことができる。またその生まれた貨幣はいっそう多くの貨幣を生める。さらに次々と、同じことが行われるのじゃ。ごほごほげほ」(おじいさん訳? 博士訳?)
「あのね、支払いのよいひとは他のひとのお財布にも影響力をもてる――そういうことわざがあることを忘れちゃだめでちゅ。約束の期限にちゃんと支払うって評判になっているひとは、友だちがさしあたって必要じゃない貨幣を、いつでもみんな借りることができちゃうでちゅ! ばぶばぶー」(赤ちゃん訳)【注】
「これじゃ、読みにくくってしようがないだろう」と思われよう。ところが、これが大評判。みんな、面白ければなんでもいいらしい。昔の大学生は一般にバカだったと思う(なかには優秀な学生もいた)が、特に80年代の大学生はバカだった。「大学のレジャーランド化」が話題になった時代だ。ただし、2年の後期からわたしが移行した文学部文学科の国文(日本文学)はまったく事情がちがった。概論でも演習(ゼミ)でも、徹底的にしごかれた。
とはいえ、基本はバカ。ことばの最後に「ちょふ」をつけるのが流行(はや)ったことも。
「田中ー。ちょっとノート貸して」
「だめちょふ」
「佐々木さん。一緒に学食でランチ食べよー」
「むりちょふ」
いったいなんなのか(困惑)。
旧ソ連の要人に「フルシチョフ」「ゴルバチョフ」というひとたちがいる。しかし、関係があるのかどうか、さっぱりわからない。ともかく面白ければよいらしい。軽薄きわまりない。
訳本の話に戻る。みなの原稿を集め、コピーし、冊子(さっし)にしたのはわたしだった。おっちょっこちょいで目立ちたがり屋だったのだ(恥)。当時つき合っていた彼女が「英米文学の翻訳家」志望で、「勉強になるから、わたしの分担、多めにしていいよ」といってくれた。現在のようにPCはなく、デジタル環境ではない。ルーズリーフやノートに手書きの原稿を集め、コピーし、ホチキス止めして冊子にした。すべて「紙」による手作業。
これを1冊500円で売った。クラス30人弱が購入したから、約1.5万円である(翻訳スタッフには無料配布)。作業はめんどうだが、経費はそんなにかかっていない。ぼろ儲けなのだ。うふふふふ。
「9月1日、休み明けに教室でみんなに配布するねー」と告知していた。ところが、8月31日、わたしは彼女と大ゲンカしてしまう。原因は都合よく記憶にない。この彼女とはものすごく仲よく、いちゃいちゃした一方、やたらとケンカもしていた。ともかく互いに遠慮がない。いいたいことしたいこと、あけすけに自由にぶつけ合った印象だ。19歳だったからなー。
「あたし明日、学校に行かないから!」(ガチャン!)
と電話を切られた。あ、「ガチャン」は受話器を本体に置いて回線を切ったときの音である。個人の電話などもっていなかったから、彼女は自宅の電話(固定電話)、わたしはアパートの共有ピンク電話(10円入れて話す)で会話していた。
さあ、困った。翌日、クラスメイトに配布する訳本冊子約40冊は彼女の家にあり、彼女が学校に持ってくることになっていたのだ。代金はすでに徴収ずみ。これでブツがなかったら、「オーモリー! きさま、どういうことだ!?」と全員からつるし上げをくらうのは必至。
そこでわたしは決心した。
(よし! 彼女の家まで行って謝罪し、誠意を見せよう!)
彼女の自宅は札幌市西区山の手。クマが出没する山の方である。閑静な住宅街であり、決して「山奥」ではないが……。このとき、時刻は23時。わたしは北区麻生(あさぶ)に住んでいた。地下鉄の最終は当時、ちょうど23時ごろ。もう間に合わない。市営バスの最終は22時半ごろだ。つまり、公共交通機関は利用できない。割り箸を使い回す貧乏学生なので、車もない。そもそも運転免許がない。
6月ごろだろうか。彼女の家にいちどだけ、遊びに行ったことがあった。麻生から琴似(ことに)に向けて「琴似栄町通り」という幹線道路がある。ここがバス通りになっている。市営バスに乗ってまず、琴似へ。琴似のバスターミナルから山の手行のバスに乗り換える。そして、「山の手X条」というバス停で降車。あとは住宅街をてくてく歩き、ご自宅まで。土地カンは、ほとんどない。道をおぼえているだろうか? いや、その前に「山の手X条」まで、どうやって行く?
ひらめいた。麻生の隣の地下鉄駅「北34条」に級友が住んでいる。彼は自転車をもっているのだ。事情を話して貸してもらえないだろうか? そいつのアパートに行ったことはない。しかし、クラス名簿がある。当時、個人情報保護という観念が希薄だった。みなの住所や出身高校、連絡先などをその名簿で確認できる。頭に叩きこみ、アパートを出た。多少まよいながら、なんとか彼の住所に行きつく。(留守だったら、どうしよう?)と思ったが杞憂(きゆう)だった。在宅だったので、事情を話し、「自転車、貸してくれ」と訴える。
「いいよ。のってけ」
ひとつ返事で、気軽にOK。こいつには今でも頭が上がらない。
すでに0時。自転車に乗って「琴似栄町通り」を南西に向かう。当時、「札沼(さっしょう)線」(札幌と石狩沼田を接続)という線路があり、この踏切をこえる。今は「学園都市線」と名前が変わり、高架になっている(ネットで確認すると「学園都市線」は愛称らしい。現在は石狩沼田までの路線は廃止され、北海道医療大学駅まで)。この数年後、1989年という昭和の終わりを舞台に、島田荘司が「札沼線」で渾身の時刻表トリックを炸裂させる。もちろん、当時のわたしには知るよしもない。『奇想、天を動かす』(1989)である。
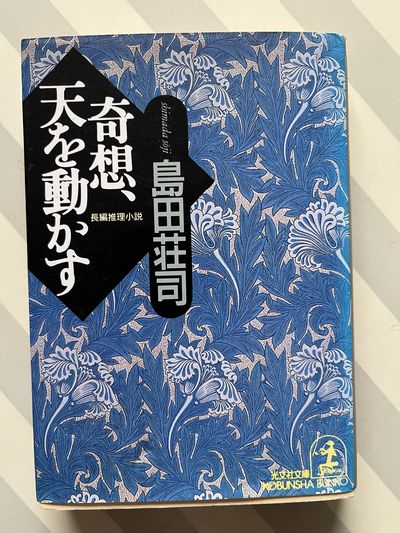
0時半に琴似到着。ここまでは「一本道」だったから迷いようがない。ところが、琴似から山の手までの行程はバスに乗って受動的に移動していた。まったく記憶に残っていない。もちろん、スマホの地図アプリもない。あせった。しかし、ここまで来てあきらめるのはバカらしい。なにか方法はないか……。
ひらめいた。
当時、バス停の表面は「時刻表」だが、裏面には「バス路線図」が掲示されていた。これを地図のように利用し、ひとつひとつのバス停を確認しながら潰していく。そうやって徐々に、「山の手X条」に近づいていけないか……。
やってみると、これがうまくいった。曲がるべき道で曲がらない、直進すべき道で曲がってしまうなど、途中、行きつ戻りつしながら、なんとかバス停をひとつひとつクリアしていく。困惑、混乱したのが「夜の街」だったことだ。いちどだけ、この道をたどったときは「昼の街」だった。すると、「街の表情」がまったくちがうのである。ぜんぜん知らない、別の街に思える。
それでも迷いつつ、どうにかこうにか「山の手X条」になんと、たどりついたのだ。やればできる! オレ、すごい! このとき、午前1時。すでにじゅうぶん、カレンダー上は9月になっていた。
今でも記憶にあるが、この年――1985年の札幌は記録的に暑い夏だった。ネットで確認すると8月の最高気温は34.7度。31日の最高気温29.4度、最低気温22.5度である。通常、「お盆を過ぎると秋」といわれる北海道だが、この夜にはまだたっぷり「夏の余韻」が残っていた。
住宅街は、しんと静まり返っている。住民たちは平和な眠りにおち、不審人物の若造が侵入したことに誰も気づかない。(道を忘れているのでは……)という危惧は、取り越し苦労だった。来てみると、風景に見覚えがある。(この角は右)(ここはまっすぐ)と記憶がよみがえる。
そしてとうとう、彼女の住んでいる家が見えてきた。き、緊張する。
当然ながら、居間のベランダの窓、それぞれの部屋の窓、すべて真っ暗。誰も起きていない。寝静まっている。現在のように携帯端末などない。ラインで彼女にだけ連絡を取ることは不可能。なんとかして家のひとに知られず、彼女だけ起こしたい。
ふつうに玄関のチャイムを押すことは、ありえない。ピンポン、ピンポーンと連打し、金属バットをもったお父さんが「きみはだれだ?」と出てくる事態は避けたい(当時、金属バットを凶器にした尊属殺人事件が話題になっていた)。
ここで、わたしは奥の手を出す。トランプでいうと、ジョーカーを切る。
当時、なぜそんな秘密兵器をもっていたのか、まったく記憶にない。しかし、ジーンズのポケットには「たまたま」入っていた。19歳の大学生がもっているモノではない。子ども向けの玩具なのだ。
スーパーボールである。
現在でも「スーパーボールすくい」など、祭りの夜店で一般的であるらしい。ネットで検索すると、アメリカンフットボールの祭典「スーパーボウル」と並んでヒットする。この、弾力性の高いゴムのボールを、わたしはポケットから取り出し、握りしめた。
(これを、2階の彼女の部屋の窓に投げつけるのだ。音と衝撃で、きっと目をさまし、窓を開けるにちがいない。ふっふっふ)
乗ってきた自転車をブロック塀のそばで駐(と)める。降車し、玄関のアプローチへ歩を進める。もはや完全に不法侵入。砂利道である。周囲が静まり返っているせいか、ジャリ! ジャリ! と大きな音がする。なるべく忍び足で進んだ。
玄関には向かわず、家の脇にまわる。夏の草花や庭木が見える。それらを背後に、2階の彼女の部屋の真下に立つ。すると自然に、1階の窓が目の前になる。この窓の部屋で彼女のご両親、小学生の妹さんが寝ていることを、当時のわたしは知っていた。窓、壁1枚へだてて向こう側に、ご家族がいるのだ。き、緊張する。
背後は庭。その後ろに自動車のガレージ。その奥はブロック塀だ。わたしはちょっとロマンチックな気分にひたっていた。『ロミオとジュリエット』や恋愛ドラマ、青春映画で似たようなシーンがなかっただろうか。
深窓の令嬢が自室ですやすや休んでいる。すると、フランス窓にこつん、こつんと小石が当たる。交際を親に反対されている恋人が、夜中にこっそり忍んできたのだ。物音に気づき、目覚めた令嬢がベッドから起き出す。ピンクか白のネグリジェなどをお召しになっている。目をこすりながら窓に近寄り、両開きに開放する。「誰なの?」と小声でささやく。期待と不安にみちた声。すると「マーガレット、ぼくだよ」と、窓の下から「禁じられた恋人」が応答するのだ。
(このシチュエーションは、まさにそれではないか!)
と、ドキドキしながら妄想全開。
(しかし、どう考えてもあれはフィクション。窓に小石を投げたら、ガラスが傷つくはずだ。器物損壊。恋人に迷惑をかける。しかし、オレがもっているのはスーパーボール。これならば、窓ガラスにダメージを与えることはない。なんという天才的なひらめき! 映画も芝居も小説も、「禁じられた恋人男性」はみな、スーパーボールを持ち歩くべきだな)
そんなことを考えながら、反り返って大きく振りかぶった。右手のスーパーボールを彼女の部屋の窓に投げつける。
コン!
という音がし、ボールはみごとに命中。その後、「ヒュン!」と夏の夜空に高く、跳ね上がった。視界に一瞬、きれいに輝く星々がうつる。ぽかんと口を開け、ボールの軌跡を目で追う。高く上がった後、放物線を描くように背後のガレージに向けて落ちてきた。(あ、あれあれ……!)と思う間もなく、落下したボールはガレージとブロック塀の間で複雑な往復運動を派手に展開した。
ゴンギャン、グワンバン、バンバンバン、ギャンキーンドンドンバン!
(ま! まずい!)
あわてて砂利道を全力疾走。
ジャリジャリ!ジャリジャリ!ジャリ!
公道に出て、ブロック塀に回りこみ、しゃがんで家のようすをうかがった。「心臓が口から飛び出す」という表現を身をもって体験する。頭のなかは混乱、混線、混沌、大パニック。
(どどどどうしようどうしょう! 謝りに来たのにご家族、ご近所さんにご迷惑をかけてしまったどうするどうするどうしよう!?)
近隣の家々の窓に明かりがともり、ごそごそぶつぶつ話し声が聞こえる。誰かが「不審者侵入!」の通報を警察にする。彼女の家の居間の窓から電灯の明かりが洩れ、とうとう玄関のドアが開く。パジャマにガウン姿のお父さんが現れる。右手には金属バット。「隠れてもむだだ。出てこい!」と激怒の声。へなへなとこころが折れ、「すみませんすみません夜分にすみませんご迷惑をおかけしました悪いのはぼくですぼくなんです」と、ふらふら、よろよろと姿をさらす。ぺこぺこ、へこへこと頭を下げ、真っ青な顔で謝罪をくり返す。遠くでパトカーのサイレンが聞こえはじめる……
という事態はまったく起こらなかった。
周囲はシーンと静まり返ったまま。
どきん、どきんと破裂しそうだった心臓の鼓動がしだいに落ち着いていく。
わたしは逆にあきれ返った。
(あれだけの大きな音、大騒動が起こったというのに……なんてことだ! 誰もようすをうかがおうと起き出さないのか!)
せめて彼女だけは、目をさますべきではなかろうか。自分の部屋の窓にボールが命中したのだ。振動や衝撃はなかったのか? その後の「ガレージを楽器にしたライブ演奏」は眠りを破らないのか? おれの「魂の叫び」は伝わらないのか!? 決死の覚悟で恋人が深夜に訪れても、グースカと寝入ったまま。そんなに鈍感な女だったのか!
釈然としないものの、なにはともあれ、ひとだんらく。ひと安心だ。スーパーボールは大失敗だったが、この住宅街でその件を問題にするのは、自分ひとりだけなようだ。
(さて、どうしよう)
「飛び道具」はすでにない。石を窓に投げるのは、どう考えてもまずい。リアクションがなければないで、こちらも「次の一手」が思い浮かばない。メモ帳やペンがあれば、置き手紙を書ける。「夜中に会いにきたけど、ふたりっきりで会う機会をつくれなかった」などとメモし、玄関の郵便受けに入れておけばいい。だが、筆記道具、紙など持ち合わせていなかった。
ひらめいた。
(玄関前の道路に小石を並べ、文字を書くっていうのはどうかな? 「大森参上」とか)
即座に却下。まるで暴走族ではないか。それにまったくロマンチックではない。
(うーん。どうしよう。うーん……うーん……)
こまった。アイディアが浮かばない。
(ここまでか! 万事休す! 残念だが、ここで撤退か……!)
あきらめて帰ることも考えた。しかし、そうするとこうなる。「夜中に女の子の家に行き、部屋の窓にスーパーボールを投げつけて、ただ帰ってきた男」に自分はなってしまう。「大学生はバカだバカだ」と書いてきたが、これではさすがにバカすぎる。救いようがない。うーんうーん……どうすべきか……いったい、どうしたら……。
さて、前回「第16回『緑の扉』ふたたび」が抽象的な内容だったので、今回はその具体例を述べている。19歳のときの、この体験は自分にとって「個人的なザマニ」だ。ザマニは本来、共同体や一族の概念である。「特定集団の過去、現在、未来に意味や価値を与える共有された記憶、歴史、神話」「意味としての過去」「時間のことばで語られる永遠」だ。この「夏の夜の夢」のような体験は、その後のわたしの人生に影響を与えつづけた。つまり、「個人的な」ザマニといえる。「壁にぶつかった」り「袋小路に迷いこんだ」り「落とし穴におちこんだ」りしたとき、この「夏の夜」にどれだけ助けられたことか。おそらく、これからも支えになってくれるだろう。所用で「琴似栄町通り」や琴似の駅前通りを歩くと、当時の記憶がふっとよみがえる。
具体例として、よりふさわしく説明するために、当時、読んでいた本を紹介したかった。「緑の扉」の向こう側の異世界には「1冊の魔法の本」がある。当時、読んでいた本のページには「今は遠く過ぎ去った夏の夜の月光」が染みこんでいるはずだ(プルースト)。このころ、記憶では19世紀、20世紀前半の欧米翻訳小説を読んでいた。ヘルマン・ヘッセ、ヘミングウェイ、フィッツジェラルド、オスカー・ワイルド、スタンダール……。これらの本はみな、どこかに散逸してしまい、今は手もとにない。もっとも、それが本当に「魔法の本」なら、紹介するために読んでしまうと本が消えてしまうか、わたしが消滅してしまう。むしろ、「どこかに散逸し、手もとにない」方が、例としては的確なのかもしれない。
とはいえ、この「本の森散歩」は本をめぐるエッセイだ。「真夜中のランデブー」ものとして、次の本を紹介したい。フィリパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』(高杉一郎訳/岩波少年文庫/初出は1958年。翻訳初出は1975年)である。

表紙が「緑色」っぽいので、「緑の扉」にふさわしい。以下が内容だ。
弟のピーターが「はしか」になってしまった。感染症隔離のため、トム少年はおじさん夫婦の住む町へ。このご夫婦、子どもがいない。だから、トムが一緒に暮らすためにやってきたのは大歓迎である。だがその一方、子どもが何をたのしみにするか、どうやって接するのが適当かの、知識がない。おじさんもおばさんも子どもが好きで自分を歓迎してくれているのは、トムにも分かる。しかし、子どもが気に入りそうな遊び道具や本がない。それに同世代の「友だち」がいない。トムは退屈で退屈で……。
身体を動かすことがないので、運動不足だ。夜になっても眠れない。真夜中、2階の部屋のベッドでまんじりともせず不満をかかえこんでいる。やがて、下のホールの大時計が「13回」鐘を鳴らした。
「13時だって!?」トムは気になってしかたない。ベッドを抜け出し、1階のホールへ。すると、ふだんは鍵のかかっている「裏の物置」へのドアが開けられる状態に「変化」していた。好奇心からそのドアを開けると、外は「真昼の庭」だ。花壇にはヒヤシンス、ニオイアラセイトウ、エゾギク、ケシやバラの花が咲いている。イチイの木もある。さっそくトムは、大好きな木のぼりを実行する。
その日から彼は、真夜中にこっそり「裏庭」に出かけることになる。そこで園丁をはじめ、何人かの人間を見かけるが、奇妙なことに、相手にはトムが見えないらしい。唯一、トムが見え、話しかけてきたのはハティ(ハリエット)という少女だけだ。事情があって年長のいとこたちと一緒に、おばさんの家に住んでいる。しかし年齢差があり、彼女は遊びの仲間に入れてもらえない。トムはこの子としだいに仲よくなり、一緒に木のぼりしたり、レンガ塀によじのぼったり、秘密基地を作ったりする。出会えるのは、トムの時間では「真夜中」だけだ。しかし、秘密の「裏庭」に行くたびに、季節が変わっていることにトムは気づく。ハティも急速に成長し、だんだんトムの年齢を追いこし、「お姉さん」になっていくのだ。これはいったいどういうことか……。
時間にまつわる児童向け読みものの古典である。おそらくミヒャエル・エンデ『モモ』(1973)と双璧だろう。
気づくのは、トムもハティも「高いところ」にやたらと、のぼりたがる点だ。イチイの木、レンガ塀、最後は「イーリーの大聖堂」である。
p297「ふたりは町を見おろしていたが、イーリーはほんの小さな町だったので、すぐにもっと遠くの方へ目をうつした。川は町の片(かた)がわの近くを流れていた。ふたりは、その川にそって、下流の方へ目をやった。夕日のあたっているところだけキラキラとかがやいているまっ白な氷の道が、うねりくねりながら、遠くのもやと夕ぐれのなかに消えさっていた。リトルポート、デンヴァー、キングズ・リンの町々や海は、その方向にあった。それから、ふたりはうしろをふりかえって、じぶんたちがカースフォルドからやってきた氷の道を眺(なが)めた。気が遠くなるような遠い道のりだった。」
時間を表現するときは、「空間的な比喩」になる。トムとハティが高所から眺めているのは常に「時間」だ。しかも「川」は「時間」を強く連想させる。「下流」は未来、「上流」は過去だ。もっとも、この「川」は流れている部分が見えない。英国でも歴史的な寒気のため、氷結している。トムとハティはスケート靴で、凍結した「川」を滑ってイーリーの大聖堂にやってきた。
さらに踏みこもう。それらを一挙に把握できる眺望の認識とは、「永遠」を示唆しているのである。ふたりが「木のぼり」をくり返すのは、当時、ニンテンドーのゲーム機がなかったからではない。「時間のことばで語られる永遠」を分かち合うためである。トムとハティにとって、「真夜中のランデブー」は共有されたザマニなのだ。
よって、ラストシーンは……おっと、これは内緒。未読の方はぜひ、手に取って確認してください。それにしても「恋/愛」と時間(旅行)は文学的、物語的に非常に相性がよい。
自分自身の「ランデブー」に話を戻そう。
万策尽きたそのときだ。とんでもないことを考えついた。「人間、追いつめられと訳の分からない暴挙に出るもの」だ(第1回 緑の扉)。非常識きわまりないアイディアがひらめいた。
(待てよ……6月にいちど、ここに遊びに来たとき、彼女は「幼友だち(女の子)」を紹介してくれた。たしか……「徳永さん」(仮名)とかいったかな……。「幼友だち」ということは、幼稚園や小学校がいっしょ。それはつまり、学区がいっしょということだ。すなわち、徳永さんの家がこの近所にあることを推測させる……)
頭脳が高速回転する。
(探せば、「徳永家」が見つかるかもしれない。そして、運がよければ「徳永さん」に会えるかもしれない。彼女には会えなかったが、徳永さんには会えるかも……。もし会えたら、「自分が深夜、謝罪にここまで来た」ことを彼女に伝えてもらえるかもしれない……)
「かもしれない」ばかりである。しかし、「プランB」として有効に思えた。
ただこのとき、時刻は午前1時半。いかに「次善の策」とはいえ、1回しか会ったことのない女の子の自宅を訪問するのに、ふさわしい時間と思えない。ご家族みなさん、すやすやぐっすり眠っているに決まっている。もっとも「知らないひとの家」を勝手に訪問する件に関しては、わたしにはいろいろと実績があった(第1回参照。「スワン家の方へ」「ゲルマント家の方へ」ではなく、わたしの場合は「赤の他人の家の方へ」が個人的なザマニであるらしい)。それにともかく、このプランは机上の空論だ。徳永家が、ご近所さんかどうか、実際のところ分からない。
(だめでもともとだ!)
わたしは自転車にとびのった。夜の住宅街をスクロール。警察のパトロールに逢着したら、職務質問まちがいなし。その場合、事情や状況をうまく説明する自信はまったくなかった。「こいつ、不審なやつ」と警官はピンときて、わたしは派出所や西区警察署に連行されることになっただろう。
さいわい、パトカーに出会うことはなかった。そして、見つけてしまったのだ、「徳永」という表札の出ている一戸建て住宅を! さらに、居間の大きなガラス窓のカーテンの隙間から明かりが洩れている。つまり、家のひとが起きているのだ、こんな時間なのに!
自転車のブレーキを力いっぱい握った。上体前のめりで急停車。
(これは! 突撃訪問せよ、という啓示か? しかし、同姓異人である可能性もある。この「徳永家」に「徳永さん」は、ほんとうにいるのだろうか?)
いやいや。「佐藤」や「鈴木」とちがって、そうある名前ではない。40人クラスに0~1人だろう。ましてや、家のひとが寝ていないのなら……(ああ! 暴挙!)。
自転車を降り、スタンドを立てた。玄関のアプローチへ入っていく。き、緊張する。
ドア脇のチャイムを鳴らす。ピン、ポーン。
反応がない。もういちど、ボタンを押す。ピン。ポーン。
《……どちらさまですか?》
インターフォンから年配の女性の声。もしここが「徳永さん」のご自宅なら、彼女の母親だと思われる。
さあ、名のろう、と思って、脳内が空白だと気づいた。
(どう名のったらいいんだ? オレはいったい、誰だ!?)
「オーモリです」といっても通じない。「徳永さんの友人です」も不可。「友人」ではないし、そもそもこの家に「徳永さん」がいるかどうかも分からない。
「う、うう……えー……あー……こちらにいらっしゃると思われる……徳永さんの友人のマーガレット(仮名)の知り合いで……オーモリといいます。……徳永さん、いらっしゃいますか?」
もって回った自己紹介である。
《…………………ちょっと待ってください》
え? 「ちょっと待ってください」だって?
ここで正解なのか? 徳永さんのご自宅? 英語圏海外ドラマなら「ビンゴ」っていうところ?
茫然として立ちつくす。やがて家のなかからは、誰かが全力疾走しているような不穏な物音が聞こえてきた。ドタドタ! バタバタバタ! こ、これはいよいよ「金属バットをもったお父さん」が登場するのか?
ガチャ、とドアが開く。頭がにゅっと突き出される。「徳永さん」だった。よかったー。
「ハノンくん、どうしたの? こんな時間に」
不審そうな表情である。一面識しかない。当然だ。
「……いやー、マーガレットとけんかしちゃってさ。それで謝ろうと思って、ここまで来たんだけど、彼女の家に行っても、うまく会えなくて。それで、『自分が謝罪にここまで来た』っていうことだけでも、あとで伝えてもらおうと思って、徳永さんの家を探して、やって来たんだよね」
経緯の説明が複雑である。しかし徳永さんには、すぐに伝わったようだ。いちどうなずくと、にやりと笑った。
「マーガレット、いま、この家にいるよ」
な、なんだとー!?!?
この瞬間、さまざまな思考やイメージの断片が脳内を駆けめぐり、交錯した。なかでもいちばんショックだったのは、これだ。「オレがスーパーボールを投げつけた、あの部屋のなかには誰もいなかった! 無人ちゃん! オレは無人の、からっぽの部屋の窓にスーパーボールを投げつけた。誰もいなかったんだ……誰も……」という考え。バカバカ! 自分のバカバカバカ!
あまりの驚愕に茫然としていると、
「呼んでくるね」
と徳永さんの頭が引っこんだ。たぶん、このときのわたしの表情を何度か思い出し、彼女はニヤニヤ笑ったことだろう。
ぼんやり突っ立っていると、ふたたびドアが開く。マーガレットが出てきた。泣いている。
「ごめんね」とわたし。
「うん。でも、もういいんだ。ゆるす」
この後、彼女は徳永さんに「おやすみー」と別れのあいさつ。夜分にご家庭の平和を乱したことを謝罪し、わたしもご挨拶した。それから、ふたりで近所の公園に行き、いっしょにブランコに座った(ああ、青春!)。深夜2時ごろ。山の方の土地なので、街の灯りや空の星がとてもきれいだったのをおぼえている。だが夜景より、特に星だ。
昼間の太陽でさえ、その光が地球にとどくのに8分かかるそうだ。わたしたちが見ているのは「8分前の太陽」なのである。それが、100光年はなれた星なら、その光は100年前のもの。1万光年はなれた星の光なら、1万年前のものだ。つまり、夜空の星を見上げることは、「時間と空間が溶け合った永遠」を見つめることにほかならない。トムとハティのように、わたしたちも永遠を分かち合った。どんな話をしたのかは記憶にないが、彼女は「明日、訳本をもって大学に行く」と請け合ってくれた。めでたしめでたし。帰り道は迷いに迷い(ほっとして気が抜けた)、往路の2倍の時間がかかったが……。
それから数日。わたしにはひとつ、解けない疑問が残った。
(あの日、彼女はなぜ、徳永さんの家に行っていたんだろう? あんな夜遅くまで、ふたりは何をしていたんだろう?)
雑談中に偶然、8月31日深夜の話になった。
「あの日、徳永さんのお父さん、東京出張中でたまたま家にいなかったんだよ。ハノンくん、ラッキーだったね」
「そうだったんだ。よかったー。ところであの夜、あんな時間に徳永さんの家で何をしていたの?」
「あー。君と電話で話した後、あまりの怒りにむしゃくしゃして『このままでは眠れない』と思ってね、徳永さんのところに行って、《ハノンこき下ろし悪口大会》を開催していたの(ニコニコ)」
うおー! 聞くんじゃなかったー。(了)
【注】もちろん、当時の翻訳はまったく記憶にない。ただ、担当者各自、勝手な文体で訳していたので、そこだけ分かるように再現した。下敷きにしたのはマックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』大塚久雄訳/岩波文庫。
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon