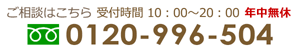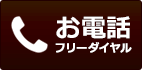「♪春よこいこい、春よこい」
そう祈りつづけたおかげか、ほんとうに春が来た! 例年より1ヶ月早い。まだ3月だが、気温は4月並みで推移している。連日のプラス気温に路上の雪は溶けた。根性なしの、へなちょこめ。ざまあみやがれ。貴様らの時代は終わった。今年もオレは「勝ったんだ! 犬神一族に勝ったんだ!」(意味不明)
乾いたアスファルトがむき出しになり、道幅が広がった。
北海道新幹線延伸にともなう札幌駅周辺の再開発で、毎年、わたしが利用していたレンタル自転車は廃業。しかたなく、自前で自転車を購入した。いまはそれを乗り回している。北海道民にとって「3月に自転車に乗る」ことは、人類の月面着陸に匹敵する快挙だ。
祈りの力はすごい。この調子で、「原稿が話題になりますように」と祈りつづければ、ほんとうに本が売れ、原稿料や印税がバカスカ入るのではなかろうか? そうしたら、「赤道直下の南の島」を買い取って、冬はそこを避寒地としたい。
午前10時くらいに、のらくらと起き出し、菓子パンと牛乳で朝食を済ませる。仕事の原稿――「南の島の楽園エッセイ」をタッタカタッタカ、キイボードで気楽に打ちこむ。出版社にファイルデータをズバッと送信。1日の仕事は終了だ。昼はサンドイッチと珈琲。自転車に乗って、島を3周し、景色を楽しむ。帰宅してシャワーを浴び、本を読みながら、ちょっと午睡。夕方に、むくっと起きて、カッターシャツにバミューダショーツ(最近はバミューダパンツというのか?)、サンダル履きで島に1軒しかないカラオケバーへ。海に沈む夕日を見ながら友人、知人、飲み友だちとビールで乾杯する。座が盛り上がってきたら、昭和歌謡曲や往年のアニソン、アイドルソングをみんなで熱唱。知らない曲でも1番を聴いたら2番からハモれる。他人のマイクを奪い合って、みんなで歌う。
「明日はパパイヤの収穫しないと。ハノンも一緒に手伝ってくれない?」
「いいね! 仕事は午前で終わるから、13時にウチに来て」
「じゃあ、また明日!」
帰宅して就寝。1日が終わる……。毎日がこんなふうに過ぎていくのだ。さよなら冬物コート。さよならマフラー。さようなら、湯たんぽ。
だが、春めいてきたとはいえ、油断は禁物。2013年3月2日、爆弾低気圧が北海道に上陸し、深刻な猛吹雪、ホワイトアウト、遭難事故が発生した。自宅まであと200メートル、という地点で発見された父と娘。父親は娘をかばうようにして倒れ、凍死した(娘は無事)。周囲が完全に白一色になり、方向感覚を喪失したのだろう。暴風だけで雪がなければ、避けられた遭難だった。車に閉じこめられ身動きができず、母親と子ども3人が亡くなった、いたましい事故も。周辺は2~4メートルの雪が積もっていたそうだ。雪がマフラーをふさぎ、一酸化炭素が車内に逆流し、中毒死した。
佐々木譲『暴雪圏』(2009)は、3月末の道東が舞台だ。猛吹雪で国道が通行止めになるなか、強盗殺人事件が発生する。孤立した町は凶悪犯人と一緒に、吹雪のなかに閉じこめられる。事件発生を警察は感知しているが、自然の猛威のせいで捜査活動が不可能だ。空間限定のサスペンスが盛り上がる。3月になり、「もうすぐ春だ」というタイミングで、「冬」が突然、断末魔の猛威を振るうことがある。ホラー映画で「ラスボスの悪霊を退治した」と思ったら逆襲をくらうかんじ。先日も、(雪のない)暴風が札幌圏を襲い、東区の高校の立ち木が倒れた。巻き添えになった女子高生が転倒。幸い軽症だったそうだが、油断大敵なのだ。

さて、前回の宿題からまず、かたづけたい。時間ループもののテキストをあれこれ考察していた。それで、西澤保彦『七回死んだ男』(1995)に触れる予定だったのだ。
『七回』の舞台は高知県、安槻(あつき)市。西澤作品では、おなじみの架空の街である。高知=「南国」土佐なので、時間ループの季節は「夏」かと思えば、そうではない(日本の時間ループものの話題作のループシーズンは「夏」が多い、という指摘は前回の「第15回 時間ループと春」をご参照ください)。正月なのだ。この時期は「迎春」「新春」「初春」である。前回の話の流れでは、映画『恋はデジャ・ブ』(1993)、ディケンズ『クリスマス・キャロル』(1843)同様、「冬を終えて春を迎える」伝統行事を連想させる時間ループになる。
『七回』では、37店舗を全国展開しているレストランチェーンのグループ会長、渕上零治郎(ふちがみれいじろう)の遺産相続にまつわる事件が描かれる。遺産目当ての一族メンバーが参集する一般的な機会とは、年末年始のあいさつ訪問となるだろう。一家の祖父母の家に子や孫が集まり、ごちそうを食べ、除夜の鐘を聞き、翌日、子どもたちはお年玉をちょうだいする。このタイミングなら、容疑者を一堂に会した遺産をねらった事件を自然に設定できるわけだ。
主人公で語り手は、零治郎の孫の大庭久太郎(おおばひさたろう)。16歳の高校1年生だ。生まれながらにして、特殊な体質をもっている。彼はそれを「反復落とし穴」と呼ぶ。夜中の12時から次の夜の12時まで、24時間の1日を9回、反復してしまうのだ。自分でコントロールは不能。多いときは1ヶ月に数十回、少ないときは2カ月に1回程度、体験するという。2~8週目は何をやっても元に戻るから、試行錯誤の期間だ。最終9週目が決定版になる。2~8週でためした、自分にとってのベストバージョンを9週目に実現し、最終決定にする。そうすると、周囲からは「非常に優秀で気の利いたやつ」に見える。中学生時代、彼はこの体質を利用し、異性の気を引いたり、テストで高得点を取ったりしたが、しだいにむなしくなった。「何だか何やっても虚しいんだよなー」とは、無限に触れた人間のニヒリズムである。先日、鑑賞した映画『エヴリシング・エヴリウェア・オール・アト・ワンス』(2022/日本公開は2023)でも同じ問題が扱われた。気が向いたら次回以降で採り上げたい。
久太郎少年は達観してしまった。ループのせいで、同世代の他の16歳より多くの時間を過ごしている。「精神年齢三十歳以上」といっても、あながち間違いではない。時間を「稼いで」しまったのだ。
「時は金なり」。久太郎の特異体質は、祖父零治郎の奇妙で幸運な蓄財とパラレルな設定になっている。82歳の零治郎がエッジアップ・レストラン・チェーン・グループを築いたきっかけは、賭博だ。市郊外で小さな洋食店を営んでいただけだったが、経営は赤字つづき。零治郎は大のギャンブル好きなのだ。店の売り上げをギャンブルにつぎ込んでしまう。借金で苦労した妻は脳溢血で急死。3人娘のうち2人は親を見限ってさっさと家を離れた。残ったひとりは将来を絶望し、ノイローゼ(今風にいうと「うつ」か)に。
行き詰った零治郎は店を売り、ノイローゼの娘と夜逃げした。最後に贅沢なひとときを共有し、海に身投げするつもりだ。ただ、ちょっと残った金で馬券を買った。残金を使い切りたかったので、勝つつもりはなかった。めちゃくちゃな大穴狙いの連続。ところが、これが当たってしまう。何十倍にもなって戻ってきた。
腹立ちまぎれに株を買った。上がりそうもない株ばかり、あえて選んで逆張りを貫く。しかしこれもまた、急騰し、大金が転がりこむ。借金を返済し、娘と一緒に無国籍風洋風料理の店を開くことに。この店がまた当たる。連日の大繁盛。チェーン店展開をはじめると、これも流行し、あっという間に店の数が増えていった……。金を「稼いで」しまったのだ。
この孫と祖父が、ある種の共犯関係となるのは必然である。しかし、ネタバレになる。多くは語るまい。
親族、チェーン店の経営にかかわる関係者には、金に困っている者もいる。零治郎は毎年、新年に遺言を書き換えていたが、「今年が最終決定。もう変更しない」という(この点も、孫と祖父は似ている)。一見、元気そうだが、大好物の酒のせいで最近、いちど昏倒しているらしい。お膳立ては十分だ。
そしてとうとう事件は起こる。屋根裏部屋で酒を飲んでいた零治郎が、後頭部を殴打され、殺害された状況で見つかる。凶器は現場に転がっていた花瓶らしい。早々に容疑者に当たりをつけた久太郎。折から始まった時間ループを利用し、祖父の命を救い、「殺人事件」を回避しようとこころみる。だが、彼の悪戦苦闘にもかかわらず、毎回毎回、事件は起こる。無限化した欲望を限定されたループで抑えつけ、無化することは可能なのか。久太郎の試行錯誤はつづく……。
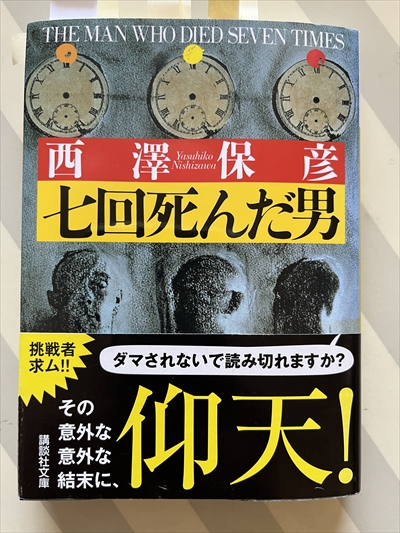
『七回死んだ男』を最初に読んだのは、講談社ノベルスだった。1990年代末である。その後、文庫が出て読み直し、今回、この文章を書くために読み直し……。いったい、何回読み直すのだろう? 七回? 七回読んだ男?
結末は明らかにしない。しかし、これだけは書いておこう。この物語、比喩的な意味だが最後にちゃんと「春」がくるのだ。それに関係者の循環する欲望は、直線の時間に延長される。きわめて読後感がよろしい。
前回のディケンズ『クリスマス・キャロル』についてもひとこと、補足したい。『キャロル』の結末は次のように考えられているだろう。独善的な欲望に支配されたスクルージが改心し、クリスマスの博愛精神を学び、自分の欲望を制限、断念する、と。
だが改心したスクルージは無限の欲望を断念したわけではない。円環上の無限の欲望を、直線化したのだ。その結果、欲望はさらに深化し、将来化し、延長された。目先の浅い欲ではなく、遠い時間の先を見こした遠大な欲望として無限化されたのだ。3番目の幽霊が見せた「未来のクリスマス」のビジョン――自分の孤独な死――を避けようと彼は願った。幸福や延命を望むのは、自然な欲望である。その結果、彼は改心し、生き方をあらためた。つまり、目先の欲望よりもっと大きな欲望に気づいたのだ。『七回死んだ男』にも、そういう側面がある。『クリスマス・キャロル』の系譜につらなる「春」を迎える〈円環⇒直線〉の物語といえるのだ。「私利私欲を捨て、博愛主義を」ではなく「深く大きな私利私欲のために、博愛主義を」である。
さて前回、「近年、時間ループものは少し落ち着いた印象」と述べたが、これを忘れていた。潮谷験(しおたにけん)『時空犯(じくうはん)』(講談社/2021)だ。
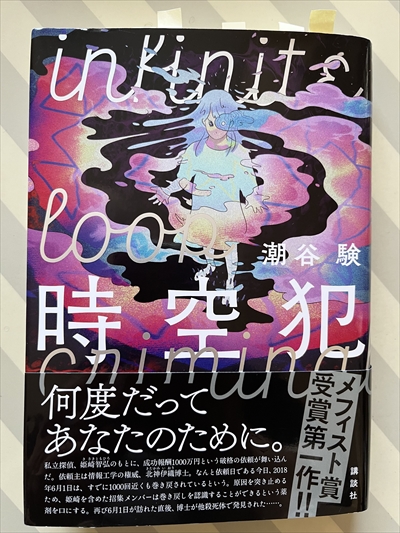
京都に探偵事務所をかまえる姫崎智弘(きさきともひろ)は突然、送られてきたメールにおどろき、困惑する。「成功報酬一千万円。応諾を問わず、準備金四十万円支給」。ネットバンクを確認すると、40万円はすでに入金されていた。送り主は情報工学の天才、北神伊織(きたかみいおり)。60歳代なかばの女性研究者だ。
仕事を引き受けることを決意し、説明会におもむいた姫崎。そこには、京都府警警視、元経産省事務次官、ITセキュリティホールのピックアップを専門とする天才高校生、芸能事務所の関西営業所所長、京都市南区観光業者協会会長のおばちゃん、姫崎と過去にワケありの芸能タレント大学院生らが集まっていた。一見、ばらばらな取り合わせのメンバーの前で、雇用主の北神博士はとんでもないことをいい出す。
「自分の本来の研究は時間遡行です。時間ループは自然現象で、多くのひとはそのことに気づいていません。しかし、ある事情から、わたしにはその現象を知覚できます。通常、ループは18~28時間くらい、巻き戻る回数は1~5回。ところが本日、2018年6月1日は978回、反復されているのです」
978日というと、約3年だ。
「これは明らかに人為的な現象です」と博士はいう。そして集めたメンバーに「時間ループを知覚できる液体」を摂取してもらい、自分同様、ループを知覚可能になるよう求める。さらに「誰が、なぜ、巻き戻しを執拗(しつよう)におこなっているのか」謎を突き止めてほしい、と依頼する。
メンバー全員、あまりの話に半信半疑だ。しかし、「時は金なり」。1千万円にほとんど全員が誘われ、みな依頼を引き受ける。永遠の時間の檻に閉じこめられるリスクは、無限の金銭欲と等価なのだ。
ペットボトルで支給された「液体」は無色無味無臭。水と変わらない。後遺症のリスクはないという。リセットは深夜午前1時20分に起こり、約20時間前の早朝午前5時35分にさかのぼる。
その晩、自室で旧知の芸能タレントと電話で話し合っていた姫崎は、実際に時間遡行を体験し、驚愕する。そして「遡行メンバー」である京都府警の警視から「北神伊織博士が殺害された」と知らされるのだ。これは、時間遡行を人為的におこなっている人物=時空犯が、「遡行メンバー」のなかにいるということか? いったい、それは誰なのか? 時間ループが発生する(つまり、殺しても生き返る)というのに、北神博士はなぜ殺されたのか? 時間ループを特殊設定として利用した謎解きミステリ、また先の予想を裏切りつづける軽快痛快なサスペンスとしても、うまく書けている。
潮谷験は21年に『スイッチ 悪意の実験』で第63回メフィスト賞を受賞してデビュー。『時空犯』は長編2作目。「リアルサウンド認定2021年度国内ミステリーベスト10」の第1位に選ばれた。その後も順調に新作を刊行しつづけている、新進気鋭の書き手だ。
「時間ループ」が発生し、それを自覚しているとき、その人物は時間の外側にいる。「時間の外側」とはなんともバカバカしい表現だ。「時間の外側」に出ることなどできない。ひとは空間を知覚するセンサーを持っている。しかし、時間を知覚するセンサーがない。その結果、時間の流れは主観に依存することになる。客観的に時間を把握するためには、その流れを「空間化」するしかない。太陽の動き、月の満ち欠け、針が動く時計、カレンダー……。したがって、「時間の外側に出る」というのも、時間を空間化したひとつの比喩だ。
「音楽は時間の芸術だ」という紋切型がある。これは不正確だが、いまは不問に付す。ここに1冊の楽譜がある。モーツァルトのピアノソナタ第12番。楽譜を読め、旋律を理解する人物にとって、その1冊は「時間の流れ」である。ピアノで演奏したら、「楽曲=時間」を再現できる。これは1枚のLPレコード、CD、あるいは「配信データのタイトル」でもかまわない。映画のDVDソフトでもよい。それらを目の前にしているとき、ひとは「時間の外側」にいるのだ。音楽や映画にかぎらない。そのように「凍結された時間の流れ」とは1冊の本でもありうる。
もし、人生の節目節目で、ひとつのシークエンスが終わりを迎えたとき、それがひとつの物語として1冊の本にまとめられたら、わたしたちは「時間の外側」にいる。その本はくり返し、反復して読むことが可能だろう。かけがえのない宝石のような過去の時間を、くり返し味わうことができるはずだ。ところが、そうはならない。「時間の外側に出る」ことは、実際にはありえなからである。それをテーマにしたのが「第1回 緑の扉」で採り上げたH・G・ウェルズの短編「塀についたドア」だった。以下で内容に触れる。
塀についた緑のドアを開けると、そこは異世界。主人公はそこで1冊の本を見つける。その本には「自分の人生」が書かれていた。夢中になって読みふける。そして読み終えた途端に、ドアのなかの異世界は消滅する。……そして最後には主人公自身も消えてしまうのではないか――そんな結末を暗示する物語である。

「緑のドア」の異世界とは、個人的なザマニにまつわる記憶であり、その記憶が書きこまれている1冊の本である。
ザマニは一般に、「個人」において語られる概念ではない。それは「一族」や「共同体」における「神話の時間」である。前回、参考書に利用した真木悠介『時間の比較社会学』(1981)で、わたしはこのことばを知った。ケニア出身でアメリカ、イギリスに留学し、ケンブリッジ大学で博士号を得たキリスト教の牧師、ジョン・S・ムビティの『アフリカの宗教と哲学』で述べられた概念だ。真木の『時間の』から孫引きする。
p32「ザマニは時間の墓場であり、終末であり、万物がおのおの休止する場所を見出す領域である。それはすべての現象や出来事の貯蔵倉であり、以前でも以後でもない現実のなかに万物を溶解する時間の大洋なのである。」
(真木悠介『時間の比較社会学』2003年/岩波現代文庫)
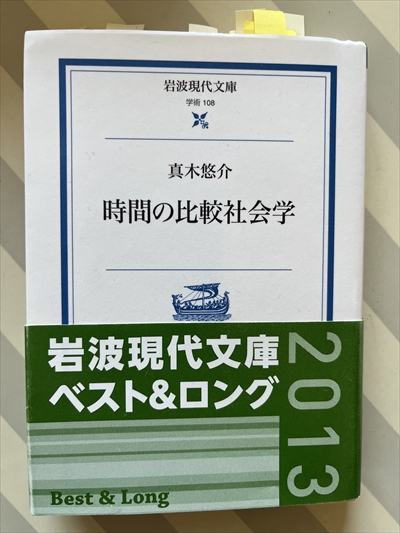
現在、そして未来という時間に根拠と意味を与えるのが「過去の神話=ザマニ」だ。「意味としての過去」であり、「時間のことばで語られる永遠」である。古代人の思考では、これは「時間の範型」で、くり返されるものだ。「うつりゆく」「かりそめな」「一回性」の不規則な変化を古代人は重視しない。反復可能――つまり無時間的な出来事こそ、いつまでもそこにありつづけ、現在や未来の根拠となる「時間や歴史のふるさと」と認識する。時間を空間化する比喩をもちいれば、「いつも遠くに見える故郷の山並み」のように、古代人はザマニを意識しているのだ。これは日本の民俗学でおなじみの「常世(とこよ)」を連想させる。「現世(うつしよ)」はかりそめで、無常であり、刹那的で価値が低い。一方「常世」は死者やこれから生まれる者たちの魂が集まる、永遠の異界で、本質的に価値がある。
近代以降、このザマニを「個人化」し、文学作品として書き残したものがプルースト『失われた時を求めて』(1913-1927)だと真木は述べる。反復し変化しない現象より、「かけがえのない」「一回性」の出来事をわたしたちは大切にする。そこに生の尊厳を求める。時間は直線で意識され、過去⇒現在⇒未来の一方向に変遷していく。反復はしない。
そのような認識下では、「時間の外」に出ることはできない。そんな状況で1冊の本をくり返し読んでも、それは反復を意味しない。初読、再読、三回目、四回目の経験はつねに変わっている。「時間ループ」を意識したフィクションの登場人物は、実はいつも「一回性」の循環を体験しているのだ。それぞれのループを「別のループ」と認識する。では、そんな場合、ザマニである「1冊の魔法の本」を読めば、どうなるか? その本は「二度と読めなくなる=消滅する」しかない。あるいは、読んでいる自分が消えてしまうしかない。
読書は、意識的には「本のなかの」時間体験だが、無意識的には「本のそとの」時間体験なのだ。「本のそと」では、この「一回性」の貴重な体験が、知らず知らずにページの1枚1枚、活字の1語1語に、染みとおっている。プルーストは次のように述べる。
p96「……その思い出が祝福であり続けているはずの、幼年時代の魅力的な読書体験は、これを別扱いしなければならなかった。この種の読書体験について最初に述べたことを、私はおそらくこれまで書き連ねてきた論述の長さと性格によって、証明しすぎたほどなのであろう。つまり私たちのなかに残っているのは、とりわけそれらの書物を読んだ場所や日々のイメージだということである。」
(「読書について」岩崎力訳/保刈瑞穂編『プルースト評論選 Ⅱ芸術篇』ちくま文庫/2002)

『失われた時を求めて』は90年代、図書館の本を借りて読んだので、いまは手元にない。上述の内容を『失われた』でより洗練された、気の利いた表現で次のようにプルーストは書き換えた。当時の読書ノートから引用する。訳は井上究一郎だ。
日々の生活によって提供される心象は、実際のところ、その瞬間に、多種多様の感覚をわれわれにもたらすものである。たとえば、以前に読んだ書物の表紙を目にすると、その表題の文字のうちには、今は遠くへ過ぎ去った夏の夜の月光が織りこまれているのである。
「今は遠くへ過ぎ去った夏の夜の月光」とは、その本を読んだときの「本のそとの」無意識的時間体験だ。となれば、1冊1冊の本の表紙こそが、個人的なザマニ=「緑の扉」への潜在的な資格をそなえていることになる。
p111「読書が私たちにとってそそのかしであり続け、魔法の鍵が、私たち自身の奥底の、自力では入り込めなかった住まいへの扉を開けてくれるかぎり、私たちの生のなかで読書の果たす役割は有益である。」
(「読書について」岩崎力訳/保刈瑞穂編『プルースト評論選 Ⅱ芸術篇』)
プルーストはこの魔法を、本だけでなく「ヴァントゥイユのソナタ」や「エルスチールの絵」、「マルタンヴィルの鐘塔」に求めていく。しかしウェルズ同様、「1冊の魔法の本」にこだわった物語としてガルシア=マルケス『百年の孤独』(1967)を指摘したい。
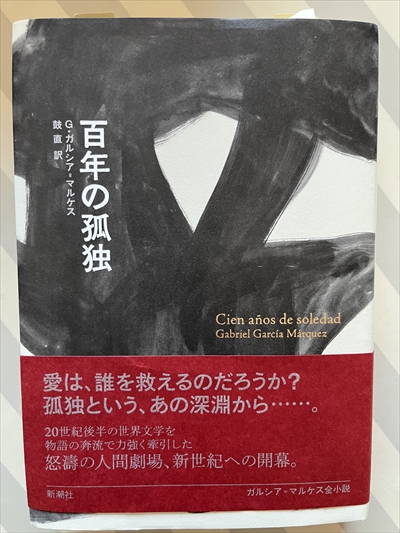
『百年の孤独』も、このエッセイで軽く言及している。すでに「第4回 一族の歴史」で触れたように、南米某国(コロンビアといわれる)、マコンドという架空の町におけるブエンディア一族の神話的歴史を扱ったテキストだ。「塀についたドア」や『失われた時』が個人のザマニを焦点化したのに対し、『百年』のポイントは一族のザマニである。
20世紀の古典的傑作であり、マジックリアリズムという手法は世界中の作家に影響を与えた。多くの研究、言及がなされている。よって、これからわたしが述べることもたいして目新しいものではないかもしれない。指摘したいのは次の2点。
(1)『百年の孤独』の中核には「時間ループ」がある。
(2)「メルキアデスの羊皮紙」はザマニが描かれた1冊の本である。その本は読み解かれることで、「円環⇒直線」の時間構造の変化をもたらし、テキスト内世界を消滅させる。
『百年』が円環構造をもっていることは、多くのひとびとが指摘しているだろう。物語のそもそものはじまりは、ホセ・アルカディオ・ブエンディアと「いとこ」のウルスラとの親族結婚である。この一族の者のなかには、親族結婚の結果、「豚のしっぽ」を生やした子どもが生まれたことがあった。それを恐れたウルスラは結婚後も、性的交渉をアルカディオに拒否。その件をからかってきた男をアルカディオは殺してしまう。ふたりは故郷にいられなくなり、落ち着いた先がマコンドだった。
その後、ふたりはアルカディオ(父親と同名)とアウレリャノというふたりの息子を生む。この名前はその後も子孫たちに受け継がれていく。そして、アルカディオ=破天荒で陽気、めちゃくちゃなバイタリティを発揮する系譜と、アウレリャノ=暗い目を伏せて沈思黙考し、不思議な能力をうちに秘めている系譜を反復することになる。女性たちも同じような名前をつけられ、レメディオス、小町娘レメディオス、レナータ・レメディオスと紛らわしい。現代日本の芸能人に引き寄せれば、森本レオ―家入レオ、薬師丸ひろ子―やくしまるえつこ、いしだあゆみ―石田亜佑美(モーニング娘。23)と、わたしの世代には紛らわしいこと、このうえない。わざとやっているなら、やめていただきたい。
夫のアルカディオの死後も数世代の一族の浮沈を見つづける、100歳をこえるウルスラはこういう。「時間がひと回りして、始めに戻ったような気がするよ」と。ウルスラのこの感慨はくり返される。作者は意図的に、円環構造を強調しているのだ。そもそも「豚のしっぽ」の形が円環である。みずからの尻尾を飲みこむウロボロスの図像と同じように、『百年』全体のシンボルになっているのが「豚のしっぽ」=円環なのだ。
マコンドのブエンディア一族の館の「精神生活の中心」が、ふだん「開かずの部屋」になっている「メルキアデスの部屋」だ。メルキアデスは、初代アルカディオの錬金術趣味に影響を与えた魔法使い的人物である。一族の過去、現在、未来を暗号で書き記した羊皮紙を彼は残す。この「メルキアデスの羊皮紙」こそ、作中で「緑の扉」「一族のザマニ」となる「1冊の魔法の本」なのだ。したがって暗号が解読され、内容を読み解く人物が登場したとたん、その人物はマコンドと一緒に消滅する運命にある。「羊皮紙」の題辞はこうだ。
p470〈この一族の最初の者は樹(き)につながれ、最後の者は蟻のむさぼるところとなる〉
(G・ガルシア=マルケス『百年の孤独』鼓直訳/2006年/新潮社)
一族の始原と終末を宣言することで、「一回性」の直線の時間が導入されるのだ。「百年の孤独を運命づけられた家系は二度と地上に出現する機会を持ちえないため、羊皮紙に記されている事柄のいっさいは、過去と未来を問わず、反復の可能性のないことが予想された」と、「緑の扉」が永遠に閉ざされたことが宣言される。
この「メルキアデスの部屋」(「おまるの部屋」と呼ばれることも)で、時間ループ現象が起こっている。初代アルカディオは晩年になると、もうろくしたのか、言動があやしくなる。もっとも、「土を爆食いする女」「町中の住民が記憶を失う伝染性の不眠症」「シーツをまとって青空に昇天し、消えていく美女(羽衣伝説か!?)」「実は王国の王女と王子の、グアヒロ族の使用人姉弟」「予知能力のある反乱軍大佐」など、奇妙で魔術的、神話的、伝説的出来事が頻発するため、「老耄(ろうもう)による言動のあやしさ」など読者は看過してしまうだろう。だが注意深く読めば、そこに時間ループを見つけられる。初代アルカディオはこういうのだ。
p99「大へんなことになったぞ。空を見ろ。太陽の照りつける音に耳をすませてみろ。昨日と、その前の日と、少しも変っちゃいない。今日もやっぱり月曜日なんだ。」
仕事場(メルキアデスの部屋)で永久機関を利用した玩具を工作している初代アルカディオは、「毎日が月曜日だ」と狂ったように混乱して、わめき出す。その結果、庭の栗の木に縛りつけられることになる。しかし、テキストはのちに、この現象が客観的に存在していることを明らかに示すのだ。
p400「ふたりはまた、そこはつねに三月であり、月曜日であることを知った。そしてそれによってホセ・アルカディオ・ブエンディアは家族の者たちが言うほど狂ってはおらず、時間もまた事故で何かに当たって砕け、部屋のなかに永遠に破片を残していくことがあるという、この真実を見抜くだけの正気をそなえた、ただ一人の人間であることを悟った。」
「メルキアデスの部屋」では同じ月曜日がループしているのだ。「豚のしっぽ」=円環構造のテキストの中核に、時間ループが埋めこまれているわけである。「時間のことばで語られる永遠=ザマニ」が解読を待つ暗号として、その部屋に保管されているからだろう。
最後に、『百年の孤独』の比較対照サンプルとして、トーマス・マン『ブデンブローク家の人々』(1901)に言及したい。
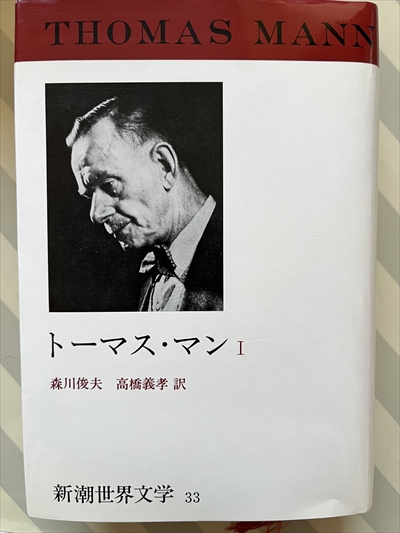
岩波文庫版などでは「ブッデンブローク家」だが、わたしが読んだテキストでは「ブデンブローク家」だったので、後者で統一する。訳者は森川俊夫。
マジックリアリズムの始祖『百年』はファンタジー、幻想文学とジャンル的に親和性が高い。そのため、SFファンタジー風のウェルズ「塀についたドア」の「魔法の1冊」が登場しても違和感がない。対して、『ブデンブローク』はゴリゴリのリアリズム小説だ。好対照の2冊に思えるが、「一族の歴史=ザマニ」に当たる「1冊の本」は『ブデンブローク』にも登場する。ただし「読み終えた途端に世界が消滅」するわけでは、さすがにない。
北ドイツの自由都市リューベックを舞台にした、ブデンブローク家4代の栄光と滅亡を描いた物語である。作中時間は1835年から1877年の約40年。この一族の歴史を年代記風に書き記した「大きな帳面」が作中に存在する。
一族3代目の令嬢であるトーニ(アントーニエ)は、心根はやさしいが気位が高い、美しい娘である。避暑地で知り合った医学生と彼女は恋に落ちる。しかし、伝統や格式を重んじる一族が、一介の医者の卵との結婚をゆるすはずがない。トーニは家族のため、自らの恋心を封殺し、意にそわぬ(どころか生理的嫌悪感さえある)相手との結婚を承諾する。一族の一員であることに誇りをもつ彼女は、父親の机で「大きな帳面」を見つけ、家族の歴史に思いをはせる。気分が高揚し、誇らしさや敬意、畏怖、偉大さをかんじ、真剣に読みすすめる。
p127「『鎖の一環のように』ってパパは書いていたわ……そうなのね! この鎖の一環になればこそ、わたしは高い、責任ある意義をもっているのね、――行為と決断とによってこの一族の歴史に協力する使命を与えられているんだわ!」
(トーマス・マン『ブデンブローク家の人々』森川俊夫訳/新潮世界文学33/1971年/新潮社)
こうした高揚感に浮かされ、彼女は系譜の自分の名前のあとに、「一八四五年九月二十日ハンブルク商人ベンディクス・グリューリヒ氏と婚約せり」と、新しく書きこむのだ。もちろん、この結婚は残念な結末を迎える。だが、これこそがザマニだ。過去、現在、未来に意味、価値を与える共同体の記憶、歴史である。
一方で「大きな帳面」が、作中人物によって内容をどんどん書き加えられている。このような性格は「緑の扉」の「魔法の1冊」には、まったくふさわしくない。ザマニである「本」と、作中人物の時間の流れは異なっている。「本」、あるいは人物は、それぞれ「時間の外側」にいなければならないのだ。しかし、トーニと「大きな帳面」は同じ時間の流れの「なか」にいる。
ところが、4代目のハノー(ヨーハン)になると事情がちがってくる。ハノーはトーニの甥に当たる、一族の最後の少年だ。生まれたときから病弱で、音楽に鋭い感性をもっているが、夜驚症(やきょうしょう)に悩まされている。いつもおどおどしており、学業にも不熱心で身が入らない。その彼が「大きな帳面」を書物机で見つける。
ハノーの心境はトーニと対照的だ。無関心、批判、軽蔑。そして、自分が誕生した記述のあとに、奇妙な「書き加え」をおこなう。定規とペンで二重の横線を引くのだ。まるで、このあとの書き加えはなく、この一族の系譜はここで「おしまい」と宣言するように。この「いたずら」(?)は、市参事会員でもある父親のすぐに知るところとなる。
p412「食後、市参事会員はハノーを呼び寄せ、眉をしかめてどやしつけた。
『これは何だ。どうしてこんなことになったのだ。やったのはお前か?』
ハノーは一瞬、やったのが自分かどうか、考えてみないとわからなかった。そしておずおずとびくつきながら『そうです』と言った。
『これはどういうことだ! お前はどうかしたのか! 答えなさい! 何でこんなけしからんことをやるんだ!』市参事会員は、帳面を軽く丸めて、それでハノーの頬を叩きながら、そう叫んだ。
すると小さいヨーハンは、あとずさりながら、片手を頬にあてがって、吃(ども)りながら言った、『ぼくは……ぼくは……もうおしまいだと思ったものだから……』」
ハノーの予感は的中する。この後、市参事会員の父親は急死し、チフスが16歳のハノー本人の命を奪う。とはいえ、このシーン、父親の意向にいつもびくびく従うハノー少年にしては、あまりに大胆な「いたずら」だ。一族の家系図にも当たる「大きな帳面」に、断絶や亀裂を入れるような不敬で不吉なサインを、ふつう書きこむものだろうか。これは作者の都合だろう。「もうおしまいだ」と思ったのは、ハノーではなく、トーマス・マンである。作者に操られているから、「一族の時間の外側」にいる、あるいはそのことを予感できる。ハノーは、はっきりした自覚もない。ただ「なんとなく」一族の系譜の末端に大きな長い横線を引く。それ以降の流れを断ち切るのだ。
「大きな帳面」はこのあと、テキスト内で出番がない。ブデンブローク一族は急坂を転がるように、解体し、滅んでいく。とはいえ魔法のように、幻想的に消滅するわけではない。作中人物は作中時間の「なか」にとどまる。「そと」にいるのは作者だけ。「なか」のハノーを通して、「大きな帳面」を部分的な「緑の扉の1冊」として利用したのだ。
さて、今日の札幌は気温が14度まで上昇。市内は積雪がゼロになった。冒頭で触れたとおり、3月には異例なことだ。とはいえ、4月に突然、猛吹雪になることもある。ひきつづき、気を抜かずに過ごしていきたい。「緑の扉」になりそうな本を探しながら……。(了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
Twitter:https://twitter.com/OmoriHanon