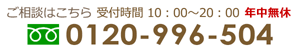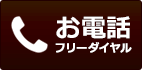みなさんは、カラスと闘ったことがあるだろうか?
わたしは、ある。
まず、カラスの弱点は何か? ほんのささやかな偶然がきっかけで、わたしはそれを知ることになった。
もう20年くらい前だろうか。札幌市の某歓楽街で飲み明かし、さんざんカラオケで歌った。さすがに家に帰ろうと店を出る。午前6時ごろだった。夏だったので、日は完全にのぼっている。周囲は明るい。雑居ビルのそばの電線にカラスが1羽、とまっていた。
「お。カラスだ」
と、酔っ払ったわたしは、その1羽をじっと見つめた。
……じっと……。
そうして、10分くらい経っただろうか(酔っ払っています)。カラスが挙動不審になったのだ。明らかに動揺している。電線の上を右に左に移動する。弱々しく「カア」「クウ」と鳴く。首を左右に振る。落ち着きを失っている。
(お。このまま見つめたら、どうなるのかな?)
歓楽街とはいえ、ススキノのような巨大な商業区域ではない。地元の住民が飲みに行く場所で、観光客とは無縁である。だから通行人など、ほとんどいない。この時のわたしは明らかに「頭のおかしなひと」だったのだが、誰にも見とがめられなかった。
頭を上にむけ、口を半開きにし、じっとカラスを見つめる。
カラスは混乱しているようだ。
(え? なんで? なんでボクにそんなに注目しているんですか? ボク、何かしましたか? ていうか、あなた、誰なんですか? え? え?)
あちこちに視線を飛ばす。仲間を探しているのだろうか? しかし、近くに他のカラスはいなかった。電線の上を小刻みに行ったり来たり。こっちを見返してくることもあるが、(ヤバいひとらしいから、視線を合わせない方がいい)と思っているようだ。「なに見てんだ、オラ。やんのか、コラ」といったかんじはない。
そうして20分をこえたあたり、カラスは悲しげに「クウウ」と鳴き、電線から飛び降りた。地面をすれすれ飛行し、どこかに飛び去った。それは「参りました。降参です」とか「勘弁してください。これ以上はもう耐えられません」という降伏や帰順のふるまいだった。
こうした体験を通し、次のように考えたのだ。「ひょっとしたら、カラスは人間のまなざしに弱いのではなかろうか」
これは仮説だ。仮説は実験によって証明せねばなるまい。
そこで、その後も何回か、機会を見つけてはカラスを見つめてみた。もう、酔っ払っていない。行きつけのスーパーの玄関前などで実験したので、買い物客は不審げにわたしを見た(真理を究明する、崇高な科学的実験なのだ。気にしない)。
カラスは、明らかにダメージを受けていた。やはり10分程度で挙動不審になり、20~30分、じっと見つめていると、降参したように電線を飛び降りる。
(しかし、これは野生動物の虐待ではないか)
と、わたしも気づいた。実験は2~3回。それでもう仮説は証明されたと独り決めし、以後、カラスに無駄なプレッシャーをかけるのをやめた。
そのころから「カラスがひとを襲うらしい」という噂は耳にしていた。札幌市のカラスは円山(北海道神宮や動物園がある)に、大きな「ねぐら」があり、早朝の残飯を目当てにススキノに「朝ごはん」を食べに行くそうだ。人間を「エサの提供者」とみなすようになり、次のような計画的犯行(?)を実施するという。
コンビニで弁当を買ったお姉さんが店の外に出てくる。1羽が近くの電線の上から、そのお姉さんに「カア!」と鋭く鳴きかける。驚いたお姉さんが弁当を取り落す。待機していたもう1羽がさっと飛び出す。くちばしで弁当の袋の持ち手をくわえ、飛び去っていく。
真偽不明の都市伝説である。しかし、実際に襲撃されたひとはいるらしい。
15年くらい前の1月だったと記憶する。
市内中心部にある中島公園の南端に、コンサートホール「キタラ」がある。このホールの音響は世界的に有名らしい。海外の音楽家、交響楽団、歌劇団など、「キタラ」での演奏を楽しみにしているという。
わたしもちょくちょく、音楽鑑賞に利用している。その時も、何かのコンサートのために「キタラ」に向かっていた。市営地下鉄中島公園駅で降りて、公園の端から端まで雪道を移動する。その途中、樹木の枝に数羽のカラスがたむろしていた。
わたしの少し前を歩いていたご婦人(60歳くらい。わたし自身は当時、40歳代だったと思う)は、あきらかに恐怖し、動揺していた。いきなり方向転換し、わたしの方にやってくる。
「ごめんなさい。わたし、カラスが怖いの。一緒に行ってくれる?」
「あー。いいすっよ」
気安く引き受けると、ご婦人はわたしと腕を組んだ。ぴったりと身を寄せてくる。カラスの集団の脇を一緒に通過したが、首をすくめ、緊張している。カラスはくちばしや爪でひとの頭部を急襲するらしいので、ふたりともコートのフードをかぶった。
中島公園にも、けっこうカラスがいる。実は、この公園、ススキノのすぐ南にあるのだ。ここのカラスも歓楽街で「朝ごはん」を食べているのだろう。したがって、ひとつの難所をこえても、次から次へとカラスの群れがあらわれる。わたしたちは、いっしょに雪道を警戒しながら歩いた。
「迷惑かけて、ごめんなさいね。このあいだ、わたし、カラスに襲われて怖い思いをしたの。だから、すっかり苦手になっちゃって」
「問題ないです。最近、カラスは凶暴らしいですねえ」
などと話しながら、雪道を踏みしめる。ご婦人が安心し、わたしをリリースしたのは、「キタラ」の玄関口だった。
こうした体験から、実際の被害者がいるらしいと、わたしは実感したのである。
しかしこのときは、自分自身も被害者になるとは思わなかった。
コロナ禍の「夜の街」規制が実施されていたころである。2021年か22年か。規制のせいで、ススキノから出る早朝の残飯の量がめっきり減った。深刻な食糧危機に陥り、カラスの数は激減したらしい。そのことが凶暴化に拍車をかけたのだろうか? 「おい。おれたちの『朝メシ』をちゃんと用意しろよ! なにをさぼってやがる!」と、カラスも憤っていたのだろうか?
8月の中旬くらい。夜中に突然、目が覚めた。時計を確認すると午前3時半である。しばらく二度寝に挑戦したが、妙に眼がさえて眠れない。かつてもこの季節、早朝に目が覚めてしまったことがある。そういうとき、どうしたか……?
豊平川河川敷にサイクリングにいくのである!
夜明けの直前の空や雲がいかに美しいか!
生まれたての太陽を見ながら自転車をこぐのが、いかに爽快か!
というわけで、わたしは布団からむくむくと起き出し、さっと洗顔する。Tシャツを着て、短パンを履き、キャップをかぶり、サイクリング用のグラブを装着した。汗みどろで帰ってから、シャワーを浴びるのだ。帰宅時には、近所のパン屋がすでに開店しているから、サンドイッチを買って帰る。シャワーを浴びた後、アイスコーヒーを淹れ、サンドイッチを食べながら朝刊を読むのだ。完璧。
まだ暗い、夜明け前の街へ、自転車を漕ぎ出した。
豊平川にたどり着くまで、カラスが妙にさわいでいるな、とは思った。しかし、「うんと遠くで暴走族が騒いでいる」程度にしか関心を持たなかった。ともかく、一刻も早く河川敷でのサイクリングを求めて、こころはうずうずしていた。
豊平川は札幌の街の中心部の南東の端をかすめるように、南から北東に流れている。札幌という街自体、この川が氾濫した扇状地にできている。そのため、起伏が少ない。ほとんど平地である。自転車に乗るためにできたような街なのだ。
わたしはいつも、ススキノの南東のはずれから豊平川河川敷に進入していた。この日も、そのルートである。
さて、いよいよ河川敷というタイミングで、頭に何かが当たった。
(ん?)
と思っていると、周囲で「バサバサ」と翼の羽ばたき。
(お! カラスだ。おれはカラスのアタックを受けたのだ!)
「カアカア!」「ガアガア!」と威嚇の鳴き声も聞こえる。2羽のカラスが、わたしの頭の周辺でホバリングしながらアタックを繰り返していた。さいわいキャップをかぶっていたから、頭皮が破れたり出血したりすることはなかった。
意外にわたしは冷静である。カラスなんかより、サイクリングへの興味や関心がまさっていた。「繁華街で因縁つけてきた若い奴らがいるが、無視無視。はやくカラオケ歌わなくちゃ」みたいな勢いで、急襲をやりすごす。河川敷に入ると、カラスたちは追って来なくなった。
しかし、その日の天候はくもり。思ったような美しい景色を見ることは、かなわなかった。がっかりである。
1時間くらいのサイクリングを終え、しょんぼりススキノへの接点の出入り口にたどり着く。すると先ほどの2羽が、ふたたび襲ってきた。明らかに、わたしの顔を覚えている。「おれたちの縄張りに進入しやがって。無傷で帰れると思うな!」ということなのか、ともかくしつこく襲ってくる。具体的な地名をいうと、南6条から大通りまで。札幌に土地カンのある方なら理解できるだろう。6街区に渡って、まとわりついてきたのだ。
温厚なわたしにも限界はある。あまりに、しつこい。また期待外れのサイクリングのフラストレーションもあった。
(カラスどもめ! きさまらの弱点はお見通しだ。返り討ちにしてくれる!)
大通り東1丁目の街区が決闘場所だ。わたしは自転車を急ブレーキで止めた。驚いたカラスたちが「ガアガア」いって、頭の上から飛び去る。
(ふっふっふっふ。選んだ相手が悪かったな。おれはそこらへんにいる普通の人間じゃない。おまえたちの弱みをつかんでいるのだ。怒りの「まなざしビーム」をくらうがよい。はっはっはっは!)
さて、最近は毎回、こういう日常エピソードと選んだ本をマッチングさせて紹介している。しかしこれが、なかなか難しい。エピソードと本の内容がうまく噛み合わないのだ。
たとえば、前々回の第26回「飛光よ! 飛光よ!」で歯の「かぶせもの」のエピソードを紹介した。しかし、歯なのだから、これは前回第27回「オモチャの21世紀」で紹介した本岡類『聖乳歯の迷宮』と噛み合わせるべきだった(歯だけに)と後悔しきりである。
今回、紹介する本はサラ・ヤーウッド・ラヴェット『カラス殺人事件』(法村里絵訳/角川文庫/2023年11月)。このタイトルを目にし、「あ。カラスなら、あのエピソードがあるじゃん! 今度こそ、ぴったりのマリアージュだ」と狂喜した。

で、さっそく読んでみたのだが、なんと、カラスがぜんぜん出てこない。
タイトルに「カラス」とあるのに、カラスが出てこない!
既読の方はご存じだろう。被害者の名前がソフィ・クロウズ。クロウズ=CROWSということで、タイトルの「カラス(CROWS)」は人名なのだ。いやいや、それにしても。英国の田園地帯のマナーハウス周辺が舞台なのだ。カラスがいないはずはない。モリムシクイは出てくる。ゴジュウカラも出る。クロウタドリも出てくる。キツツキも。マガモ。カワセミ。白鳥。グレーウサギコウモリも。
しかし、カラスだけは1羽も出てこない!
いないのか? 英国にカラスはいないのか!?
そんなに珍しい鳥なのか!?
もちろん、英国の他の小説にはふつうにバンバン出てくる。カラスがいないはずはないのだ。タイトルに「カラス」を使ってしまったから、作者がわざと作中にカラスを登場させるのを避けているのにちがいない。なぜ、そんなことをするのか? なにか、ひねったユーモアなのだろうか?
こういう趣向の小説を、わたしは他にも知っている。
ドン・ウィンズロウ『犬の力』(東江一紀訳/角川文庫/2009)だ。
このテキストにも、イヌが出てこなかった。麻薬取締官や麻薬組織が登場し、たしか水族館をかねたダンスクラブで銃撃戦が起こる。水槽のガラスに銃弾が当たり、タコとかクラゲとかさまざまな海の生きものが出てくる。それ以外にもいろいろな陸の動物も登場する(記憶で書いています)。しかし、イヌだけは出てこないのだ!
「タイトルに使った生きものは作中に登場させない」という隠れたルールがあるのか? いやいや、そんなバカな。最近、話題になったディーリア・オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』(友廣純訳/早川書房/2021)では、ふつうにザリガニが登場した記憶がある。よって、変化球の好きな一部の作家の個性なのだろう。まったく勘弁してくれ。もう、しようがないので、このままカラス抜きのテキストを紹介する。とほほほ。
『カラス殺人事件』のあらすじは以下の通り。
8月末日、英国の片田舎の〈マナー・ハウス・ファーム〉で、若い女性が殺害される。被害者は、その家屋敷や近隣の土地の所有者であるソフィ・クロウズだ。死因はレンガによる撲殺。犯行現場は館の敷地内の地下トンネルだった。
周辺の土地には再開発の計画があった。開発に先立って、土地の生態系を調査し、行政に報告する必要がある。そこで〈エコロジカル・コンサルタンツ〉に所属する生態学者、ネル・ワード博士が〈マナー・ハウス・ファーム〉に派遣されていた。地下トンネルはコウモリの居住空間として最適だ。そのため、ちょうど殺害時間周辺に博士は事件の現場に居合わせてしまう。
事情聴取で博士の家を訪問した刑事たちは仰天する。ひとり暮らしには似つかわしくない、豪勢な邸宅にネルは住んでいるのだ。室内の調度も高級品ばかり。「生態学者って、こんなに儲かるのか?」と刑事は驚愕する。また、質問に対するネルの応答も、やや歯切れが悪い。「この女性は何か隠している」という印象を刑事たちは持つ。
そう。たしかにネルには秘密があるのだ。
ネルの本名は、早い段階で読者に明かされる。レディ・エレノア・ワード=ビューモント。「レディ」なので、貴族の令嬢だと分かる。だがネルはその素性を、職場はもとより世間にも隠している。にしても、その秘密主義はあまりに徹底しているのだ。不信感を強めた警察は、彼女を容疑者とし、捜査をすすめる……。
謎解きミステリとしての興趣は、はっきりいって薄味である。犯人はそう意外ではない。犯行トリックも「え。今どきそれ?」といったもの。警察の見込み捜査も、度が過ぎている。したがって、この物語の読みどころは次のふたつだ。
まず、ラブロマンス。
職場の同僚、生態学博士のハンサムさん、アダム・カシャップをネルは気になっている。アダムの方でもネルに関心を寄せているようで、ふたりは冗談を言いながら仕事をしたり、素人探偵をしたり。また、ネルを捜査対象として尋問する刑事、ジェームズ・クラークもハンサムさんだ。重要参考人のネルに一目ぼれし、捜査に私情を持ちこむ葛藤に悩む。気の多い(?)ネルも、ジェームズにこころを許しているところがある。こんなふうに「なんとなく三角関係」の恋愛のゆくたて、女ごころのゆらぎ、などを楽しんで読むことが可能だろう。
もうひとつは、ネルの正体についての謎だ。解説の大矢博子も「読者は腑に落ちるだろう。そうか、著者はこれがやりたかったのか、と」とコメントしているが、本書の最大の読みどころだと思う。物語の中盤で明かされるネルの秘密。これがテキストの第2段階ロケット点火となる。動物生態学が、人間生態学になるのだ。それは「いちど失敗し、挫折した人間がどうやって警戒心をやしない、思慮深くなり、精神的に成長するのか」の経過報告のように読める。正体をあらわしたネルは状況を掌握し、限界を突破する活動力を見せ、物語を強力に牽引する。文庫本1冊2000円(税抜)という価格に「うへえ」と声を洩らしたが、ここまで読んで「十分に元は取った」と思った。
襲撃する鳥と人間との闘い――を描いたテキストとしては、なんといってもダフネ・デュ・モーリア『鳥』(務台夏子訳/創元推理文庫/2000)である。カラスも出てくるし。最初からこの本を紹介すればよかった。古典中の古典だ。


サスペンスの巨匠、映画監督のヒッチコックが映像化したから、短編「鳥」より先に映画『鳥』を観た方も多いだろう。デュ・モーリアの長編小説『レベッカ』もヒッチコックによって映画化され、作者はサスペンス作家として名高い印象がある。
しかし、短編集『鳥』で彼女の多様な作品群に触れれば、「サスペンス作家」はデュ・モーリアの一面にすぎないと分かる。幻想、怪奇、謎解き、ロマンス、黙示録的破滅と作風は多彩だ。そして、どの作品も驚くほど技巧的で、完成度が高い。古代の信仰を題材に聖なるものの顕現と消滅を、男女のロマンスにからめて描いた「モンテ・ヴェリタ」は特に印象深い。
「鳥」は動物パニックものの、かなり初期の作例に思う。先に地上波テレビでヒッチコックの映画に触れていたので、原作を読んで驚いた。内容がまったく違う。理由もなく、鳥の大群が人間を襲うというアイディアのみが共通している。登場人物も作品舞台も別ものだ。
浜辺の農場で働く農夫の一家が、鳥の襲撃からいかにして生きのびるか。短編「鳥」は、そのワンアイディアで話をぐいぐい押していく。父親は理論的な思考ができ、先見の明がある。理由は不明ながらも、鳥が人間を襲いはじめることに、いちはやく気づく。家の窓を板で補強し、燃料や食料を確保して、籠城をこころみる。
一方、ふだんと違う鳥の異常行動に気づいても、他の住民たちは事態を甘く見て楽観的だ。銃でかんたんに追い払えると考えている。
鳥たちの一斉蜂起がはじまる。主人公農夫には妻と、ふたりの子どもがいる。両親は子どもがパニックにならないよう、夫は妻が怖い思いをしないよう、さまざまな配慮や気づかいを見せる。家族は団結して、この難局に当たる。しかし、ロンドンは音信不通になり、ラジオも沈黙する。このように、地方の住民の動静を物語の核に据え、世界の破滅を情報メディアで間接的に表現するスタイルについても、この作品は初期の作例ではあるまいか。ゾンビ映画などでおなじみの様相なのだ。
特に感心したのは、鳥と人間の格闘シーンがほとんど描写されない点である。
映画では、こここそ見どころだろう。丁寧に表現せざるを得ない。役者は何度も何度も、鳥の大群に襲われ、腕や頭から血を流す。だが一方、鳥の襲撃を受けて「わーわー」「きゃーきゃー」と叫び、ひたすら両腕を振り回しているだけにも見える。襲ってくる鳥を素手でつかまえ、羽を折ったり、首をひねったり。そんな映像は出てこない(合成撮影だから)。また、そんな演出では劇場公開が難しいように思う。しかし実際に襲われたら、人間はそうやって反撃するのではなかろうか。したがって、かつて再見、再々見したヒッチコックの『鳥』は、その格闘シーンがどうも滑稽で非現実的に見えてくるのだ。
それに対して、短編「鳥」では格闘シーンがほとんどない。派手で、扇情的な読みどころになりそうだが、きわめて抑制的なのだ。むしろ、襲われて血まみれになって倒れた死体、その周辺に無数に散らばっている小鳥たち、といった描写が読者の想像を刺激する。籠城した主人公一家の建物は無数のコツコツ、ドンドンといった音と衝撃に囲まれ、遠くで戦闘機が墜落する轟音が響いてくる。要するに、直接的に襲撃や争いを描かず、視覚や聴覚に婉曲的に働きかける表現を作者は選んだ。そして見事に効果を上げているのだ【註】。
さて、わたし自身のカラスとの対決に話を戻そう。
自転車を歩道の脇に止めた。カラスは「ギャアギャア」鳴きながら、近くの電線に止まった。わたしは両腕を脇にぶらりと垂らし、2羽のカラスを見上げる。じっと見つめる。ただ、ながめるだけだ。ひたすら目を向ける。
カラスたちは逆上する。さかんにわめき、鳴き散らす。周囲のビル群に、鳴き声が反響する。電線の上を右に左に移動する。プラスチック製らしい黒い小箱が電線に装着されている。それをくちばしでガンガン突きまくる。箱の表面が削れ、プラスチックの砕片が飛び散る。下のアスファルトに、ぼろぼろ落ちる。そうとうムカついているらしい。おそらく、こんなふうに対峙(たいじ)する人間にはじめて出会ったのだろう。
(ふっふっふっふ。怒ってる怒ってる。今日は仕事が休みだから、いつまでもつき合ってやるぜ。今はまだ時間帯が早い。交通量もないし歩行者も少ない。しかし、ここは札幌の中心地だ。そのうち、出勤してきたひとたちがこの道を通る。車の量も増える。おまえたちの状況は不利になる一方だぞ!)
こっちは余裕である。「まなざしビーム」で挑発をつづけるだけだ。
飛びかかって頭上からわたしを急襲することはなかった。カラスたちも理解しているのだ。こっちには両手がある。後頭部から不意を衝くならともかく、しっかり目視されている状態で襲いかかっても、両手でかんたんに捕まえられる。そうしたら翼を折られる。地面に叩きつけられる。首を持ってぶんぶん振り回される(そんなことはしませんが)。だから、わたしが立ち去るのを待っている。視線が外れるのを待っているのだ。そうしたら、安心して急降下攻撃できる。
1時間以上、経過した。時間が経てば経つほど、状況はわたしに有利になっていく。歩行者も交通量も増えてきた。スーツ姿のお兄さんは、わたしと電線の上のカラスを見て、首をかしげて通り過ぎる。完全に不審者である。しかし、まったくかまわない。カラスも、敵対する相手はわたしひとり。他の人間には目もくれない。こっちが微動だにせず、悠々と構えているので、苛立ちを募らせ、激昂している。
午前7時半くらいになった。カラスたちは、さすがに負けを認めた。威勢よく「カアカア」叫んでいたが、ずうっと東の方にある高層マンションの屋上をめがけて電線から飛び立った。こっちの勝ちだ。
(けっ。ケンカするときは相手をちゃんと見きわめろ。お互いに時間の無駄じゃねえか)と無駄に勝ち誇り、自転車に乗って、わたしは帰路についた。サンドイッチとアイスコーヒーの朝食に、頭はすでに占領されていた。
たぶん、あのカラスたちにとってわたしは「酸っぱい葡萄」になっているだろう。(了)
【註】
この文章を書くにあたり、久しぶりにヒッチコックの映画『鳥』を鑑賞した。鳥の襲撃シーンはすべてが合成撮影ではない。カットによっては、ほんものの鳥を使っていた。役者の演技の苦労は想像にあまりある。
また、原作で効果を上げていた「襲われて血まみれになって倒れた死体、その周辺に無数に散らばっている小鳥たち」、「籠城した主人公一家の建物は無数のコツコツ、ドンドンといった音と衝撃に囲まれ」るといった描写はヒッチコックも流用していた。特に後者はクライマックスに利用され、恐怖やサスペンスを盛り上げる。しかし、映像的なショックでは、やはり直接、鳥に襲撃され、格闘するシーンに及ばないのだろう。文章で効果的な想像力を刺激する描写は、映像で直接的に表現されるシーンに負けるようだ。したがって映画を鑑賞して数年たつと、前者のシーンを忘れてしまうわけである。とはいえ以上は、わたし個人の体験による、狭い範囲の意見にすぎない。
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon