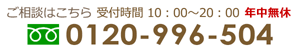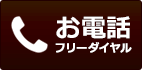「戦争映画が観たいなー」と脈絡もなく、唐突に思った。近所のレンタルショップまで雪道を歩くこと30分。スティーヴン・スピルバーグの『戦火の馬』(2011)、『プライベート・ライアン』(1998)のDVDを借りた。以下で内容に触れる。未鑑賞の方はご注意を。
『馬』は劇場公開時に鑑賞している。今回は2回目だ。『ライアン』も映画館で観て、ノルマンディー上陸作戦の描写に度肝を抜かれた。今回は3回目の観賞(たぶん)。何回観ても細かいところは忘れるし、話の内容もあいまいになる(ううう)。『馬』が第1次世界大戦のストーリーなのは記憶していたが、戦場に送りこまれるまで農村で農耕馬として働くシーンが結構長くつづくことを失念していた。ベネディクト・カンバーバッチ(今やドクター・ストレインジ)やトム・ヒドルストン(今やロキ)が英国の将校として出演していたなど、まったく記憶にない。馬がフランスの農場に逃げこむエピソードも覚えていなかった。
記憶に残っていたのは、塹壕(ざんごう)と鉄条網の西部戦線を怒り狂った馬が駆け回るシーンである。痛々しくて、強烈に印象に残っていた。
『ライアン』は、第2次世界大戦が舞台。優秀な士官で、現実的な対策を臨機応変に思いつくミラー大尉(トム・ハンクス)の前職を当てようと、部隊の面々が賭けをしているエピソードは忘れていた。しかし、冒頭と結末が現代(98年)のノルマンディー米軍英霊墓地のシーンだったことは記憶通り。子どもたち、孫たち――家族と一緒にライアンが墓参におもむく。太陽光を浴びて、すっかり色あせて見える星条旗が風になびいている。ライアンはミラー大尉の墓をじっと見つめる。画面は「大尉の墓」と「ライアンの顔」を何度も切り返す。そして、「色あせた星条旗」も。
彼は戦場で大尉やその部下たちから生命を救われた。ミラー大尉は「命を大切にしろよ」「おれたちの犠牲を無駄にするな」といったことばをライアンにかける(不正確かもしれません)。そこでライアンは妻に問うのだ。「自分の人生は、彼らの犠牲に価しただろうか」と。画面は「大尉の墓」と「色あせた星条旗」をくり返し映しつづける。
スピルバーグの映画は、このように「真実の口」演出をくり出すことがある。
「真実の口」とは、映画『ローマの休日』(ウィリアム・ワイラー監督/1953)の1エピソードだ。ローマ市内の観光名所でもある。

『休日』では、新聞記者ジョー・ブラッドレイ(グレゴリー・ペック)とアーニャ/アン王女(オードリー・ヘップバーン)のだまし合い、その罪悪感を観客に印象づけるため効果を上げている。いや、それ以外の効果も。
ネットで調べると、サンタ・マリア・イン・コスメディン教会に飾られているらしい。海神オーケアノス(あるいはトリートーン)の「顔」だという。郵便ポストのように開いた、その口の部分に手を入れる。すると、ウソをついている者の手は口から抜けなくなったり、手首から噛み切られたりするという伝説がある。
「ためしてみたら?」と、まずはジョーがアーニャに手を差し入れるようすすめる。挑発に乗って、震える手を差し込もうとするが、彼女は王女である自分の正体をジョーに隠している。つまりウソをついているわけだ。そこで急に臆病になり、「あなたが最初にやってみて」とジョーに切り返す。
ジョーはアーニャが王女であることを知っている。賭博好きで借金まみれの彼は、行方不明の王女のスキャンダル記事を書いて大金を得ようと考えた。だから彼女の正体に気づいていることは隠している。内心はよこしまな動機で彼女のローマ観光につき合っているのだ。ふたりとも相手を互いに欺いている。そして、観客はそのことを知っている。
ジョーは、ためらいつつも手を口に挿入する。そして……(ネタバレになるので、ここまでとします)。
このエピソードのラスト、画面は「真実の口」をしばらく映しつづける。ジョーとアーニャはすでにいなくなっているが、観客は無表情の「顔」を見せられるのだ。すると、その「顔」が何かを問いかけているような、観客に思考を促しているような気分になってくる。最初にこのシーンを観たとき、とても不気味で、奇妙な心理状態におちいったことをおぼえている。無生物が生命を得て、語りかけてくるような……。「不気味の谷」を超えたというべきか……。
その後、テレビ放映された『刑事コロンボ』「構想の死角」(スティーヴン・スピルバーグ監督/1971)というエピソードで、まったく同じ演出を体験することになる。この作品、日本初放送は1972年らしいので、わたしが鑑賞したのは、再放送か再々放送だろう。
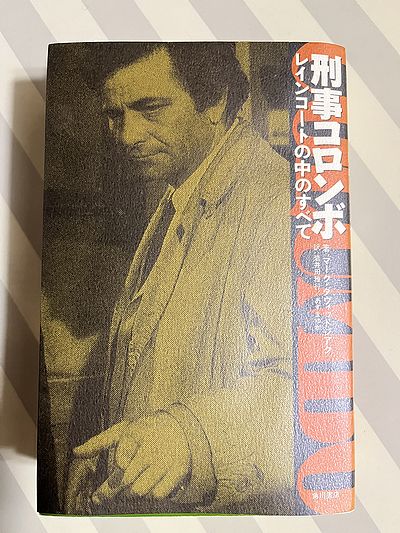
エラリー・クイーンや岡嶋二人、レビンソンとリンクのように、二人組のミステリ作家がおり、ベストセラーを乱発している。『ミセス・メルヴィル』シリーズが有名だ。「ミセス・メルヴィル」とは、ふたりが創造した名探偵である。映像化もされているのか、オフィスには彼女のポートレイトが額装され、飾られていた。
二人組の片方は熱心にタイプライターを叩き、執筆に余念がない。しかし、もう片方は印税で飲み歩き、遊び回り、まったく仕事をしていないようだ。そこで熱心な方が、相棒にコンビ解消を提案するのだ。そんなことされたら贅沢な暮らしができなくなる、と殺人計画を考案する。
事件が起こり、トリックが使われ、コロンボが殺害方法を暴く。ラストシーンは「ミセル・メルヴィル」のポートレイトだ。この中年のご婦人の「顔」が、視聴者をしばらく見返すのである。何かを問いかけ、語りかけるように。不気味な印象におそわれ、観客は何らかの思考を促される。この演出、効果は「真実の口」とまったく同じものだ。
はじめて視聴したときはもちろん、監督がスピルバーグとは知らなかった。テレビ映画『激突!』(1971)の前の仕事だ。当時は、才能のある「若造」「青二才」といった扱いだったらしい。よって、この演出がスピルバーグのオリジナルか、脚本のスティーヴン・ボチコ(80年代の『ヒル・ストリート・ブルース』でエミー賞総なめ)のアイディアか、わたしには判断できない。当初の編集ラッシュから削られたフィルムは、たった20フィート(6メートルほど)だったという。つまり、スピルバーグの頭のなかには完成した「絵」が、放映時間とほぼ完全に一致して存在していたらしいが(以上、マーク・ダウィットジアク『刑事コロンボ レインコートの中のすべて』岩井田雅行・あずまゆか訳/角川書店/1999 を参照しました)。
その後のスピルバーグ作品を観ていると、こういう「真実の口」演出に逢着する。たとえば『ミュンヘン』(2005)ではラストシーンに世界貿易センター(WTC)ビルが映る。この映画はイスラエル、パレスチナ双方から批判のあった問題作だ。当時、この映画を鑑賞し、すでに存在しなくなったWTCビルを見て、わたしは感慨にふけった。もちろん、これは「顔」だ。どんな景色を見ても、ひとはそこに「表情」を見出す。目や鼻がある「顔」である必要はない。よって、「色あせた星条旗」や「ミラー大尉の墓」、「WTCビル」も「真実の口」同様の効果を発揮する。ただし、見方を知らないと「顔」には見えないかもしれない。「やけに長いな、このシーン。もう見飽きちゃったよ」というわけだ。
最近作の『フェイブルマンズ』(2022)は、スピルバーグの自伝に即した内容だという。以下でややくわしく内容に触れるので、未鑑賞の方はご注意を。
家族で出かけたキャンプのフィルムを編集した主人公のサミーは、それまで漫然としか見ていなかった日常生活の秘密に突然、気がつく。カメラはただ客観的な、ありのままのようすしか映していない。だが、客体のベールの向こうから、「風景」が主体を見返し、思考を促すのだ。「これはいったいどういう意味だ?」「この光景は何を意味しているんだ?」「いったいどういうことが起こっているんだ?」 風景が内奥の秘密を露呈し、突然、語りかけ、思考を促してくる。そして彼は、見過ごしていた家族の秘密に思いいたる。これは意図されたものではないから、「真実の口」演出とはいえない。だが、その効果は同じものだ。
同じことがローガン・ホールにも起こる。しかし、チャド・トーマスには起こらない。
ふたりとも、サミーが通う高校のいじめっ子だ。「ユダヤ人嫌い」を公言し、何かというとサミーを攻撃する。
フィルムの撮影が趣味だということが知られ、サミーは高校卒業パーティ(いわゆる「プロム」。アメリカ青春映画でおなじみ)の記録映画を撮ることを依頼される。「おサボリ日」といわれるビーチへの遠足行事の映像だ。
ローガンもチャドも、パーティ参加者もみな、この記録映画を観る。作品は好評で、パーティは盛り上がり、サミーはみなから才能を絶賛される。しかしローガンは自分の映像に衝撃を受け、激しく傷つく。サミーを難詰する。
「お前、わざとあんなふうに撮ったろう! おれに対する復讐か!?」
金髪で肉体美を誇るローガンは非常に格好よく撮影されていた。映画を鑑賞した出席者は彼をほめそやし、もてはやす。ただし、ローガンはそんなふうに単純には観なかったのだ。自分があんなに格好よく、理想的な人間であるとは、思っていない。しかし映像上の彼、光の幻想のなかの彼は、まさに自分の理想(あるいは、それ以上)である。その差異が彼を混乱させ、苦しめ悩ませ、怒らせた。しかし、サミーはただこう切り返す。
「フィルムは、ありのままの姿を映すだけだ」
風景が突然、ローガンに語りかけ、彼はその声を聴いたのである。
一方、チャドの方は愚劣で貧相な自分の姿が映像化されていた。彼は単純に腹を立て、サミーを殴ろうとし、ローガンにさえぎられる。チャドは単に「いじめの仕返しをされた」と考えただけで、「声」は聴こえてこなかった。映像は彼に語りかけなかったのだ。映像の意味を深め、思考を促されることはなかった。
「ありのままの映像」が、見る者に「意味」を語りかける。それは、はっきり言語化できない「表情」であることもある。だが、その映像がわたしたちに思考を促し、考えることに駆り立てる。こうした演出効果は、きわめて映像的だ。よって、映画やテレビ、動画などの表現に特有のものと思うかもしれない。だが、かならずしもそうではない。『更級日記』の冒頭に、わたしは「真実の口」効果を見つけ、仰天した。
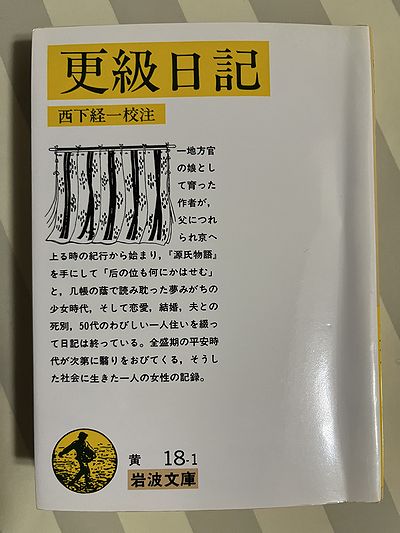
「あづま路(ぢ)の道のはてよりも、なほ奥つかたに生(お)ひいでたる人、いかばかりかはあやしかりけむを……」という冒頭は有名だ。受領である父親の仕事のため上総国(千葉県)で生まれ育った作者は、京の都に「物語」があると知り、「なんとかして読んでみたい」と願う。それで等身大の薬師仏をつくり、床に額をつけ、「京に行かせてください」「物語を読ませてください」と必死に祈る。
その願いが通じたのか、13歳のとき、上京が決定する。旅の準備のため大騒ぎになる。このエピソードは「門出(かどで)」というタイトルで高校の教科書に掲載されることもある。ご存じの方も多いだろう。
では、あれほど熱心に拝み、祈った薬師仏はどうなるか? なんと、上総国に捨てていくのだ。
p8「年ごろあそびなれつるところを、あらはにこぼち散らして、たちさわぎて、日の入りぎはの、いとすごくきりわたりたるに、車に乗るとて、うち見やりたれば、人まにまゐりつゝ額(ぬか)をつきし薬師仏のたち給へるを、見すてたてまつる悲しくて、人しれずうち泣かれぬ。」
『更級日記』西下経一校注(岩波文庫/2000年 第69刷)
「長年、遊び慣れた場所を、剝き出しになるように壁や天井を壊し、解体し、大騒ぎして(荷物をまとめ)、たいそう霧が一面に立ちこめる夕方、車に乗って出発しようと、振り返ってみると、人が見ていない間に額を床につけてお祈りした薬師仏が立ちなさっている。それを見捨て申し上げるのが悲しく、他人に知られぬ涙を流した。」
壁や柱などの建材は当時、貴重で、使えるものは引っ越しの時に持ち運んだという。しかし、薬師仏の仏像は捨てていく。物語的な前後関係の文脈からは、作者が上京できたのは薬師仏が祈りを聞き届けてくれたからであろう。その大恩のある仏像を廃棄し、自分だけちゃっかり都に行くわけである。その薬師仏は何も言わず、ただ立っているだけ。しかし、「真実の口」効果を体験している読者は、このシーンで仏の「顔」をイメージするはずだ。いや、それは「後姿」でもかまわない。その映像がわたしたちに思考を促し、考えることに駆り立てる。
作者は「真実の口」演出を意図したわけでは当然、ない。ただ、ありのままのようすを描写しただけなのだ。しかし、読者に対する効果はスピルバーグの諸作品と同じものである。
このように、映画やテレビが生まれる前に、どう考えても映像向きとしか思えないシークエンスやカットが書かれることがある。わたしは生まれたときにはすでにテレビがあった映像世代だが、小説や物語などでそういう描写に遭遇すると、やはり度肝を抜かれる。代表的なのはレフ・トルストイだろう。『復活』(1899)の、以下で示すシーンはどう考えても映画の1シーンである。
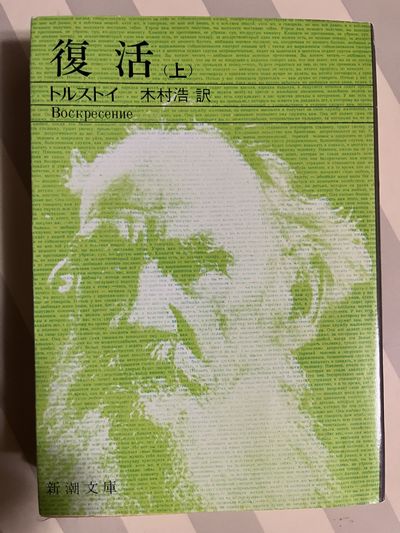
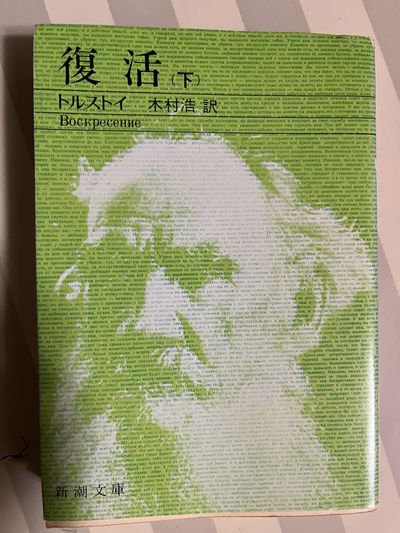
新潮文庫の翻訳者、木村浩が下巻巻末に解説を寄せた。そこでトルストイが『復活』を書くことになったエピソードを紹介している。友人の裁判官が、裁判で知ったある男女の物語を作家に伝えた。それは『復活』のオリジナルストーリーとでもいうべきものだ。以下で提示し、おおまかな粗筋としたい。未読の方はご注意を。
p371~372「フィンランド湾にのぞむある貸別荘に、妻を亡くしたフィンランド人が娘のロザーリヤとともに暮らしていた。やがてそのフィンランド人が死んで、娘は別荘の持ち主である裕福な婦人に引きとられた。はじめは養女のように大事に育てられたが、しだいに冷たく扱われるようになり、ついには女中部屋に追いたてられた。彼女はそこで十六歳を迎えた。ちょうどそのとき、女主人の親戚に当る大学を出たての青年が遊びにきて、ロザーリヤに目をつけ、誘惑した。女主人はロザーリヤが妊娠したことを知ると、怒って家から彼女を追いだしてしまった。青年からも捨てられたロザーリヤは赤ん坊を生むと、自分は最も低級な娼婦に身を落した。あるときペテルブルグのセンナヤ広場近くの宿で、ロザーリヤは酔っ払った客から百ルーブルを盗み、裁判にかけられ、四カ月の刑に処された。その裁判の陪審員のなかに、偶然かつてロザーリヤを誘惑した男が混っていた。法廷でのロザーリヤとの再会は、その男に強烈な印象を与え、彼の良心を呼びさますことになり、彼はロザーリヤと結婚することを決意した。……(略)」
トルストイ『復活(下)』(木村浩訳/新潮文庫/1990年 18刷)
小説『復活』ではロザーリヤではなく、カテリーナ(カチューシャ)・ミハイロワ・マースロワ。フィンランド人の娘ではなく、ロシアの地主屋敷で奉公していた百姓女の娘だ。父親は不明。地主姉妹の老嬢に気に入られ、養女のような、あるいは小間使いのような立場で成長した。母親は3歳のときに病気で死んでいる。16歳のときに、老嬢たちの甥の青年が遊びに来て、彼女を妊娠させてしまうのだ。
誘惑した若者はドミートリイ・イワーノヴィチ・ネフリュードフ公爵。ネフリュードフに捨てられてから売春婦になるまで、カチューシャにどのような遍歴があったのか、トルストイは冒頭で丁寧に説明する。
さて、身重のカチューシャは、地主屋敷のそばの駅に向かう。軍務についたネフリュードフが汽車に乗って、その駅を通過することを知ったのだ。せめてひと目だけでも彼に会おうと決心し、大粒の雨の降る秋の夕暮れ、彼女は停車場に急ぐ。この時点では、彼女は自分が捨てられたことに、まだ気づいていない。
ようやく駅に着くと、汽車はすでに動きはじめていた。一等車の車窓に、ネフリュードフの姿を見つける。明るく、あたたかそうな車室で上等な衣服に身を包み、ふかふかの座席に座っている。仲間の士官たちと楽しそうに談笑している。
彼女は窓に近づき、手でドンドンと窓ガラスを打った。
p214「……彼女はもう一度窓を叩いて、その顔をガラスに押しあてた。そのとき、車輛もごとんと一つ動いて、ゆっくり動きだした。彼女は窓をのぞきこみながら、並んで歩きだした。士官は窓を下ろそうとしたが、なかなか下りなかった。と、ネフリュードフが立ち上がって、その士官を押しのけ、自分で下ろしにかかった。汽車は速力を早めた。カチューシャは窓から目を放さずに急ぎ足で走った。汽車はいよいよ速度を早めた。が、ようやく窓が開かれたとたん、車掌が彼女を突きのけて、その車へ飛びのった。彼女は少しおくれたが、それでもまだプラットフォームの濡れた板の上を小走りに走っていた。ついにプラットフォームがつきた。カチューシャは転ばぬように足をふんばりながら、階段づたいに地面へかけ下りた。彼女はなおも走り続けたが、もう一等車ははるか先のほうになってしまった。二等車がそばをかけぬけたかと思うと、つづいてそれよりもっと早く、三等車が次々に通りすぎていった。しかし、それでも彼女はなおも走りつづけた。ついに、尾燈のついた最後の車輛が通りすぎたとき、彼女はもう柵をはずれた給水タンクの先まで来ていた。と、風がどうっと吹きつけて、彼女の頭からプラトークを奮(ママ)おうとしながら、その足にスカートの裾をからみつかせた。ついにプラトークは風に飛ばされてしまった。それでも彼女はなおも走りつづけた。
「おばちゃん、ミハイロヴナおばちゃん!」やっとのことで彼女のあとにつづいて走りながら、女の子は叫んだ。「プラトークが飛んじまったよ!」
《あの人は明るい一等車の、ビロード張りの柔らかいシートにすわって、冗談をいったり、お酒を飲んだりしているのに、このあたしはこんな真っ暗なぬかるみのなかで、雨風に打たれながら、泣いているんだわ》カチューシャはそう思うと、その場に立ちどまって、ぐっと頭をうしろへそらすと、いきなり少女を抱きしめて、はげしく泣きだした。
「行ってしまった!」彼女は叫んだ。」
トルストイ『復活(上)』
長い引用になってしまった(汗)。しかし、この一連のシークエンスは切れ目のない心象風景である。捨てた男は、光り輝く高速の乗り物にのって安楽に過ごし、談笑している。一方、捨てられた女はそれを必死に追いかけ、暗い雨の降る夕暮れ、ついに力つき、寒さとぬかるみのなか立ちつくす。
なぜ、これが映画の1シーンではないのか!?
このシーンを観るだけで、観客は多くの事情を了解するだろう。情報量が圧縮された、ドラマチックなシークエンスだ。
トルストイの映像的想像力は『戦争と平和』(1864~69)のボルコンスキー公爵が戦場で倒れ、空を見上げるシーンなどでも有名だ。しかし『復活』のこのシークエンス、単に映像的想像力というのでなく、映画的想像力といえる。「動き」のなかにドラマのメタファーが埋めこまれているからである。
この『復活』が20年ほど前に映画化された(ネットで確認すると、2001年にテレビ映画化されたらしい)。ノートによると、2004年4月5日に劇場で鑑賞している。札幌市狸小路にあるミニシアターだ。監督はイタリアのタヴィアーニ兄弟。「妊娠したカチューシャが、そのことを告げに深夜、ミーチャ(ネフリュードフ)の乗る汽車を求め、駅へ行くシーンがあった」と当時、わたしは記入している。そう。ご想像通り、まったく忘れているのである(ううう)。石炭を燃料にする重たい鉄の塊である蒸気機関車の重量感、圧迫感、威圧感を映像で目の当たりにし、現実に映像化したシークエンスを高評価している。うーむ、まるで覚えていない(苦笑)。
とはいえ、記憶しているシーンもある(エッヘン!)。
次のふたつは特に感心した。
まず、スケートリンクのシーンだ。『復活』は長大なテキストなので、2~3時間の映画にまとめるのは難しい。実際は187分あった(ネットで確認)。約3時間だが、それでもストーリーはすべて収まらない。そこで、些末な出来事は登場人物が口で説明することになる。貴族の娘がネフリュードフとスケートしながら会話する。そうやって多くの筋を見事に端折(はしょ)っている。このシーンではチャイコフスキーの「花のワルツ」が流れる。実に効果的な使用で、台詞の流れと曲想の流れが完全に一致していた。とても印象的だった。
もうひとつは、ラストシーンだ。原作では福音書を引用する。いかにもトルストイっぽいけど、現代の読者、鑑賞者には説教くさい。そこで、次のように処理していた。
シモンソン(カチューシャが新しい伴侶に選んだ男)とともに汽車で、シベリアのさらに奥地に去ったカチューシャと別れた後、ネフリュードフはしかし、すぐにはモスクワに戻らなかった。彼はカチューシャに捨てられた形になり、孤独と寒さにさいなまれている。だがカチューシャが幸せなら、問題ないはずだ。それこそが彼の望みなのだから。複雑な心境を持て余しつつ、夜の闇のなか宿を探す。すると、ある建物のなかでパーティが開かれている。「新世紀(作中では20世紀!)」を迎えたお祝いなのだそうだ。
パーティに集まったひとびとは、ささやかで個人的な祈りを、0時の時報とともに願う。「人気者になりたい」「金だ。金持ちにしてくれ」「健康でありますように」「仕事の成功を祈る」「子どもたちが元気に育ちますよう」……
「あんたは何を願うの? さあ!」と促され、ネフリュードフはこう答える。
「愛するひととの幸せを」
あー。これまた強烈な「真実の口」効果である(演出方法はちがう)。わたしたちはすでに、20世紀がどんな時代だったかを知っている。そして、この映像作品がもともと2001年に公開されたことは、このラストシーンと無縁ではあるまい。作り手は「新世紀」という言い方に「21世紀」を含意しているのだ。
わたしたちは21世紀の最初の23年がどういう経過をたどったか、すでに知っている……。「愛するひととの幸せを」を願うシーンは、わたしたちをじっと見返し、思索を促すことになる。映像は語りかけ、問いかける。
みなさん、愛するひとと幸せに過ごせていますか? (了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon