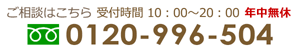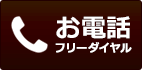久しぶりに文庫解説の仕事をちょうだいした。アマゾンで予約販売がはじまっており、書影も出ているので情報解禁のようだ。この三月兎之杜さんでも「くろけんの古書店探訪記」をアップしている黒田研二の『神様の思惑』(2019年刊行の単行本『家族パズル』を文庫化に合わせて改題。講談社文庫)。「家族」をテーマにした「心あたたまる」ミステリ短編集である。12月15日刊行予定なり。リンクを貼っておく。クリスマスプレゼントにどうでしょう!

神様の思惑 (講談社文庫) | 黒田 研二 (Amazonサイトより書影引用)
依頼があったのは9月中旬。「10月20日くらいが締め切り。400字詰め原稿用紙10枚程度」というお話だ。
(生まれてはじめて、原稿料をもらった仕事って何だろう?)
と考えてみると、1998年の雑誌のライター仕事だったように思う。それより前、1989年にアルバイト先の受験予備校で、中学生向けの国語のテキストを作成したことがあるが、「本」にかかわる原稿料ではなかった。
「Weeklyぴあ」(ぴあ)や「東京ウォーカー」(角川書店)など「街ネタ」情報誌が刊行され、ブームになったのが1990年代(「ぴあ」は70~80年代から人気で、わたしの感覚では「老舗(しにせ)」だった)。講談社も97年、「TOKYO1週間」というタウン誌を創刊した(2010年で休刊)。サラリーマン時代の後輩が、この編集部で働いており、むかしのよしみで仕事を回してくれたのだ。98年5月5日・12日合併号の「GWは和製ホラー&ミステリーを楽しもう!」という読書特集に「下請けライター」として参加した。
わたしが担当した書評は2冊。綾辻行人『十角館の殺人』と法月綸太郎『二の悲劇』。FAXもパソコンも持っていなかったので、原稿を郵送したんじゃないかな。当時は品川区のマンションに住んでいた。バイク便でゲラを届けられたときは、「ぐえ。物書きみたい!」と興奮し、奇妙な感慨におちいった。たいした文字数を書いていないのだが、ギャラはけっこうよかった。

さて、10月前半を通して文庫解説の執筆をおこなっていたのだが、筆はよくすすんだ。わりと支障なく、アイディアもぽんぽん飛び出し、タッタカタッタカとキーボードを叩き進めた。15日くらいには完成していたと思う。それでも、著者の未読作品が若干あって、古書店や図書館をまわってかき集めた。16日日曜は日中、あたたかく、部屋の換気をかね、窓を開けて読書に集中。午前に1冊、午後に1冊、夜に1冊。がんばって集中するとなんとか日に3冊読める。読めるひとは、おそらくもっと読めるのだろう。しかし、わたしは3冊が限界。16日もそのペースで読み進め、すっかり日が沈んで気温が下がっても、部屋の窓を閉めるのを忘れていた。
(あれ? なんだか寒気が……。熱っぽい? ま、寝れば治るだろう)
と、布団に入って就寝。あまり眠れないまま起床。
本格的に具合が悪い。
体温計を脇に挟むと、37.5度である。
職場に電話し、「熱があるので休みます」と伝える。時節柄、当然のようにコロナ罹患(りかん)を疑う。陽性か陰性か、判断するには抗原検査キットが必要だ。しかし、それを手に入れるためには外出しなければならない。コロナかもしれないのに、ふらふら外に出てよいものであろうか? ただの風邪ならよいのだが……。
閉じこめられた部屋から脱出するのは小さな扉のみ。そのためには身体を、うんと小さくしなければならない。「わたしを飲んで」の薬を飲んでみると、扉をくぐれるくらい小さくなった。しかし、小さな扉を開ける金色の鍵はガラス・テーブルの上にのっている。背が低すぎて、今度は鍵に手が届かなくなった。何かをなしとげる条件を満たしたとたん、(条件を満たしたことが原因で)その行為が実行不可能になったのだ。これを「わたしを飲んでパラドックス」、略して「わたのんパラドックス」という(うそです)。
ま、もうちょっと休んで様子を見よう。とりあえず、文庫解説のデータを出版社に送信した。
18日火曜になると、熱は38.5度。
SNSでツイートする。すぐに諸岡卓真(このエッセイに何度も登場しているミステリ研究者・評論家さん)からLINEのメッセージがくる。はやい! つーか、わたしのツィートをチェックしているんですね! フォロワーじゃないですよね(ミクシイ時代は「マイミク」さんだった)。
諸岡「何か必要なものがありますか?」
わたし「抗原検査キットです。果物も食べたい(遠慮なし)」
諸岡「午後1時くらいにうかがいます」
わたし「ドアの前に置いてください」
熱は相変わらず高いのだが、洗濯をする必要があった。寝衣、寝具みな大量の汗でびしょびしょだ。ごそごそといちど起き出し、洗濯をする。布団乾燥機も大活躍。
部屋のチャイムが鳴る。(あ。諸岡さんだ!)と玄関に行くが、わたしにはコロナ感染の疑いが。ドアを開けずに会話する。
わたし「諸岡さん! ありがとうございます」
諸岡「……………!」
わたし「え? なんですか? 洗濯機の音が大きくて聞き取れません!」
諸岡「……………!?」
わたし「わたしの声は聞こえますか? 届いていますか、この感謝の言葉がー」
諸岡「………………… …… ……」
らちが明かないので、スマホで電話した。いくつ必要か分からないので、抗原検査キットをふたつ用意してくださったそうだ。買い物のレジ袋をドアの取っ手にかけてある、とのこと。
前後して、千澤のり子からもLINEが来る。
千澤「大森さん、だいじょうぶですか?」
わたし「諸岡さんが支援物資を提供してくださいました」
千澤「わたしもネット通販で必要なものを送ります。何か欲しいものはありますか?」
わたし「いやいや。大丈夫ですよ(いちおう遠慮する)」
千澤「ネットでちゃちゃっとやっちゃえるので、まったく手間がかかりませんよ」
というわけで、札幌市内にある我が家の近所の大手量販店から、東京発注の日常雑貨・食糧支援物資が届いた。ありがたやありがたや。21世紀万歳! その後、千澤のり子には代金を銀行振り込みで返済した。諸岡卓真は同じ札幌在住なので、直接会った時に返すつもりである(と考えて、未返済のまま今にいたる)。
諸岡が届けてくれた抗原検査キットは、綿棒を鼻の奥に挿入し、ぐりぐりするやつ。陽性を示すサインが、はっきりあらわれた。
(オオ! とうとうコロナに……)
その時点では、さいわい、症状は熱だけだった。味覚嗅覚が消えることも、のどの痛み、頭痛や吐き気もなし。極度の倦怠感……は、ふだんからあるので、よく分からない(歳のせいである)。コロナの症状なのかどうかはっきりしないが、ひどく眠かった。9~10月はばたばた忙しく過ごしており、睡眠も不足していたせいだろう。はっきり「陽性」と分かった時点で、精神的に開き直った。しっかり寝て、休んで、病気を治そう。じたばたしてもはじまらないのだ。
数年前、声帯結節をやってから、就寝時もマスクをつけるのが習慣化している。咽喉が保湿されるせいか、しだいに声が戻ってきた。最初は寝苦しかった。しかし慣れたのか、最近はあまり気にならない。むしろ咽喉の調子がよい。マスクをつける前はたぶん、口を大きく開けて、「グガー」と寝ていたのだろう。
そういうわけで、(咽喉を保湿し、コロナウィルスへの抵抗力を養えるから)とその晩もマスクを装着して寝た。あまり何も考えていなかったのだ。
その夜、締めつけるような咽喉の痛みで目が覚めた。
(コロナの症状に「唾を飲むだけで痛い」咽喉の痛みがあったが、まさにそれではないか!)
寝ぼけた状態で仰天する、という器用な体験を味わう余裕はない。反射的にマスクを取った。外気をむさぼり、深呼吸をくり返す。すると、痛みはふしぎに緩和するようである。
(あれ? マスクはずして寝た方がいいのかな……あれ? あれれ? ……スー……むにゃむにゃ……)
とふたたび眠りにおちる。
翌朝、咽喉の痛みは引いていた。
目が覚め、頭のなかもしっかりしてきた。昨夜の体験を反芻する。
(これはつまりあれだな。咽喉の奥で繁殖したコロナウィルスを呼気とともに吐き出す。それを吸いこんで、咽喉の奥に戻す。ウィルスはさらに繁殖し、呼気で大量に吐き出される。それをまた吸いこんで……。つまりセルフ2次感染、3次感染ではないか!)
自宅療養する陽性患者には、そういう危険があったのである。「部屋の換気をするように」と行政からも注意されていたが、「そういうことか」とようやく腑に落ちた。自分が自分自身を何度も感染させ、重篤化させる可能性があるのだ。おそろしやおそろしや。
それからは用心した。定期的に窓を開け、換気を入念におこなった。熱もしだいに落ちていき、経過は良好。行政にリクエストした生活支援物資は、手配や配送に2~3日を要した。到着時には自宅療養期間が終わりかけていた。
さて、というわけで今回紹介するのはまず、ダニエル・デフォーの『ペスト』(1722)である。中公文庫の初版は1973年。オイルショックのせいで、日本はトイレットペーパー買い占め騒動があり、やはり群衆パニックの年だ。
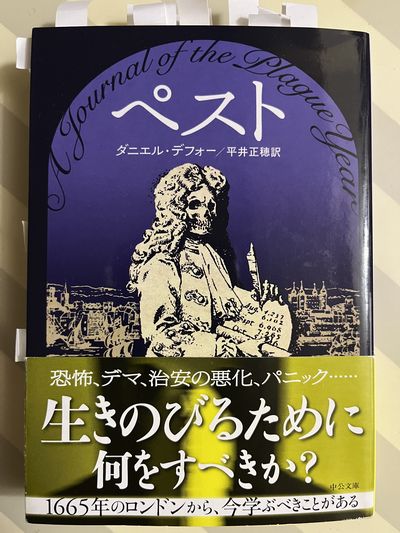
なかなかおっかない表紙である。
1665年、ペストがロンドンを襲い、多くの死者を出した。商売をしている「私」は、はやばやと田舎に疎開する兄の忠告にさからう。神の加護を信じ、ロンドンに残ることを決めたのだ。そこで見聞きした阿鼻叫喚(あびきょうかん)、鬼哭啾々(きこくしゅうしゅう)、死屍累々(ししるいるい)の地獄絵図、ひとびとの抵抗や慈善行為を描いている。
解説では、次のことが指摘されていた(訳者の平井正穂による解説である)。
デフォーの生年は1660(一説には1661)年だ。つまり、1665年には5歳たらず。当時の記憶などほとんどないか、かなりあいまいだろう。ペスト禍は憶えていても、親に連れられてさっさと疎開していたはずだ。要するに作中の「私」は、完全なフィクションの語り手である。叔父に馬具商のヘンリー・フォーなる人物がいる。「私」は名前のイニシャルが「H.F.」なので、この叔父がモデルではないか。
とはいえ、内容までうそ、でっち上げではない。語りのキャラクターを仮構しただけで、5歳当時の災厄をデフォー(執筆当時、60歳くらいか)は調べ、取材し、事実に基づいて書き記していったのだろう。
わたし個人がコロナで自宅療養を体験したせいか、特に印象に残ったのは「家屋閉鎖」である。
ペストの魔の手がロンドン市内に広がり、死者数が急増しはじめると、市当局は次のような手を打った。感染者が確認された家屋を、まだ感染徴候の見られない健康な(?)家族(つまり濃厚接触者)ともども閉鎖し、隔離したのである。ペストの致死率はコロナの比ではない。感染者はやがて高熱を発する。首、脇の下、鼠蹊(そけい)部にぐりぐりした腫脹(しゅちょう)を生じる。こうなるとすでに病状は末期で、この腫脹が激烈に痛むらしい。譫妄(せんもう)状態になり、やがて狂い回り、突然、卒倒する。確認すると、息絶えている。朝に感染が確認され、夕方には死んでいる例も多い。医者に感染を宣告され、ショックで気絶し、そのまま死亡する例も。
そんな病人と一緒に閉じこめられるのである(!)。ポオの短編「早すぎた埋葬」ではないか。
コロナ同様、ペストは感染しても発症していなければ本人に自覚症状がない。「わたしは健康だ」と思っている。それなのに、感染した家人と閉じこめられる。感染や発症、死の危険におびやかされることになる(その時点で感染している可能性はあるし、かなり高い)。
当局は閉鎖した家屋の扉や壁に赤い十字と、「主よ、憐みたまえ」という文句を書いた。昼と夜の二交代制による「監視員」を1名やとい、張り番とした。閉鎖された家屋の住人は食糧、生活雑貨など必要なものの購入を、この監視員に依頼できた。
しかし、たった1名だ。
家屋の出入り口は1か所ではない。裏口もあれば窓もある。監視員が正面の玄関扉だけを見張っていても、裏口や窓から出入りし放題である。そのような行為はもちろん、当局が禁じていた。だが、道理に反した法令にひとを従わせることは難しい。一見、健康な家人たちは夜になると、こっそり窓から抜け出す。外気を吸ったり気晴らししたりする。あげくに、そのまま病気の親や子どもを打ち捨てて逃亡した。
準備をすっかり整え、「あれこれのものを買ってきて」と、なるべく遠くに監視員を使いに出し、そのすきに逃げ出す家人もいた。当局が描く前に自宅の壁に赤い十字、「主よ、憐みたまえ」の文句を書き、すでに家屋閉鎖が実施されているように偽装する家もあった。そして家人は当局の監視からうまく逃れ、タイミングを見はからって脱出した。
そうやって家屋閉鎖を逃れたひとびとはどうなったか? しだいに身体がペストにむしばまれ、外見にもあきらかな兆候が出はじめる。市民は誰も近寄らず、相手にしなくなる。食料は手に入らず、宿の宿泊はこばまれる。街道をさ迷い歩き、体力の限界がくると道端に倒れる。最後は病毒が身体をむしばみ、野ざらしの死体となるのだ。結局、ペスト菌をロンドン市内に広める結果となる。
p291「全体的にいって家屋閉鎖ということが悪疫の伝染をくい止めるのに相当な効果があったかどうか、これは今日でも疑問視されている。効果があったとは私はいいきれないと思っている。悪疫が猛烈な勢いで広がっていったその凄まじさに匹敵するものはほかにはなかった。そういう時に、感染した家を、いくら厳重に、効果的に閉鎖したところで結局なんの役に立つものではなかった。病気にかかった人間を全部有効に適切に隔離してしまえば、健康な人間がそれらの病人から病気をうつされるということはいかにもありえなかった。第一、近寄ろうにも近寄ることができなかったからである。ところが、ことの真相は次のとおりであった。私はここで簡単にふれておきたい。つまり、感染は知らず知らずのあいだに、それも、見たところ病気にかかっている気配もない人たちを通じて蔓延していったということである。しかも、その人たちは、自分がだれから病気をうつされ、まただれにうつしたかもまったく知らないのであった。」
家屋閉鎖を批判し、感染者のみを一か所にまとめ、集中的に治療、看護する施設――「避病院(ペスト・ハウス)」――を複数、用意し、実用に供するべきだった、と「私」は主張する。
現在、われわれは「鳥インフルエンザの殺処分」の報道に接する機会が多い。鳥インフルに冒された個体も、同じ養鶏場にいる健康な個体も、いっしょくたに処分されるのだ。万単位で。この対応を、人間に当てはめた印象を受けるのが家屋閉鎖である。感染者、濃厚接触者をひとつにまとめ、隔離し、未感染で健康な市民を救おうという判断は、いかにも行政が考えそうなものだ。人命を「数字」という抽象概念で捉えているからだろう。死者数も生存者数も、行政にはただの「数字」にすぎない。「一羽」も「一人」も「一」なのだ。てっとり早い対策で、即効性をねらった対処療法である。
しかし、医療関係者は具体的な「ひと」を見る。感染者も未感染者も、すべてのひとを救おうと考える。行政の指示に従う一方、感染症の原因や根本的な対応策を研究しつづける。その結果、細菌やウィルスが発見され、ワクチンが開発されたのだ。
したがって、デフォーの時代よりも、21世紀のわたしたちは感染症パンデミックに対し、有効でスマートな対応をとれるはず……。だが『ペスト』を読んだ印象は、コロナ・パンデミックとの類似点である。なるほどペストは、コロナとくらべものにならないほど致死率が高い。一方、感染しても発症するまで自覚がなく、接触した知人や家族に知らぬまま感染させてしまう――という共通点がある……。関心を抱いた方は、ぜひ本書を手に取り、内容に触れてほしい。
家屋閉鎖みたいなケチケチした話と交錯するのが、太っ腹な金銭的援助、食糧援助の話だ。ロンドン市当局、貴族や富豪たちは多額の寄付金を提供した。
p172「それにつけても、生命の安全を求めて田舎(いなか)に疎開した市民たちが、自分自身は逃げはしたものの、後に残した者の福祉に多大の関心を示していたことははっきりと記しておかなければならない。彼らはロンドンに残留している貧民の救済のためには、惜し気もなく多大の寄付をしたのであった。のみならず、イングランドの田舎にある商業都市においてさえも、多額の救済基金が募集されていた。貴族や紳士階級の者も各地において、ロンドンの悲境に大きな同情を寄せ、貧民救済のための多額の義捐金(ぎえんきん)を市長ならびに市当局者あてに送ってきたといわれている。国王も毎週千ポンドの金を四分して、それぞれの地区にご下賜になったという話であった。」
なんだか、うらやましい話である。
大きな災害にみまわれた土地ではつねに、ケチケチした話と景気のいい話が交錯する。詐欺師や火事場泥棒、集団の暴動、どさくさまぎれに自己利益をかすめ取ろうという話がある一方、恩恵や救い、ほどこし、なぐさめにまつわる美談が生まれる。
この傾向を集約しテーマとして扱い、近年、話題になったのがレベッカ・ソルニット『災害ユートピア なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか』(高月園子訳/亜紀書房/2010)だった。大地震、大洪水、大火災、巨大テロといった悲惨な出来事の直後には、互いにひとびとが助け合い、援助しあう「ユートピア」が、ごく短期間だが必ず生まれるというのだ。
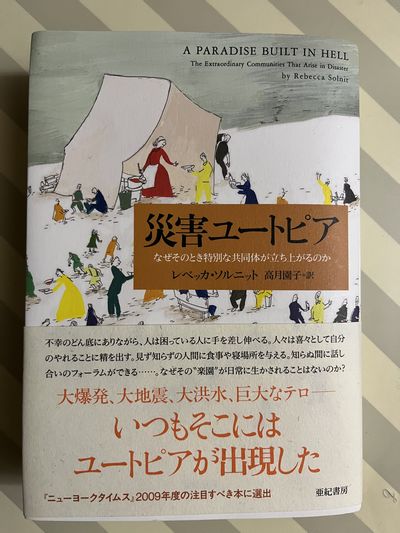
2001年9月11日、ニューヨーク同時多発テロ(後に「911」と呼ばれる)の直後のようすを、ソルニットは次のように説明する。
p314~315「九・一一の直後には、消防士、警官、役所の職員、ボランティアの職員など、大勢の公僕が集まって、機能不全に陥ったシステムを扱った。市民自身は、港湾局の『その場にとどまるように』とのアドバイスに逆らって貿易センタービルから逃げることに始まり、大規模な救助活動の組織化にいたるまで、大きな決断をした。ペンタゴンが対処できないでいると、市民は九三便の中で劇的なアクションを起こした。おそらく乗客たちの間で迅速な同意に達し、行動を起こしたのだろう。それは単なる相互扶助と利他主義の瞬間ではなく、ユニオンスクエアや、診療所や、仮設キッチンや、ボランティアたちの間に存在した直接民主主義の瞬間でもあった。人々は何かをしようと決断し、たいていは見も知らぬ人と力を合わせ、実行し成功した。これは無秩序な無政府状態ではなく、クロポトキンがいうところの自発的決定の無政府状態だ。これはまた、公的機関が対応不能になり、市民社会が機能する、災害時に典型的な現象である。これは権威が不在のときに、市民の中に、少なくとも束の間の活発な市民社会を作る意志も、そして能力も存在している証拠だ。」
感染症パンデミックにかぎらず、過酷事故、巨大災害、深刻なテロ、また地域紛争や戦争はこれからの時代、ますます身に迫っている印象だ。そんなとき、ソルニットの『災害ユートピア』は、生命の危険にあらがうひとびとの健全な意志や能力への信頼をかき立ててくれる。危機の時代を生きるための指針を与えてくれる。
わたしのコロナ感染は、さいわい軽症だった。日曜日に発症し、木曜には熱が引いていた。自宅療養なので、外出は不可。それでも深夜になると、(誰にも会わなければいいんじゃないか? 自転車に乗って夜の街をふらふら見てこようかな。窓の外の月、なんだかすごくきれいなんだよなあ……)などと考えてしまうのである。1週間、閉じこめられるのは、なかなかの苦行だ。
デフォーの『ペスト』によると、家屋閉鎖期間は40日。気が遠くなる。今はコロナ第8波の最中で、感染状況は予断をゆるさない。みなさん、お気をつけて。なんとか12月も乗り切っていきましょう。感染時、直接支援してくださった方々、またSNSなどで心配してメッセージを寄せてくださったみなさん、ありがとうございました。(了)
※文中、地の文では敬称を略した。
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon