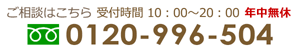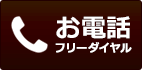明けましておめでとうございます。
2023(令和5)年、新しい年がはじまった。初夢は特に見た記憶がない。しかし、「夢」の話を披露しても、そう唐突ではないタイミングである。1年を通して、見た夢を語れる機会はそうない。今回はまず、いつか見た夢の話をしたい。……見たのがいつなのか、記憶にないのだが、その内容は鮮明で印象深かった。次のようなものだ。
新しく開店したデパートへ行った。
たいして欲しいものはないのだが、商品の陳列が珍しく、フロアをあちこち見て回る。新規出店したテナントも多く、どこもすごく混雑している。それで精神的にも身体的にも疲れてしまった。何階かわからないが、奥のエレベーターコーナーにソファがある。誰も座っていない。(やれやれ)と腰をおろし、ひとやすみ。
すると、知らない紳士が近づいてきて、隣に座った。口ひげを生やしており、恰幅(かっぷく)がよい。仕立てのよい、三つ揃いのスーツ姿である。ぎょろりとした大きな目でわたしを見る。
「お久しぶりですね」
親しげに話しかけてくる。
誰だっけ?
そう思いながら、適当に調子を合わせ、会話する。その間に、記憶を探る。会話に何かヒントはないか、としばらく、やり取りする。
「さて、そろそろ時間ですね。こちらへどうぞ」
と立ち上がる。わたしもつられて立ち上がった。紳士に誘導されるまま、ソファの壁の裏側に移動する。
おどろいたことに、そこは舞台――ステージなのだ!
正面は客席だ。数十人の観客が席に座っている。舞台に登場したわたしたちふたりを、好奇心もあらわに注視している。前列右側に、白いタイツ、黒いワンピースの少女が座っていた。興味しんしんといった表情である。
仰天し、かたまってしまった。そこに、完全に芝居口調の台詞が聞こえてくる。
「あなた、そちらは、どなた様?」
舞台の下手には、緑のカーディガンに裾の長い紺色のスカートの、年輩の女性が立っている(わたしたちは上手から登場した)。クラシックバレエでもやっていたのか、背筋がピンと伸びていた。頭髪はグレイ。切れ長の理知的な瞳が不審そうに、わたしをうかがっている。衣服は舞台衣装なのだろうか? メイクは完全にステージメイクだった。つまり、この夫人は「女優」なのだ。
「知人の息子さんだ。久しぶりにお会いしたので、なつかしくてね。お父上の消息を聞こうと、お招きした」
紳士の口調も舞台の発声だ。さっきまで親しげに会話していた調子ではない。
自分はここらへんで自己紹介しなければならない。しかしいったい、わたしは誰なのか?
「オーモリハノンです」と名乗っても、無意味だろう。ここはステージだ。役名があるはず。どうやら進行中の芝居に、途中から参加したようなのだ。
(デパートのオープニングイベントか?)
と考える。
デパート内に新設したミニシアターの「こけら落し」なのだ。買い物客を無作為に選び、舞台に「特別出演」させる。アドリブで台詞をいわせ、演技させる。ある程度、進行や演出につき合わせる。適当なところで退出させ、商品券か何かをプレゼントする……。となれば、ここで腹を立てたり、取り乱したりするのは野暮というもの。だが、舞台上のわたしはいったい、何の役なのか? 何者なのか……?
困惑していると、紳士はいう。
「吉丸さんに、あたたかい飲みものを差し上げて。外は寒かったからね」
夫人はうなずき、使用人を呼び、紅茶を命じた。
(オレは吉丸だったのか……)と認識する。「名前」が判明し、安心した。
その瞬間、どたん、という音と衝撃が伝わってきた。夫人が立ち上がり、悲鳴を上げる。振り向くと、紳士が舞台の床に倒れている。
「だいじょうぶ? だいじょうぶですか!?」
あわてて近寄り、介抱する。紳士の身体はぐったりし、まったく力が入っていないようだ。
――し、死んでる? まさか!?
手のひらを鼻と口にかざす。――息をしていない!
右手首を取って、脈を探す。――脈がない!
しかし昔、読んだミステリでこんな趣向があった。固いゴムボールを脇の下にぎゅっとはさむと、脈を止め、死んだふりができるのだ。紳士の脇の下を確認する。ボールは見えない。しかし、衣服の下にあるのかも……。
服をあらためようとすると、舞台を横切った夫人が寄ってくる。腕をつかんだ。
「おやめください! いったい、あなたは何者ですか? この人に何をしたのですか?」
「オレは……わたしは……」
「吉丸」のはずだ。しかし、この紳士は舞台上で、ほんとうに死んだのか!? 芝居をつづけていいのか? これは脚本の一部、台本通りの展開なのか? 夫人は「主人」でなく、「この人」といった。芝居の台詞ではないのか? 素の質問なのか? どこまでリアルで、どこまでフェイクなんだ? 観客はわたしに注目し、台詞を待っている。
「……た、たぶん、……ヨシマル……です」
「たぶん?」
客席から笑い声が上がる。
そこで自分は(これでいい。これは台本通りの展開なのだろう)という感触を得た。
「えーと……よくおぼえていないのです」
「おぼえていない? どういうことですか?」
夫人は糾弾する。しかし、すぐに気を変えて使用人を呼んだ。倒れた紳士を寝室に運ばせる(つまり舞台の袖から楽屋に運び出した)。転倒したのが、芝居の一環なのか、突発的なアクシデントなのか、分からない。だが、楽屋に運んでしまえば、医者に診察させたり救急車を呼んだりできるだろう。
「警察を呼びます。主人と古くからの知り合いだというのは、ほんとうですか?」
「いえ。えー……実は、ついさっき、お会いしたばかりで……」
客席からくすくす笑い声。どうやら、まちがったことはいっていないらしい。と、ここで自分の「役」についてインスピレーションを得た。
「では、初対面。あなたは……いったい……?」
「実は……わたしは、記憶喪失なのです!」
「記憶ソーシツ!?」
客席は爆笑している。
「たぶん、ご主人はわたしに似ているひと――お知り合いの息子さんをご存じなのでしょう。わたしは、そのひとにまちがえられた……」
「……すると……あなたは、ひとちがいにもかかわらず、我が家にのこのこやってきたのですか?」
爆笑。
「いや、面目ありません。ですがなにしろ記憶がないので、ご主人の勘ちがい、まちがいだという確信もないのです。……わたしは本当に、お知り合いの息子かもしれません」
「いずれにせよ、主人の意識が回復したら確認します。あなたが主人に何かよからぬことをした……とわたくしは疑っていますが……」
そこに私服の刑事が登場した。あまりにはやい!
「警察のものです。通報を受けてやってまいりました」
下手からあらわれたその男性を見て、おどろいた。さっき「死んだ」紳士なのだ。口ひげはない(付けひげだったのだろう)。三つ揃いのスーツではなく、くたびれた灰色のコートを着ている。となると、さっきの「死」は芝居の一環――演技だったというわけだ。内心、ほっとした。
「なにやら不審な人物のせいで、お宅のご主人が亡くなられたとか……」
「いえ。主人は死んでおりません」
夫人が即座に否定する。
「奥様。かかりつけのお医者様に連絡し、診断をお願いしました。ご主人様は……」
絶望的な表情で使用人が伝える。
「え……! なんですって!?」
状況的にはわたしが筆頭「容疑者」だ。「記憶喪失」を主張する、正体不明の訪問者。しかしわたしには、動機がないのだが……。
コートの刑事が近づいてきた。わたしの顔をのぞきこむ。
「職務質問をおこないます。『約束』、ご存じですね。守ってもらいますよ、『約束』を」
そう話しかけられ、ふたたび混乱する。
(約束……? なんの約束だ? 誰かと約束なんかしたっけ? 約束……約束……)
いったい事件(他殺)なのか、事故(心臓発作などの急病)なのか。死因はなんなのか。「吉丸」氏とは誰なのか。謎がふくらむ、不穏で不可解な状況のまま、目が覚めてしまったのである。
以上が、夢の内容だ。目が覚めてからも、気になっていろいろ考えてしまった。
これはリアル脱出ゲームのような、リアル推理ゲームなのではなかろうか。
参加希望者は、デパートの「ソファ」に、指定された時間に着席し、待機する。わたしがたまたま座った時間がちょうど参加希望の時間だった。参加者にまちがえられ、リアル推理ゲームの舞台に引き出されたのだ。舞台でアドリブの演技をしながら、動機、犯行方法、犯人を推理し、正解だったら賞金(100万円とか)をもらえるのだ。その状況はネットで有料配信され、視聴者も推理に参加できるのである。まあ、夢なので、こう考察しても「正解」はないのだが……。小説の書き出しとしては面白い。
さて、夢の話をえんえんしてしまった。この「気まぐれ本の森散歩」というエッセイは、そもそも本の話をするもの。というわけで、舞台、演劇、芝居にまつわる近作を紹介したい。
ジャニス・ハレット『ポピーのためにできること』(山田蘭訳/集英社文庫)である。
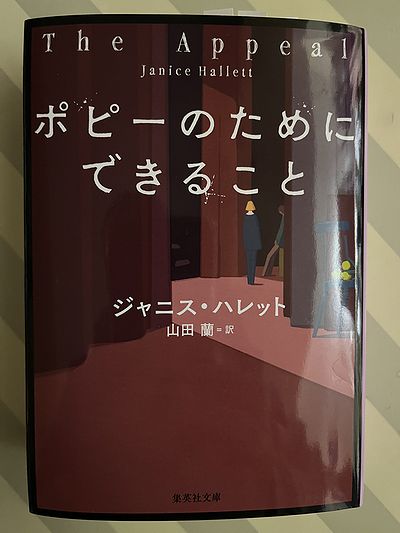
奥付によると、刊行は22年の5月だった。昨年末のミステリランキングの順位は次のとおり。「ハヤカワミステリマガジン」で5位。「このミステリーがすごい!」で3位。「週刊文春ミステリーベスト10」で4位。「本格ミステリベスト10」で1位である。かなりの高評価だ。ランキングではさらに上位のクリス・ウィタカー『われら闇より天を見る』(早川書房)より、個人的には面白かった。
英国の地方の資産家、ヘイワード家の2歳の少女、ポピーは「ごく稀(まれ)な型の脳腫瘍(のうしゅよう)」があると診断された。治療のためには米国で治験に使われた薬がよいらしい。しかし、その価格は25万ポンド(約400万円)だという。
右から左へ、ひょいと都合のつく金額ではない。そこでヘイワード家では募金活動を始めた。当主のマーティンは近在の有志を集め、アマチュア劇団を主宰している。その参加者たちは《ポピーに治療薬を》ダンス・パーティをはじめ、チャリティ・ハーフ・マラソン、「ヨガの夕べ」などの募金活動を精力的に開始する。しかし、いったいどれだけの募金が寄せられたのか、総額いくらになっているのかの情報はつねに曖昧だ。ただひたすら、ヘイワード家は「まだ不足」「よりいっそうの善意を」と呼びかける……。
一方、そのアマチュア劇団に新しく参加した看護師夫婦は、もともとアフリカで《国境なき医師団》に加わっていた。武力紛争が頻発する危険地域での活動は、モラルや常識が通用しないこともある。何かのトラブルを経験し、英国に舞い戻ったらしい。いったいどんな過酷な過去――闇を抱えているのか。それはやがて、大きな災厄に発展し、ついに深刻な事件が出来(しゅったい)する。
物語は主として、関係者のメールやテキストメッセージなど「会話」ですすんでいく。つまり、21世紀的な「書簡体」小説なのだ。地の文がないので、そこにはウソ、欺瞞、芝居、策謀、落とし穴が仕掛けられる。アマチュア劇団が背景に利用されるのもむべなるかな。全体が大掛かりな「芝居」「演劇」のようなのだ。
原題は「The Appeal」。つまり、支持や募金などの「呼びかけ」の意味と「自己顕示」「承認欲求」の意味が重ねあわされている。両方に「演劇的な演出」が含意されているわけだ。もうひとつ、裁判に不服をとなえ、「上告」する意味もあるが、こちらの方は実際に作品に当たって、内容を確認してほしい。物語の冒頭は、紛争地から英国に帰国した看護師(妻の方)の他薦紹介文である。「看護、あるいは医療介助の職に最適の人材であると、ここに推薦するものです」と「訴える」。結末は、ある登場人物の自己PR。「あたしはすごくきっちりしてて手際がいいし、人の手助けをするのが好きだから、こういう仕事にはまちがいなく向いていると思うんです」という「売りこみ」である。アピールで始まり、アピールで終わるのだ。原題は作品の主旨を的確に、深く反映している。
近年、アンソニー・ホロビッツをはじめ、英語圏では「本格謎解きミステリ」への回帰が主流のようだ。そのとき、お手本になるのはまず、アガサ・クリスティらしい。『ポピー』の解説は霜月蒼である。霜月は『アガサ・クリスティー完全攻略』(講談社)という評論ガイドブックで2015年の第15回本格ミステリ大賞(評論・研究部門)を受賞している。解説ではクリスティ作品との類似性を考察していた。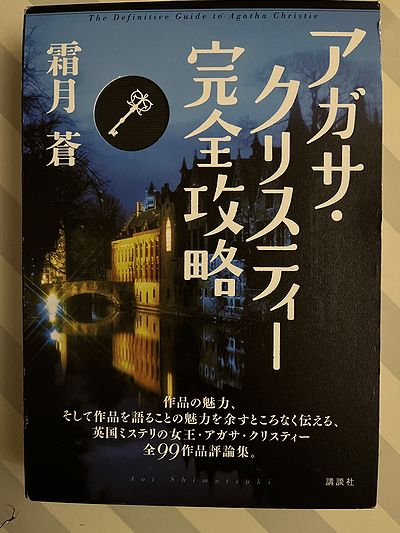
実際、クリスティ作品には芝居、演劇への言及が多い。そもそも若いころ、クリスティ自身がアマチュア芝居に出演していたはずだ。姉の方が熱心で評価が高く、クリスティはその後、声楽の方に関心が移ったのではなかったかな(記憶で書いています)。
『ねずみとり』のような記録的ロングランのミステリ芝居を書き、関係者が複数人で「劇団」のように、ニセの手がかりでポアロ相手に芝居を打つ話も書いている。「演劇関係者、特に☓☓が登場したら、犯人だと疑え」(あえて伏す)という文句は、クリスティ読者でおなじみだろう。『ポピーのためにできること』――クリスティのファンはぜひ、注目すべきである。
さて、「約束」の話に戻ろう。
今の段階で思い当たる「約束」といえば、この原稿を仕上げて、三月兎さんへきちんと送り届けることだ(あ! 今年はウサギ年ではないか)。なんとか書き上げたので、ミッション終了。「約束」を果たす。
では、みなさま、今年もよろしくお願いします。(了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
Twitter:https://twitter.com/OmoriHanon