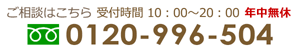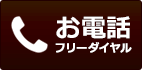中学生のころだろうか。倉多江美のマンガを読んだ。主人公の少年(青年?)がカミュの『異邦人』(1942)を読み、「太陽が黄色かったから、ひとを殺す」ことに、ずうっと違和感を表明しつづける内容だった。もちろん、記憶で書いている。読み直したら、きっとびっくりするだろう。「思っていた内容とぜんぜんちがう!」
とはいえ、主人公のキャラクターが「太陽が黄色い」「太陽が黄色かったから」と何度も吹き出しで連発していたのは、まちがいない。読んだわたしは、『異邦人』が「不条理文学」と呼ばれていること、「不条理」が何か、を知っていた。だが『異邦人』自体は未読だった。
というわけで、このとき、「不条理」の可能性として次の3点を思い浮かべたのだ。
1・太陽が黄色いこと(「太陽とは本来、赤いものではないだろうか?」)
2・太陽が黄色いことを理由に、ひとを殺すこと
(「そんな理由ではたして、ひとを殺すものであろうか?」)
3・以上の両方を組み合わせ、「不条理」というのだろうか?
実際に『異邦人』を読んだのは大学生のころ。読み終えてすぐ、興奮して席を立ち、部屋のなかをぐるぐる歩き回った。
(なんかこりゃもうすげーもん読んじゃったな! どうなるんだこりゃ。さっぱりわけわからんが、話の筋は一本ビシーと通っていて、展開はまったく不自然じゃない。それなのに、行動や発言はめちゃくちゃで何がなんだかさっぱりわからない。なんなんだこりゃ。どういうことだ? これがあれか。ブンガクというやつか? それでもどうでもブンガクなのか? そうなのか? ここは是が非でもブンガクでなければならないのか? ブンガクっていやでございますわね。 ぐぬぬぬ)
あんまり興奮して調子にのり、すぐに『ペスト』(1947)を読んだ。だが、こっちはまったく「フツーの小説」なのだ。盛大に肩透かしをくらった記憶がある。「消える魔球」を投げられた後、興奮して第2球を待っていたら、まったくクセのないストレートを投げられ、茫然として見送り、ツーストライクに追いつめられた心境だった。
第3球目は戯曲の『カリギュラ』(1944)だ。このテキストを読み、「消える魔球」の謎や、いったい何が「不条理」だったのか、理解できたように思う。そう。「太陽が赤くなく、黄色い」点は不条理ではない。フランス文化圏(『異邦人』の舞台はアルジェリア)では「太陽が黄色い」こと自体は当たり前=条理なのだ。
今回は「太陽と月」の話をしようと思う。
われわれ日本人は「太陽は赤い。月は黄色い」と感知し、そうみなしている。しかし、これは世界では少数派だという。多くの国では「太陽は黄色い」らしい。
では、月はどうなんだろう? ネットでいろいろ調べると、「月は白」という情報を見かけた。こういう色彩認識の異同は、「虹の色は何色あるか」という問題で説明されることが多い。文化圏によって虹の色の数がちがうというのだ。3色の国もあれば、5色の国もある。8色の国もあるそうだ。文化的色彩認識のちがいである。
たとえば日本でも「青信号」という。信号の色は「緑」だが「青信号」というのは、古来、緑も青に含め「あを」と呼んでいたかららしい。若山牧水の短歌に、
白鳥はかなしからずや 空の青 海のあをにも染まずただよふ
がある。空の青(ブルー)と、海の「緑がかった青」=「あを」を区別しているのだろう。また、森の木々の葉が生い茂っているようすを「あおあおと」と表現するが、これも本来は「あをあを」だったというわけだ。ほかに「緑の黒髪」という表現もあるが、これは……どうなんだろう?
手元の古語辞典で「あを」を引くと、「緑・藍・水色をも含み、ときに黒・灰色や白をも指す」とある。寒色系はすべて「あを」なのか。
ともかく、「太陽が赤い/黄色い」も以上の理屈で片づけられる。だが、ほんとうにそうか?
「太陽が赤い」ときは、もちろんある。日の出、日の入りの瞬間だ。また「太陽が黄色い」ときもある。日中、われわれの頭上にのぼっているあいだだ。これは光線の波長で説明できる。地平線上の太陽は、多くの大気の層を通過してわれわれの目に光を届ける。そのため、波長のゆるやかな「赤」だけが大気層を透過し、ほかの色彩が撥(は)ねられてしまうのだ。一方、頭上にある太陽は「黄色」の波長を透過させるわけである。太陽も月も星も、頭上にあるときは黄色くて、地平線上では赤いのである。
さて、わたしたちはどの太陽を見るだろうか?
わたしたち日本人は、太陽をあまり見上げないのだ。見上げるのは「月」である。日本人は「日の出」「日の入り」の太陽を、よく見るわけだ。朝日や夕日こそ、日本人が気に留める太陽なのである。さてところで、太陽とは王権の象徴ではなかったか。
太陽―天皇家
月 ―藤原貴族政権・武家政権
このように考えたとき、天皇の存在がひとつの政権秩序の勃興と滅亡のタイミングで歴史の地平に姿を現す、つまり「朝日」と「夕日」になっていると連想が働くのだ。したがって「太陽が赤く、月が黄色い」のは、日本の歴史の二重権力構造と関連しているのではないか、という仮説を思いつく。
古代社会における蛇信仰、鳥信仰を教えてくれたのは、鎌田東二だった。「龍性の淫―ブルー/トパーズの聖と性」という、村上龍の小説を「鳥シャーマン」に対する「蛇=龍シャーマン」の闘争と読み解く評論だ(「Ryu Book」現代詩手帖特集版/1990年9月/株式会社 思潮社)。
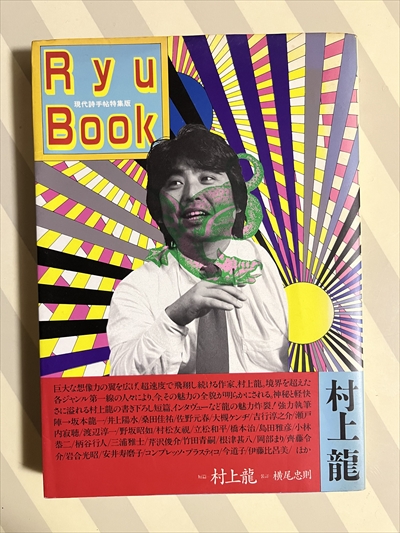
こういう民俗学的な文芸批評を読んだことなく、読み終えたときは、あっけに取られた。そして興奮し、鳥や蛇のシンボリズムについていろいろ、手探りで学びはじめたのだ。
古代社会の基底にあるのはまず、蛇信仰であるらしい。蛇、魚、鰐、鮫など川や海、水辺の生き物が信仰の対象となった。注目すべきなのは「水」なのだ。水は生命の源だ。これがないと、生き物は死んでしまう。農耕がはじまったら、水の確保はなおさら必要だ。いきおい、水にまつわる生き物が信仰の対象になっていく。特に蛇は脱皮する。古い皮を脱ぎ捨て、新しく生まれ変わる。その生態を古代人は「死と再生」という神話的なモチーフで解釈した。何度も死に、何度も生まれ変わる蛇は永遠であり、円環回帰する時間の象徴ともなっていく。
この「死と再生」のモチーフは月と結びつく。月もまた死に(新月)、再生する(満月)のだ。満ち欠けをくり返す月はまた、円環状に回帰する永遠の時間のシンボルである。
p73「蛇というのは、いつでも飛びかかってきて、無慈悲にも一咬みで人間を殺しかねない、あるいはすでに殺してしまった存在ということになるでしょうが、実はそうした存在であるだけでなく、みずから脱皮することで、身体がいわば生ける鞘から抜け出すようにして、自分の皮膚を捨てて、再び新たに生命を存続させるそのさまを、蛇はみずからにおいて体現している存在なのです。蛇は大地の中に這い込むこともできれば、そこからまた新たに姿を見せることもできるのです。死者たちが安らぐ地の底の冥界から帰還するゆえに―また脱皮して新たな皮をまとうこともあいまって―、蛇は不死のシンボル、病と死の苦しみからの再生のシンボルとなるのです。」
(ヴァールブルク『『蛇儀礼』三島憲一訳/岩波文庫/2008/原著は1923年の講演)
p28~29「ナウマンは、縄文人の象徴の中核にあったものの一つが「月」であることを突きとめました。人間にとってもっとも切実で悩ましい問題は「死」です。この死の恐怖から逃れることは人類にとって誕生以来の大きな命題でした。その命題への一つの答えが、「再生」するものへの畏敬だったとナウマンは考えました。そして「死と再生」を象徴するものとして昔から誰もが考えたのが月だったのだといいます。(中略)
蛇や蛙も、脱皮を繰り返すことから、月と同じように「不死」や「再生」を象徴するとナウマンは考えました。ナウマンは積極的には示していませんが、縄文土器に描かれた蛙がときとして赤ちゃんや女性器に見立てられるのも、それらが「再生」のシンボルとされているからでしょう。」
(大島直行『月と蛇と縄文人 シンボリズムとレトリックで読み解く神話的世界観』
寿郎社/2014)
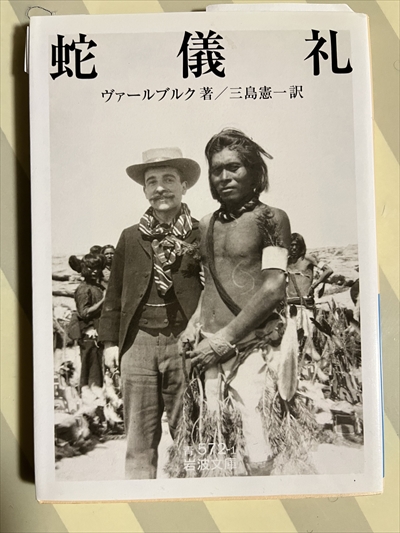

「ナウマン」は、ドイツの日本学の研究家ネリー・ナウマンである。
世界の四大文明がみな大きな河川の周辺から誕生したのは、もちろん偶然ではない。川のそばにムラ、マチ、都市が築かれたからだ。そこで川水を利用した農耕が営まれただろうことも、容易に想像がつく。
しかし、そうなれば河川の氾濫、洪水がたいへんな破局をもたらす自然災害だったことも了解できよう。何度、蛇神様に祈っても、雨は降りつづき、河川は湧き上がり、農地や宅地は水没する。家屋や財産は押し流され、家族はちりぢり、溺れて死んだり行方不明になったり。そうなれば、ひとは蛇への信仰を捨てるだろう。川のそばにムラやマチを築くのをやめ、もっと乾いた、そして肥沃な土地を求めることになる。だが、農耕のために依然として「水」は重要だ。
そこで、「雨」が注目されるようになる。記憶で書くが、「聖(ひじり)」とは「日知り」であったと、柳田国男が述べていた。「日」つまり太陽や天の運行、気象を支配するシャーマンである。ひとびとはしだいに、空を見上げはじめるのだ。「川」という水平方向の世界認識から、「雨」という垂直方向の世界観へ。この上下の意識が、王権、身分制度の発想をうながす。
p77「自分の手では何もせず、ただ単に存在するだけで離れた所から自分の環境に力を及ぼす――そういういわば太陽の如き人物を考え出したことは、人類の歴史の中でもっとも重要なことの一つである。それは統治機関の発明に他ならない。太陽=人間という教義が君主制に与えた形態に対して科学的な正当性がいまだに見出せないなら、これらの形態の異常なる存続とそれらの驚くべき生命力が示唆することは、責められるべきは君主体制であるよりもむしろその原因を解明できないわれわれの道徳哲学の未熟さであり、また君主体制にはわれわれがいまだに理解できない心理学的価値があるということである。」
(A・M・ホカート『王権』橋本和也訳/岩波文庫/2012/原著は1927)
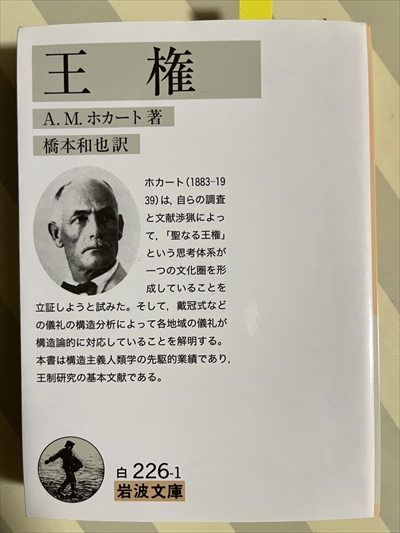
こうして蛇や龍は、天界の太陽の王族たちによって打ち負かされ、退治された。古事記や日本書紀の「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治」を思い出そう。
天空を支配する神々(あるいはその係累)が何らかの事情で地上に降臨し、蛇、龍、ドラゴンを退治する話はひとつのシンボリズムになっている。ヘラクレス(ゼウスの息子)が九頭の大蛇=ヒュドラを退治したように、素戔鳴尊(スサノオノミコト)は高天原から出雲の国に降臨し、八岐大蛇を切り殺す。足名椎(アシナヅチ)、手名椎(テナヅチ)の娘である櫛名多比売(クシナダヒメ)が人身御供にされるのを救うのである。このクシナダヒメは、日本書紀では「奇稲田姫」と表記される。「奇(くし)」には「神秘的な・霊妙な」の意味があるので、この姫が農耕に関連していることが了解できる。
p76「いま一つは、スサオヲが大蛇を退治して結婚したのがクシナダヒメであったという点である。書紀には奇稲田姫と記しているところから明らかなごとく、この名は水田耕作とふかい縁をもつ。つまり原始の水の霊に巫女として仕えた処女は、今や新しい豊饒霊の化身たるスサノヲに助け出され、その妻となることによって、稲田の奇(く)しき稔りを予祝するということになる。(中略)大蛇退治におけるスサノヲは、この季節祭における王の役割を神話的に表現したものである。王は共同体の首長で、それを代表する個人として大蛇とたたかい、そして勝ち、新しい豊饒霊として水と田の支配をおのれの有となし、さいごに聖婚をおこなうという演出である。」
(西郷信綱『古事記の世界』岩波新書/1967)
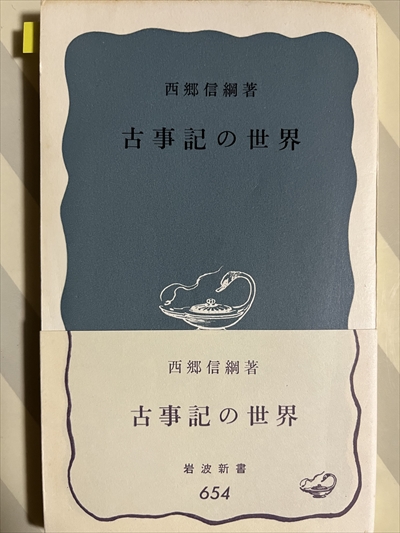
こうして、天界の太陽の神々=鳥信仰は、月にまつわる蛇信仰を圧倒し、葬り去る。素戔鳴尊の姉である天照大御神は、ばっちり太陽神の属性だ。その係累で、やはり伊弉諾(イザナギ)の片目から誕生した月読命(ツクヨミノミコト)=月を神格化した存在は、古事記・日本書紀で名前しか出てこない。記紀が太陽=王権の確立を主唱するシナリオを採用している以上、月の存在が閑却されるのは自然ななりゆきなのだ。
「鳥」で印象的なのは、熊野から大和まで神武天皇の軍を先導した八咫烏(やたがらす)だろう。鳥は天界からのメッセンジャーとして、天と地上をつなぐ役割をする。キリスト教でおなじみの「天使」も、鳥信仰の文脈で語ることができる。「受胎告知」は天使の仕事だった。日本の神社の「鳥居」も、天から飛んできた鳥の「止まり木」だという。
ただし、「鳥」は「蛇」と異なり、脱皮しない。死と再生の象徴をになうには不適切だった。そこで不死鳥=フェニックスの伝説が生まれたのではないか、と考えている。老いたフェニックスは炎のなかで燃えつき、その火のなかから新しく若々しい鳥として復活する。この当時、日本人に「太陽は何色か?」とたずねたら、「黄色」と答えたと思う。ヤマトのひとびとは頭上の太陽を見上げていたはずだ。こうして、鳥信仰は蛇信仰に取って代わり、人類のシンボリズムは一新された。
……はずなのだが、日本では「月」が復権するのだ。
日本の和歌に「月」の歌がやたら多いことはお気づきだろう。平成、令和のポップスでも「月」の歌は多い。太陽の歌もあるが、月の歌詞やタイトルの方が直感的に多いように思う。実は、万葉集の時代からそうなのだ。
p95「しかしその「自然」は大自然一般ではなく、極めて限られたものであり、しかも花鳥風月の特定の対象に集中しようとする傾向の著しいものであった。月の歌は多く、太陽や星の歌は極めて少ない。」
(加藤周一『日本文学史序説(上)』ちくま学芸文庫/1999/初刊行は1975)
散文では、なんといっても『竹取物語』と『土佐日記』だろう。つくり物語の、また日記文学の嚆矢(こうし)である両作品は、強力に「月」を押し出している。月は王権=天皇家を超越する存在として、『竹取』において新たなシンボリズムを獲得するのだ。天皇が支配する地上世界は、月にとって「流刑地」にすぎない。月で罪を犯したかぐや姫は、期限付きでこの「流刑地」=地上に「遠島・島流し」の刑に処されたのである。
さて、その月の世界の住人たちのイメージは「冷徹」「無感動」「高圧的」だ。自分たちの圧倒的優位をみじんも疑わない。一点のくもりもない純粋さのせいで、たとえ悪意があったとしても「悪」をかんじさせないほどなのだ。地上の最高権力者=帝と、その軍勢を圧伏する。「力」でかなう相手ではない。では、「情」はどうか。かぐや姫には竹取の翁(おきな)、媼(おうな)への個人的な恩義や親愛の情があった。「月」は、こうした人間的な感情と競合したり敵対したりするのだろうか?
いや当然、競合も敵対もしない。超越するのだ。月の住人=天人たちが、地上の人間の感情とぶつかり合ったり、共感し合ったりすることは絶対にない。競合も敵対も、同じような感情をもつ相手同士の関係から生まれる。わたしたちはカマキリやハエ、微生物やウィルスと同レベルの感情的関係をもつことがない。同じように、月の住人たちも地上の人間など眼中にないのである。
彼らには「感情がない」のだ。おそらく、法律(かぐや姫への刑罰/刑期を終えての回収)と利害関係しかないのだろう。非常にドライで、クールで権威的。そして、地上を「この穢(きたな)き所」と呼ぶのである。
物語の結末部でついに、かぐや姫は「天の羽衣」を着る。月の世界=天人たちの衣装である「羽衣」は、身にまとったとたんに地上の感情すべて払拭(ふっしょく)してしまう。
p65~66「 今はとて天の羽衣きるおりぞ君をあはれと思ひいでける
とて、壺の薬そへて、頭中将呼びよせてたてまつらす。中将に天人とりて傳(つた)ふる。中将とりつれば、ふと天の羽衣うち着せたてまつりつれば、翁をいとおしく、かなしと思しつる事も失せぬ。此衣(このきぬ)着つる人は、物思ひなく成りにければ、車にのりて、百人ばかり天人具して昇りぬ。」
『竹取物語 伊勢物語 大和物語』(日本古典文学大系/岩波書店/1957)
「今はもう最後、と天の羽衣を着るこの時にこそ、あなたのことをなつかしく思い出しますよ。
かぐや姫はそう歌い、頭中将を呼び、彼を通して不死の薬の壺を帝に差し上げる。天人は天の羽衣を中将に渡す。中将は受け取り、そのままかぐや姫に羽衣を着せ申し上げたところ、翁をいとおしく、親身に思っていた感情が消え失せた。この衣装を身につけた者は、感情が喪失されるので、そのまま姫は飛ぶ車に乗り、百人ほどの天人たちを引き連れ、天にのぼった。」
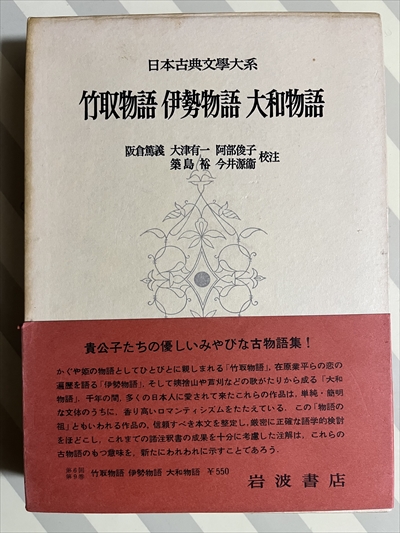
「感情が消失する」という物語の趣向以外に、天の羽衣には別の機能がある。それは、かぐや姫に「鳥」の属性を付与することだ。
鳥は太陽=王権のシンボルであり、天と地上を橋渡しする存在だった。しかし、この物語で「月」はその鳥を、太陽から奪うのである。今回のわたしのエッセイの文脈に引き寄せて解釈するなら、かぐや姫とは「月」と地上を橋渡しする「鳥」なのだ。鳥は月とのシンボリズムの関係を、新たに打ち立てたのである。
では、そのような「月」とはなんであるか?
王朝貴族社会である。あるいは、広く「都(みやこ)」といってもいい。感情のない殺伐とした統治機構や人間関係。利害にさとく、かんたんにひとを裏切り、ドライでクールで強欲な権力、支配、管理の世界だ。「月」卿雲閣(げっけいうんかく)とは、宮中の貴族たちをさすことばだった。
いやいや、待て待て。『竹取物語』では五人の貴公子たちの求婚譚を通し、王朝貴族がけちょんけちょんにコケにされたのではなかったか。「月」は、そういう地上の貴族たち皇子たちの欺瞞や退廃、浅慮や俗臭を超越する存在である。なぜ、月=宮廷貴族社会となるのか? おかしいではないか。
そういう疑問は正当である。具体的に、貴族社会を動かしていたのはひとりひとりの人間たちだ。そういう「人間」としての貴族らは考えが足りず、軽薄で、無能、不器用、かなしくも情けない存在だったろう。きわめて「地上的」「人間的」なのだ。この俗臭ふんぷんたる地上世界において、純粋で聖化されたかぐや姫ただひとりが燦然と輝き、孤高を保つのである。
しかし貴族たちから人間性を捨象した「システムとしての貴族社会」は別だ。非情、無感動、冷徹で権威的。抽象化されたものは、なんであれ純粋だ。非共通要素を捨象しているのだから当然である。純粋なものは理想化され、聖化される。これが「観念」の働きである。プラトンがイデアを称揚したのもむべなるかな。
要するに『竹取』で笑いものにされたのは具体的な貴族。帝を超越する「月」となったのは観念としての貴族社会(月卿雲閣)。わたしはそう考えている。そこは「豊饒の海」のように光り輝きながら、からからに乾いており、空虚である。
さらにわたしはそれを「都」とからめて考えている。「システムとしての/観念としての貴族社会」こそ「都」=月であり、地方や田舎はゆたかな人間性や笑い、諧謔にみちた平俗な地上世界なのだ。(続く)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
Twitter:https://twitter.com/OmoriHanon