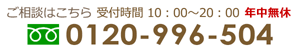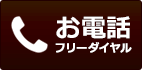表向きのコロナ収束ムードのおかげで、いろいろな日常が戻ってきている。もっとも、収束は「表向き」「ムード」にすぎない。第9波がはじまったという報道もある。感染がつづけば変異株が生まれつづける。感染力が強力で、致死率の高い株が発生しないように祈っている(いつもこんなことを書いている気がする)。
近所の大学も、ようやく図書館を一般に公開した。そこで自転車に乗って、気軽に大学図書館へ。用事があって街に出かけたり通勤したりするとき、構内を自転車で通過することはある。信号がないので、移動が速いのだ。しかし、図書館に入るのは、ほんとうに久しぶりである。
6月の大学図書館。樹木はあおあおと茂り、緑陰と陽光のきらめきはラベルの「水の戯れ」――ピアノの楽音のようだ。ふわふわ漂うポプラの種も、ゆるやかな風の動きを視覚化している。本来は目に見えないはずのものが目の前にひろがっている幻想風味がある。
館内もきわめて静粛だ。市立の図書館だと子どもの声や、時間を持て余した老人たちのおしゃべりが聞えることがある。しかし、大学の図書館には異質の時間が流れている。落ち着いた、集中力のみなぎる空間だ。そこにいるだけで、思考が研ぎ澄まされていくようである。
カウンターで入館カードを新しく作ってもらった。あんまり久しぶりなので、旧カードは完全に期限切れ。更新も不可。新しくカードを作るしかないそうだ。
目当ての本は2冊。
松村一男編『生と死の神話』宗教史学論叢9(リトン/2004)。
鈴木日出男『古代和歌史論』(東京大学出版会/1990)。
前者の神話学の本には、山田仁史「東南アジア・オセアニアにおける死の起源神話:〈バナナ型〉と〈脱皮型〉の分布に関する諸問題」という論考が所収されている。記紀における木花之佐久夜毗売(このはなのさくやひめ)と石長比売(いわながひめ)との対立概念については、以前もこのエッセイで述べた(第9回「コノハナノサクヤヒメたち」)。死と植物を組み合わせ、長命と鉱物に対立させるアイディアはひろく東南アジアに分布する神話イメージだという。ジェームズ・フレイザーはこれを「バナナ型神話」と名づけた。日本の歴史、文化、精神史の奥底に、この二項対立が根深く伏流しているとわたしは考え、ずうっと考察を深めようとしているのだ。
たとえば、「日本人の死生観には仏教的な無常感が通底している」といわれる。唐木順三は『無常』(筑摩書房/1965)で、次のように述べる。

p65「『大言海』には、「はかなし」は、「あとはかなし」(無痕跡)の略といふ一つの解があり、そこでは『伊勢物語』の中の「中空に立居る雲の跡もなく身のはかなくもなりぬべきかな」が引かれてゐる。「身もはなかくもなりぬべきかな」は、身があともなく消えて、むなしく、いたづらになるといふのであらう。そして、この歌の奥には、例の『萬葉集』巻三の沙弥満誓の、「世の中をなににたとへむあさびらきこぎいでし船のあとなきがごと」が内意されてゐるのであらう。そしてこの満誓は、最初に人生無常、世間無常を歌にした人として、しばしば巷間に云々されてゐるのである。」
しかし、満誓の歌に仏教感はうすいと疑っている。『万葉集』の無常観の背景には木花之佐久夜毗売神話が伏在しているのではないだろうか。
そうなれば、日本的無常観の根底に東南アジア「バナナ型神話」の死生観が存在することになる。ただ残念ながら、『生と死の神話』は図書館に所蔵されていなかった。うう。代わりに借りたのが、松村一男『神話思考Ⅱ 地域と歴史』(言叢社/2014)である。マレーシアやインドネシアの複数のバナナ型神話が紹介されており、参考になった。第9回のエッセイでは「バナナ型神話」ということばを、ポンと出しただけだ。ここで引用し、具体的にひとつ紹介しよう。
p251・インドネシアのスラウェシ(セレベス)島中央部のポソ地方、トラジャ族――「はじめ天と地は近く、人間は創造神が縄で結んで天空から下ろしてくれる贈り物を食べて命を保っていた。ある日、創造神は石を下した。最初の父母は、『この石をどうしたらよいのか、何か他のものを下さい』と神に叫んだ。神は石を引き上げて、バナナを代わりに下ろした。最初の父母は走り寄ってバナナを食べた。すると天から声があって、『お前たちはバナナを選んだのだから、お前たちの生命はバナナの生命のように短くなるだろう。バナナの木が子供をもつときには、親の木は死んでしまう。そのようにお前たちは死に、お前たちの子供がその地位を占めるだろう。もしお前たちが、石を選んだならば、お前たちの生命は石の生命のように不変不死であったろうに』」
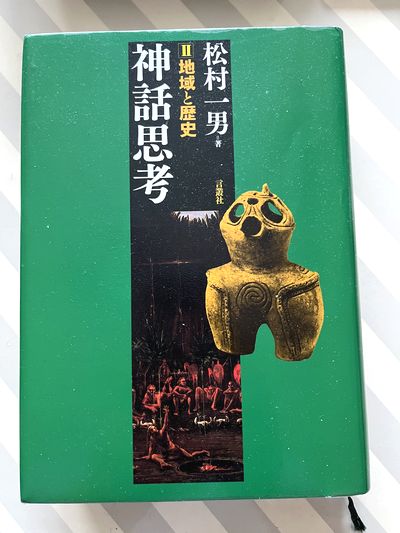
「バナナ=死」と「石=不死」というイメージが対立する。第9回エッセイで紹介した「木花之佐久夜毗売(このはなのさくやひめ)=短命」と「石長比売(いわながひめ)=長命」の対立と重なるのだ。ただし環太平洋地域、とくにインドネシアに普及している「バナナ型神話」と記紀神話のちがいは、「美醜」の概念であろう。
木花之佐久夜毗売は美しい。対して石長比売は醜いのである。つまり記紀においては、「美しいもの=長つづきしない」と「醜いもの=長つづきする」という対立概念が新しく付け加わっている。これが日本的美意識を深く規定し、江戸時代の「粋」や「野暮」となったのではないか、と考えるのだ。その影響はもちろん、令和の日本もこうむりつづけている。
わたしはこのふたり、さらにいえば「火山(信仰)の女神」ではないか、と疑っている。ま、それはまた機会のあるときに。この件、ひきつづき継続して調査、考察していきたい。
もう1冊、後者の鈴木日出男『古代和歌史論』を借りたのは、和歌における心物対応構造について知見を深めたかったからだ。鈴木のこの著作には「和歌の表現における心物対応構造」という論考が所収されている。初出は昭和45年(1970)の『国語と国文学』。これを読めば、おおまかなポイントを把握できるかと考えたが、甘かった。鈴木は万葉集から古今集、さらに歌物語や物語文学全般に心物対応構造を指摘し、考察する――そういう「古代和歌史」を構想しているのだ。
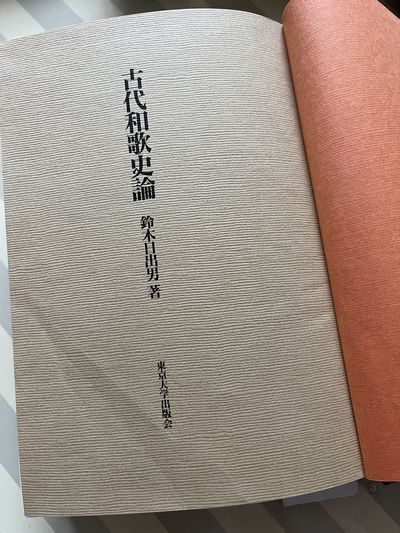
「心物対応構造」について、説明しよう。和歌のジャンル分けにはいくつか方法があるが、次のようなものもそのひとつである。
A 寄物陳思(きぶつちんし)
B 正述心緒(せいじゅつしんしょ)
Aは「ものによせておもいをのべる」と訓読し、Bは「まさにしんしょをのべる」と読む。たとえば「ながらへばまたこのごろや偲(しの)ばれむ うしと見し世ぞ今は恋しき」(藤原清輔)などは、正述心緒歌の好例だろう。
一方、特に「物象」と「心情」を対応させ(見立てたり、たとえたり)、和歌を構想するAの寄物陳思歌は万葉集の時代から盛んである。
たとえば伊勢物語19段の次のエピソードを、鈴木は引用する。短いので全文掲載しよう。
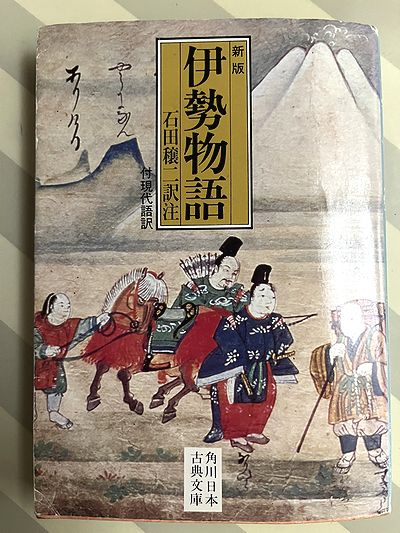
p30
むかし、男、宮仕へしける女の方に、御達(ごたち)なりける人をあひ知りたりける、ほどもなく離(か)れにけり。同じ所なれば、女の目には見ゆるものから、男は、あるものかとも思ひたらず。女、
天雲のよそにも人のなりゆくか さすがに目には見ゆるものから
とよめりければ、男、返し、
天雲のよそにのみして経(ふ)ることは わがゐる山の風はやみなり
とよめりけるは、また男ある人となむいひける。
石田譲二訳注『新版 伊勢物語』(角川日本古典文庫/1979初版/1991第18版)
角川文庫の脚注では「御達」を「普通の女房とはやや別格の女房の呼称」と説明している。岩波古典文学大系では単に「女房」とし、「紀有常の女という。御は婦人への敬称。女房であった人を。」と説明し、訳す。「紀有常の女」は「きのありつねのむすめ」と読む。同様のシチュエーションのふたりの贈答歌が、古今集の恋五に収録されている。
「風はやみ」は「風速み」。「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」の「はやみ」と同じだ。「●を〇み」で「●が〇なので」と訳すから、「み」には理由、原因の意味がある。「風はやみ」は文法通りなら「風をはやみ」だが、「風はやみ」でも「風がはやいから」となるだろう。以下、大意。
むかし、ある男(在原業平)が、宮仕えしている先で紀有常の娘と親密になった。だが、しばらく後、男は女のもとを訪問しなくなる。娘が仕えている宮中には、男も出勤していたので、女は業平をたびたび見かける。しかし、彼は彼女に目もくれない。そこで、女は次のような歌を送った。
空ゆく雲がどんどん遠く離れていくように、あなたはわたしから離れていきましたね。そうはいっても、同じところで働いているので、お姿をお見かけしますけど。
業平は次のように返した。
空ゆく雲のように、ひたすら離れていくのは、雲であるわたしがいた山の風が激しく吹き飛ばしたからです。
彼がそのように歌を詠んだのは、娘の方にまた別に親密な男がいたからだという。
ここでは人物や心情が物象に仮託され、表現されている。「雲」は業平、「山」は御達(紀有常の娘)、そして「風」は彼女の背信だ。
心物対応構造――寄物陳思の和歌の概念、ご了解いただけただろうか。
さて、話はこれからである。
源氏物語の構想の背景に、以上の寄物陳思の発想が伏在しているのではないか、とわたしは数十年、考えつづけているのだ。先走って結論めいたことを述べれば、源氏物語における「風」はおおむね、男性貴族や帝の愛情や求愛行為の象徴である。また、「花」は女性たち。1990年代後半、現代語訳を完成させた瀬戸内寂聴も「源氏は、登場する女性たちが不幸になったり、仏門に入ったりする物語」といった趣旨の発言をしたと記憶している。大雑把な要約だが、源氏物語のテーマの説明として、ひとつの社会通念になっていると考える。
それを、わたしの関心に引き寄せて言い換えれば、こうなる。つまり、「寄物」では「吹きまくる風が花を散らす」ように表現され、「陳思」では「男性の愛情が女性を不幸にする」と主題化されるのだ。
そうなれば、まず大きな和歌的な発想があることになる。次に構想としての物語がくる。最後に作中登場人物が詠む約800首の和歌が存在するわけだ。「たったひとつの大きな和歌>物語>約800首の小さな和歌」という入れ子構造。
例によって、まったくの門外漢が勝手な思いつきを述べている。そもそも紫式部が書いたテキストは存在しない。複数の異本があるなかで、作者の意図を推測するには、異本相互の関係を考察する(校合)必要があるはずだ。そんな手間をはぶいて、好き勝手なことを述べようとしているので、学問的には失笑ものである。また、現在の研究動向などもわからない。トンチンカンで的外れな内容であることはまちがいあるまい。ひょっとしたらすでに誰かが丁寧に考察し、また別の誰かがさらに丁寧に否定しているアイディアかもしれない。なにしろ、1000年前のテキストなのだ。
しかし、このエッセイはかなり自由なしろもの。一般の出版社の印刷刊行物、デジタルマガジンならあるはずの、編集サイドの横槍、口出し、手取り足取りの「あやつり」がない。ほとんど、なにを書いても自由。ま、逆にこわくもあるが、「本の話」ならよいのだ。わたしもすっかり甘えてしまい、好き勝手をやらせてもらっている。いつも本当にすみません(ぺこり)。
というわけで、以下で先ほどの考察をくわしく述べていく。
源氏物語の女性たちはみな「花」か、という疑問があるだろう。この疑いは正しい。「花」――つまり木花之佐久夜毗売ではないキャラクターも登場する。代表的なのは明石の君だ。源氏の最愛の女性である紫の上が、ばっちり木花之佐久夜毗売であるのに対し、明石の君の属性は石長比売的である。
とはいえ、明石の君は決して醜いわけではない。作中ではっきり醜女(しこめ)として描かれるのは末摘花だ。彼女には「花」と「石」の両方の印象がある。「花」は紅花(=末摘花)ではなく「藤」のイメージで、わたしは認識している(蓬生)。ただ、源氏の愛情=風が、それほど吹かないのだ(「末摘花」の巻では源氏の求愛シーンで風が吹く。彼女の素顔を目にするまで、源氏は好意を寄せているからだ)。だから、散ることがない。ふたりの関係は愛情……というより、現代的なことばだが「信頼」「信用」といった方がいいだろう。
一方、はっきりと鉱物系の名前の明石の君は、どれだけ「風」が吹いても平気だ。いや、彼女にとって「風」は、むしろ有利にはたらく。
若紫の巻の冒頭で、北山訪問中の源氏はまず、明石入道と明石の上の噂話を「耳」にする(「かいりうわうのきさきになるべき、いつきむすめなンなり」=「海竜王の妃になるように、大切に育てられている娘であるようだ」)。その直後、隠れ住む尼君と紫の上の姿を「目」にする。ふたりの対立は作品構想的に、はっきりと打ち出されているのだ。のちに、紫の上は「絵合(えあわせ)」の巻で源氏と絵を描くことになり、明石の君は「松風」の巻で源氏と楽器を演奏することになる。つまり、紫の上は視覚性が優位にくるキャラクターで、対して明石の君は聴覚性が優位にくるキャラクターである。
まず、紫の上から考察しよう。
思慕する義理の母親、藤壷ゆかりの少女である若紫をなんとかわがものにしようと、源氏は仲介役を期待する僧都にはたらきかけるが、冷淡に対応される。しかし、少女への源氏の関心は高まる。
p256~257「君(光源氏)は心ちもいとなやましきに、雨すこしうちそそぎ、山風ひややかにふきたるに、瀧のよどみまさりて、音たかく聞ゆ。」(若紫『湖月抄・上』)
と「風」の描写につながっていく。
このシーン、煩悩をさとし、悟りをなすことの大切さを僧が語る一方、煩悩に心を悩まし、心の闇に深く沈み、女性(藤壷の身代わりとしての少女)に傾倒、執着する源氏の心情を描いている。
したがってこのあと、源氏はこんな和歌を詠むのだが、煩悩の「夢」がさめたとはとうてい思えないのだ。
p262「ふきまよふみ山おろしに夢さめて 涙もよほすたきのおとかな
(吹き荒れる山からの風に煩悩の夢が覚めて、滝の音にも涙をもよおす)」(若紫)
その証拠に、邪魔な尼君が亡くなり、経済的な後ろ楯(少女の父、兵部卿宮)にも見放されそうになると、その少女に対する源氏の愛情は燃え上がる。「いまはまろぞおもふべき人。なうとみ給ひそ」といって強引に距離をつめる。「いざたまへよ。をかしきゑ(絵)などおほく、ひいなあそび(雛遊び)などする所に」
p290「あられ(霰)ふりあれてすごきよ(夜)のさまなり。」
p291「夜ひとよ風ふきあるる(吹き荒れる)に」(若紫)
源氏がひとまず、少女の住まいから退去したあと、父親の兵部卿宮があらわれ、その庭が荒れているのにおどろく。
p293「としごろよりもこよなうあれまさり(数年来、このうえなく荒れまさり)、ひろうものふりたる所の(広く、なんとなく古びた場所で)、いとど人ずくなにさびしければ(ますます人数少なく、さびしいので)」(若紫)
男君や女君の登場する王朝物語では、荒れ果てた庭の描写は住人の経済力の欠如、男運のなさ、などを示している。しかし、この描写、「風」による植物の荒廃と見ても矛盾しない。もともと手入れされず荒れた庭が、「風」のせいでいっそう荒廃したのである。
源氏の愛情と庭園荒廃は、矛盾した二面性をもつ。愛情をかけず疎遠になると、女君は経済的に困窮し、庭園が荒れる。一方また、深く愛情をかけても「風」が吹き荒れ、庭園が荒れるのだ(野分)。いちばんよいのは、経済的援助だけを受け、愛されないことである(たとえば末摘花の立ち位置)。
つぎに明石の君について考察しよう。
朧月夜との密会を右大臣、弘徽殿女御に知られた源氏は、須磨へ単身、渡ることを決意する。そして海辺で神に祈り、罪、穢れ、災禍などを祓う儀式をおこない、歌をつくる。
p630「『やほよろづ(八百万)神も哀(あわれ)と思ふらん おかせるつみ(犯せる罪)のそれとなければ』
とのたまふに、にはかに風ふき出でて、空もかき暮れぬ。……よろづ吹きちらし、又なき風なり。」(須磨)
突然の暴風雨である。これは藤壷との密通事件がありながら、「わたしは潔白です」という和歌を詠んだ源氏に対する天、神の怒りの表現だ、と解釈されることがある。しかし、この「風」が機縁となり、源氏は明石へ渡ることになるのだ。つまり、明石の君への橋渡しとなるのが「風」だ。つづく明石の巻も冒頭は風の描写からである。
p634「なほ風やまず、神なり(雷)しづまらで日頃になりぬ(おさまらずに数日たった)。」(須磨)
紫の上から、源氏のようすを尋ね、都の状況を知らせる手紙が届く。京でも異様な風が吹いているらしい。その翌日も吹きつのる。「其又(その、また)の日の暁(あかつき)より風いみじう吹き、鹽(しほ=潮)たかうみちて(高く満ちて)、浪の音あらきこと、いはほ(巌)も山も残るまじき気色なり。」 源氏の寓居は一部、落雷し、炎上する。被災した彼は、うたた寝に故桐壷院(光源氏の父)の夢を見る。そして亡くなった父親から「住吉の神のみちびき給ふままに、はやふなで(舟出)して、このうら(浦)をさり(去り)ね」と助言される。暴風がやむやいなや、明石の入道(明石の君の父親)から迎えの舟がくる。入道もお告げの夢(住吉の神?)を見ている。「あんな暴風のなか、どうやってこの浦にたどりついたのか……」と疑問に思うと、「あやしき風ほそうふきて(細く吹いて)、此浦(このうら)につき侍ること、まこと神のしるべ(導き)たがはずなん」と迎えの使者はいう。源氏が舟に乗りこむと……
p645「れいの風いできて、とぶ(飛ぶ)やうにあかし(明石)につき給ひぬ。ただはひわたる(這い渡る)程は、かたときのま(片時の間)といへど、なほあやしき(怪しき)までみゆる(見ゆる)かぜ(風)のこころなり。」(明石)
都では若紫の庭を荒した「風」が、「明石」では源氏と明石の君を結びつけるはたらきをする。まず、雷雨、暴風が明石の入道、源氏にとって夢の予兆となる。入道は神秘的な「順風」のおかげで、源氏を須磨から明石へ移すことができた。ふたりはしだいに親交を深めるが、父入道は源氏に、娘(明石の君)のことをなかなか打ち明けられない。その口火を切ったのは、琴や琵琶による源氏との合奏。彼はここで娘の琴の音を「松風」にたとえ、その存在を源氏にほのめかす。彼が明石の君に傾倒していく理由には「浜風」が添えられる。
p665「あかし(明石)には、例のあき(秋)ははま(浜)風のこと(殊)なるに、ひとりね(独り寝)もまめやかにものわびしうて、入道にもをりをり(折々)かたら(語)はせ給ふ。『とかうまぎらはして、(明石の君を)こち参らせよ』とのたまひて……」(明石)
明石の君も先夜、源氏が演奏する琴の音を「風につけて」聴いている。そしてとうとう会った明石の君は、源氏によって六条御息所と比較される。その後、源氏は都に残した紫の上の立場をはばかり、明石の君のもとへ通わなくなる。その間、彼は「絵」を描きためる。同じころ、紫の上も、絵日記を描きためている。
【視覚】かいま見―紫の上=源氏―絵画―花
【聴覚】 噂 ―明石の君=源氏―音楽―石
紫の上が「花」に比定される理由はいくつかあるが、なんといっても彼女が「紫のゆかり」だからだ。源氏の両親は桐壷帝と桐壷の更衣。「桐壷」とは皇居の淑景舎(しげいしゃ)。日本語では「区切られた空間」を「つぼ」と呼ぶことがある。「ひと坪(つぼ)300万円」とか「局(つぼね)=宮中や貴人の邸宅で、そこに仕える女性の居室として仕切った部屋」とか。したがって「桐壷」は「その部屋の庭に桐が植えられている居室」である。この「桐」が紫の花を咲かせる。
桐壷の更衣の死後、嘆き悲しむ帝は更衣とよく似た面影の女性を入内させる。藤壷の女御だ。「桐」「藤」と紫の花である。紫の上は藤壷の姪であり、その面影を宿している。したがって「紫の上」の名のなかに「花」のイメージが含意されているわけだ。
明石の君の石長比売性は、単に「石」の字面だけではない。明石一族大繁栄の立役者になるからだ。源氏の子どもを結局、出産しなかった紫の上に対し、明石の君は源氏との間に明石の姫君を生む(紫の上の養女になる)。この姫君が入内し、女御となり、若宮を生むのだ。紫の上は、女三宮に源氏の正妻格を奪われ、不運のうちに生涯を終える。対して、明石の君は娘のおかげで、繁栄を享受する。
ところで明石の巻におけるこの物語、あまりに竹取物語に似ている。光源氏と明石の君は「かぐや姫」に、明石の入道は「竹取の翁」に比定されるだろう。
日本の古代では、美しさを「光り輝くもの」とイメージする感性があった。伝説の衣通姫(そとおりひめ)は、あまりに美しく、全身の輝きが衣服の繊維の隙間から洩れたという。「かぐや姫」の「かぐや」も「輝く」から命名された。ネーミングの発想が光源氏と通じるのだ。明石の君の「明」にも、通じる。
かぐや姫は月の世界でなんらかの罪をおかしたらしい。その刑罰として地上に送られ、一定の期間、滞留することになった。源氏の須磨・明石滞留は表向き自主的な判断だが、朧月夜との関係が政敵の右大臣サイドから疎まれ、後難を避けたところがある。どちらも貴種流離譚だ。
また、かぐや姫には五人の求婚者があらわれ、最後には帝にまで求愛される。しかし、月世界の美女である彼女はこれらをことごとく拒み、忌避しようとする。同様に、明石の君は地方の有力者からのあまたの求愛を拒みつづけた。「海竜王の妃になるつもりか」とからかわれた。気位が高く、頑固である。
竹取の翁はそんなかぐや姫の頑なさに困惑し、ふりまわされるが、明石の入道はむしろ娘の判断と同意見――いや、彼女が求婚を拒みつづけた背景には、父親の野心があるのだろう。受領階級である彼は「京」という中央貴族社会の華やかさを捨てた。そして地方の富を独占し、財政的優位を築く。「名=花」を捨てて、「実」を取ったのだ。それでも、裕福で、娘を愛する父親のイメージは竹取の翁に通じるだろう。
「若紫」の噂で登場したときの明石の君は18歳。9年後の「明石」の巻で登場した明石の君も18歳。27歳ではない。都ではカレンダー通り時間はすすみ、源氏は年を取り、若紫も成熟し、紫の上になっていた。この明石では時間が流れていない。この矛盾は一般に次のように考えられている。
p30~31「ここで話題の娘は、後に光源氏が明石の地で巡り合う播磨国の元の国守、明石入道(あかしのにゅうどう)の娘の明石の君である。父の入道が家の将来を託すべく祈願してきた特別な娘で、その祈願の歳月からして、明石の地で光源氏が巡り合う頃には明石の君は少なくとも十八歳である。だとすると若紫巻の時点では九歳ということになるが、多くの求婚者の求愛を受け、断り続けているという若紫巻の話の印象からは、ややかけ離れている。逆にこの時点ですでに適齢期だとすれば、明石巻で光源氏と結ばれる時には二十台半ばになってしまう。この明石の君の年齢が、光源氏の時間の進行と辻褄が合わないという物語の歪みは、『源氏物語』の成り立ちと関わっていようか。もとは独立した短編的なエピソードに過ぎなかった物語が、光源氏の物語の一角に据えられることで長編性を獲得したという、物語の成長過程を想像させる端緒でもある。(中略)明石の君の年齢など、光源氏の物語の時間的進行とは矛盾を抱えるが、それは『源氏物語』が既存のより小さな物語を吸収しながら、より巨大な物語に成長した可能性を示唆していよう。」
高木和子『源氏物語を読む』(岩波新書/2021)
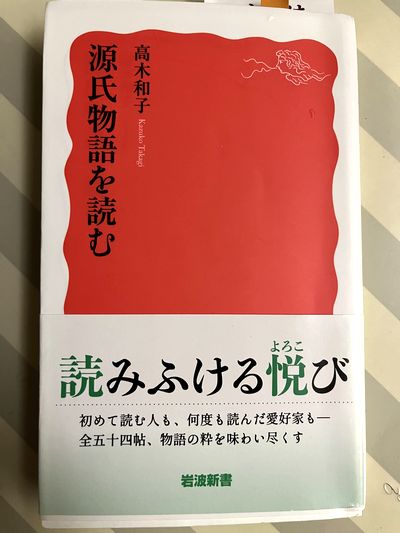
現在のような54帖の統一的全体像は最初から構想されていたわけではない。光源氏を主人公にした色好みの物語を短編で書いているうちに、しだいに人気が出て、長編化していったというのだ。したがって、書き足していった後続篇には、先行編の設定と辻褄の合わない「瑕疵(かし)」がある。そういう考えである。おそらく、そうだろう。
しかし、竹取物語に引き寄せたら、明石の君の年齢の矛盾も「明石と都で時間の流れ方がちがう」というネタをあえて披露した筆の余裕にも思える。竹取物語には、月の世界と地上では時間の流れ方がちがうことをうかがわせる台詞があるのだ。
p52「『汝、おさなき人、いさ々かなる功徳(くどく)を翁つくりけるによりて、汝が助けにとて、かた時ほどとて下し々を、そこらの年頃、そこらの金(こがね)給ひて、身をかへたるがごとく成りにたり。かぐや姫は、罪をつくり給へりければ(罪をおかしなさったので)、かく賤(あや)しきをのれがもとに(このように卑しいおまえの所に)、しばしおはしつる也(しばらくいらっしゃったのだ)。罪の限(かぎり)果てぬればかく迎ふるを、翁は泣き嘆く、能(あた)はぬ事也(泣いて嘆いても無駄なことである)。はや出したてまつれ』と言ふ。翁答へて申(もうす)、『かぐや姫を養ひたてまつること廿餘年(にじゅうよねん)に成りぬ。かた時との給ふに(ほんの少し、とおっしゃるけど)、あやしく成り侍りぬ(不審でございます)。又異所(また、ことところ=別の場所)に、かぐや姫と申す人ぞおはすらん(いらっしゃるのでしょう)』と言ふ。
『竹取物語』阪倉篤義校訂(岩波文庫/1970初版/2000第48刷)

月から降りてきた天人は「かた時」という。対して翁は「20年あまり」という。月と地上で時の流れがちがうのである。
したがって、明石の君の年齢の矛盾に気づいた読者のなかには「ああ。竹取物語のかぐや姫だな」と連想をはたらかせ、にやりとしたひとがいたのではなかろうか。京の都で9年でも、明石では「かた時」なのだ。これまた、わたしの勝手な思いつきである。すでに誰かが指摘しているだろう(そしてきっと、やんわり、あるいは笑いながら否定されている)。【以下、第21回に続く】
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon