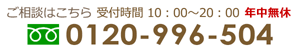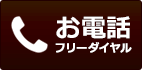毎日、コロナコロナでうんざり。
わたしもフリーであちこちの職場に出向き、あれこれの仕事をしている身である。札幌雪祭り後の新型コロナウィルス感染拡大の状況をかんがみ、クラスター回避のため、仕事が激減。ヒマになり、本を読めるのはいいことだが、収入が!
落城寸前の城のように、松の木の皮をはぎ、土を煮込んで食べる生活が間近に迫ってきた(誇張あり)。
そんなある日、やはり札幌在住の作家である松本寛大さんから連絡がくる。
「高城高先生と会って、新作についていろいろお話をうかがいます。大森さんもご一緒にどうですか」
「いくいく!」
高城高といえば、「日本ハードボイルドの嚆矢」としてミステリ文学史に必ず名前が挙がる伝説の作家である。1955年、デビュー作「X橋付近」が雑誌「宝石」の懸賞小説に当選し、江戸川乱歩が激賞。その後、「宝石」を中心に活躍する。しかし新聞記者の仕事が忙しくなり、長い休業に入った。ようやく2006年、仙台の出版社「荒蝦夷(あらえみし)」から出された傑作集が「すごい」と話題になり、劇的に復活。東京創元推理から過去作品を「全集」として文庫で刊行(現在、入手がむずかしい)。再評価の波に乗って、09年新作『函館水上警察』シリーズを同出版社から上梓した。
その後、バブル期の札幌を舞台にしたキャバレーの黒服、黒頭(くろず)シリーズ3部作を完結させ(12~16年)、近年は『ウラジオストクから来た女/函館水上警察』(10年)の表題作の短編「ウラ……女」からのスピンオフ作品『〈ミリオンカ〉の女/うらじおすとく花暦』(18年)を完成させていた。

昭和10(1935)年生まれ、というから、今年で85歳。まさに「生きた伝説」である。高城高に匹敵する札幌の作家は現在、SF第1世代に当たる荒巻義雄ぐらいだろう。
コロナのせいで緊急非常事態宣言が出された街である。高齢者が感染すると重篤になる、という話だ。人の多い街中にご自宅からお越しいただき、感染させたらたいへんだ。
「大森と松本のせいだぞ」
「あのふたりが札幌の至宝を危険な目にあわせた」
「あまりに軽率、思慮が足りない」
と糾弾されるのは必至。
先日も北海道知事が臨時記者会見を行った(4月9日)。自覚症状があるにもかかわらず飛行機に乗って東京から来道し、陽性反応が出て道内のコロナ患者にカウントされた方がいたそうだ。会見時、道知事の口調は厚労省大臣、国交省大臣の手際の悪さ、また不用意に感染を拡大させてしまう危険を冒す市民へのいら立ちをにじませていた。インタビューを行った日(4月1日)はまだ、首相の新型コロナ緊急事態宣言の前であったが、予断の許されない状況であった。
さて今回、お話は高城高の新刊『仕切られた女/ウラジオストク花暦』についてである。刊行されたのは、今年の2月中旬。
「ほんとうは昨年12月に出る予定でしたが、いろいろありまして……」
と高城先生。わたしたちは札幌中心部の某ホテルの喫茶店で取材を行った。先生と松本さんは珈琲、わたしは紅茶を注文。この紅茶がとにかくうまい(!)。
『仕切られた女/ウラジオストク花暦』は、サブタイトルから推測できるとおり、『〈ミリオンカ〉の女/うらじおすとく花暦』の続編である。
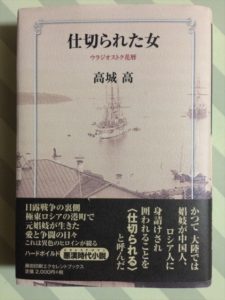
複雑な事情のもと、ロシア商人ペトロフの養女となったエリサヴェータ・ギン・ペトロヴァ。函館で生まれた彼女は、ウラジオストクの〈日之出楼〉という妓楼(ぎろう)で「浦潮吟(うらじおぎん)」を名のり、若くして花形娼妓(しょうぎ)であった。しかし、ペトロフに引き取られてからは当時の国際教養語であるフランス語を学び、貴婦人としてのマナーを身につけ、「令嬢」として認知されていく。
松本さん「ウラジオストクという街に注目され、一種の都市小説のおもむきです。何か思い入れや作品的な狙いがあったのですか?」
高城先生「実際にウラジオには2011年に取材に行きましたし、思い入れのある街です。以前にも日本の近代が1890年代に成立したという考えを、『ウラジオストクから来た女』の〈あとがき〉で書いたと思いますが、漢人、満人、ロシア人、日本人、朝鮮人(※当時の呼称で示します)が入り乱れ、国際色豊かな北の街を背景に、庶民の歴史を描き、残したいと思ったのです」
わたし「将軍や政治家が登場する歴史は国レベルの話になりますが、庶民の歴史は街レベルが規模としてちょうどよさそうですね」
高城先生「また、海外進出する日本の尖兵として成功する〈お家芸〉といってもいいのが、当時、妓楼産業だったのです。世界に類を見ないほど発達を遂げ、巧妙な仕組みを官民協力して作り上げた。これはまったく名誉なことではありませんが、小説的にはドラマがある。浦潮吟(うらじおぎん)は、ここに出自をもつヒロインでありながら、ロシア商人の養女となり、仕事の面でも私生活でも、国際的な対外関係を結んで活躍していきます。東北アジアの明治末年、外国交流の要衝で、激動の人生背景を持つ――となれば、娼妓をヒロインにするのがふさわしいと思ったのです」
バブル期のススキノを舞台にしたシリーズ小説も書かれていることを、わたしは連想した。「夜の街」を通し、資本の動きに翻弄されるひとびとを歴史的に記録するという発想は、よくいわれているが、高城高のジャーナリストとしての資質(元新聞記者)に負うところなのだろう。
作中に説明があるが、タイトルの「仕切られる」とは「娼妓がロシア人や中国人に身請けされ、その妻妾となること」である。吟自身はあくまで「養女」であるが、立場的には「仕切られた」のと同じ、と作中人物から指摘されるシーンがある。莫大な借金を背負わされ、貧しく虐げられた女性が貴族的生活や経済的豊かさ、文化的教養を享受する立場となる。こういう設定なら、社会階層の厚みを描けるのだ。
松本さん「『仕切られた女』では、とうとう日露戦争が描かれますが、戦後すぐにウラジオで水兵の暴動事件(1905)があり、街がたいへんな状況になったとは、知りませんでした」
高城先生「わたしは実のところ、シベリア出兵まで描きたかったんですよ。日本兵の蛮行を含め、ドラマチックな歴史の渦に巻きこまれた一般のひとびとの姿を。ただ、そこまで描いたら吟もおばあさんだ。ヒロインとしてはちょっとどうか、と思ってね」
松本さん「当時の資料には相当あたられた?」
高城先生「新聞はなるべく目を通しました。資料にあたるときは、『この時代、この街は面白いか、ハナシになるか』という視点で調査している。ロシア側の資料は克明に残っていましたね」
わたしは横でボケッと聞いているだけだが、果敢に質問する松本さん。
松本寛大さんは第1回「ばらのまち福山ミステリー文学新人賞」(作品は『瑠璃の家』というタイトルで講談社から09年に刊行)の受賞者。知り合ったときには講談社ノベルスから『妖精の墓標』(13年)を出しており、札幌で作家どうしの飲み会があると、親しくお話させていただくようになった。
松本さん「今度、引っ越しすることになったんですが、本が大量で。妻に処分するようにいわれ、困ってしまって、結局、捨てちゃったんですよ」
わたし「え? 奥さんを!?」
松本さん「そんなわけないでしょ!」
膨大な資料を読み込み、精緻な本格ミステリを発表しているが、ホラー小説にも造詣の深い作家さんだ。評論や書評の活動にも精力的である。
あ。そうだ。わたしも質問しなければ。
わたし「まさに町ネタを探す新聞記者の視点だと思います。歴史的事件へのこだわりは一種の写実主義で、先生のハードボイルドの文体にもマッチしています。しかし、目に見える情景をひたすらカメラのようにクールに描写するだけなので、登場人物の内面描写に乏しい。ヒロイン吟は不幸な生い立ちで、その後も人生でさまざまな波乱に巻き込まれていきますが、周囲の出来事に対し、彼女がどうかんじ、何を考えているか、いまひとつ、分からない。
それを補っているのが、『花が好き』という吟の設定だと思いましたが……」
高城先生「そう。花はいろいろ調べて丁寧に出しました。
吟の友人で実在の人物、エレノア・プレイも花が好きでね。ただし、エレノアは庭に咲いた花に関心があるんだけど、吟はむしろ野に咲く、野生の花が好きなのです」
わたし「何か可憐で、たおやか、はかない美しさのような……吟にはない部分を『花が好き』という設定が補っているように読んだのですが……?」
高城先生「花の名前はなるべく正確に、『ミリオンカ』では学名までつけて書きました。
日本の作家は往々、モノについての名前、呼び名が不正確で、いいかげんです。そういう風潮に対し、わたしは批判的なのです。言葉や言葉づかいに対しては厳格でありたいと思っています」
わたし「女性と花をからませて描く日本文学の伝統がありますが、するとこれも……」
高城先生「まったく関係ありません。
戦後、日本文学史の流れからまったく離れたところ――アメリカからハードボイルドが流入してきました。ハメットやヘミングウェイの影響を受け、自分の小説を書きはじめたのです。
ですが、ぼくはついにハードボイルドは書かなかった……」
松本さん「(え? 何をおっしゃっているのですか!?)」
わたし「(なぬ!? 先生、どうなさったんですか)」
わたし「や。あの……文体としてのハードボイルドと、ジャンルとしてのハードボイルドがあって。高城先生はたしかに、車や銃、酒、暴力と謎の美女が登場する大藪春彦的なジャンルとしてのハードボイルドはお書きにならなかった。しかし、より源流のヘミングウェイ的な、文体としてのハードボイルドを追及なさっている。こちらの方がより本質じゃないですか」
高城先生「ふむ。『農道を老婆が歩く』――ただそれだけの情景でも、描写スタイルによってハードボイルドになります。それこそが理想だと思っています。
また、事件を起こそうと思うのなら、魅力的なキャラクターを造形することです。そうすれば、その人物にふさわしい出来事が自然と立ち上がり、ストーリーが動いていきます」
わたし「……つながらない……高城先生と梶原一騎が……つながらない……(苦悩)」
(「キャラクター先行でストーリーを考案するのなら、梶原一騎じゃなく、小池一夫じゃないですか」と松本さんからあとでご指摘をいただきました。その通りでございます。うう……恥ずかしい)
インタビューはその後もつづいたが、わたしの記憶、印象に残っているのはだいたい以上の内容。ICレコーダーを所持していた松本さんがその後、北海道ミステリクロスマッチ(札幌とその近郊在住の作家集団のコンテスト作品を掲載している)のサイトにもっと詳細なインタビューをアップする予定である。そちらはより硬派な内容になるはず。ぜひご覧ください。
『仕切られた女』の粗筋は次の通り。
前作では、音楽家を志望するロベルト・レーピンという青年と関係を深めていた吟であったが、彼女の生い立ちのせいでこの恋愛はうまくいかず、あげく数々の不祥事がレーピン家を襲う。それは吟の養家であるペトロフ家も同様で、レーピン家とペトロフ家はウラジオを舞台に仇敵同士の一家になったおもむきである。そこに、ロベルトの新妻としてルイーゼ(ルルと呼ばれる)が登場。自分の夫のかつての恋人だと思っているのか、レーピン家の数々の不幸はすべて「この女」のせいだと思っているのか、吟に対して激しい敵意を燃やす。敵対関係にある、この二家族の確執は物語全体を貫き、吟やその周囲は時に窮地に陥り、生命の危険にさらされる。
一方、日露関係にはしだいに暗雲がたれこめ、ロシア帝国海軍の巡洋艦がウラジオストクに配備されることに。装甲巡洋艦リューリクの士官、ニコライ・ゼニーロフ大尉は吟を見初め、ふたりはしだいに仲を深めていく。しかし日露戦争へのカウントダウンは待ったなしで、街はやがて混乱と騒擾(そうじょう)に呑みこまれ、ひとびとの運命も大きく狂いだす……。
前作『ミリオンカ』にくらべ、軍人、満鉄職員、馬賊など登場人物が多彩になり、読みごたえ十分である。
ともかくコロナのせいで、紀伊國屋札幌本店ガーデンスペースで実施を計画していた刊行記念イベントも断念。他の書店のイベントも建物老朽化のため移転する予定があり、実施が難しい。せっかく本を出しても、外出自粛で書店にそもそもひとが行かない。せめてネットでも見てもらえれば――ということで『仕切られた女』お薦めです。(了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
Twitter:https://twitter.com/OmoriHanon